
「良い投資銘柄がなかなか見つからない」と悩んでいませんか?個別株の分析は時間がかかり、リスクも高いことから安定的な運用方法を探している方は多いはずです。
この記事ではインデックス投資の定義や代表的な指数、具体的な始め方などを解説します。記事を読めばインデックス投資の全体像がわかり、新たな投資先の選択肢が広がります。現在のポートフォリオを安定させるためにインデックス投資も検討してみましょう。
インデックス投資とは特定の指数に連動した運用を目指す投資方法

インデックス投資とは日経平均株価やS&P500など、特定の市場指数と同じ値動きを目指す投資法です。個別銘柄を選ぶ必要がなく、指数に含まれる多数の企業に自動的に分散投資できます。投資家は対応する投資信託を購入すれば、市場平均のリターンを狙えます。
インデックス投資は「パッシブ運用」とも呼ばれ、市場を上回る運用を目指すアクティブ運用とは対照的な投資手法です。年金基金や保険会社などの機関投資家もインデックス投資を採用しており、運用資産の土台として世界中で活用されています。
» インデックス投資信託の基礎知識や他の金融商品との違いを解説
インデックス投資の代表的な指数

インデックス投資で使用される代表的な指数は以下のとおりです。
- 日経平均株価(日経225)
- 東証株価指数(TOPIX)
- S&P500
- NYダウ平均
日経平均株価(日経225)
日経平均株価(日経225)は日本を代表する225社の株価から算出される指数です。日本経済新聞社が東証プライム市場から選定した企業で構成され、日本経済の動向を示す重要な指標です。投資家は日経平均株価指数に連動する日経225を購入すれば、日本の主要企業225社にまとめて投資できます。
日経225の構成銘柄は年に1回10月に定期見直しが行われ、常に日本経済の実態を反映する構成が保たれています。
東証株価指数(TOPIX)
東証株価指数(TOPIX)は東証プライム市場に上場する、ほぼすべての企業を対象とした株価指数です。東証株価指数は時価総額加重平均で算出されるため、企業規模が大きいほど指数への影響力が強くなります。TOPIXの構成企業で代表的なものは以下のとおりです。
- トヨタ自動車
- ソニーグループ
- キーエンス
- 三菱UFJフィナンシャル・グループ
- ソフトバンクグループ
TOPIXは約2,000社以上を対象としており、幅広い日本企業への分散投資が可能です。日本株式市場全体の実態に近い動きを示し、TOPIXは機関投資家のベンチマークとして広く活用されています。
S&P500

S&P500は米国を代表する500社の時価総額加重平均株価指数です。米国株式市場の時価総額の約80%をカバーしており、世界中の投資家が注目する重要な指標になっています。S&P500の代表的な構成企業は以下のとおりです。
- アップル
- マイクロソフト
- アマゾン
- エヌビディア
- アルファベット(グーグル)
S&P500は長期的に右肩上がりの成長を続けてきた実績があり、過去30年間の平均リターンは年率約10%を記録しています。配当をS&P500に再投資すれば、複利効果でさらに高いリターンが期待できる魅力的な指数です。
NYダウ平均
NYダウ平均は米国の代表的な30社で構成される株価指数です。NYダウ平均は1896年から算出されている歴史ある指標で、ダウ・ジョーンズ社が選定した優良企業のみで構成されています。NYダウ平均の構成銘柄数は30社と少ないものの、各業界のリーダー企業が厳選されています。
NYダウ平均では高額株の値動きが指数全体を大きく左右するため、投資の際は個別銘柄の動向にも注意を払うことがポイントです。NYダウ平均の銘柄数は他のインデックス投資先と比べて少ないですが、米国経済の動向を示す指標として世界中で注目されています。
インデックス投資のメリット

インデックス投資の主なメリットは以下のとおりです。
- 低コストで運用できる
- リスクを分散できる
- 初心者でも始めやすい
- 少額から投資ができる
- 市場全体の成長に乗れる
低コストで運用できる
インデックス投資はアクティブファンドと比べて、運用コストを大幅に抑えられます。機械的に指数と同じ銘柄構成にするだけなので、ファンドマネージャーの調査・分析コストがかからないためです。インデックス投資の信託報酬は年率0.1%未満の商品も多く、購入時手数料が無料のノーロードファンドが主流です。
長期投資では手数料の差が運用成績に大きく影響します。インデックス投資を30年間行う場合、信託報酬が0.5%違うだけで資産額に15%以上の差が生じます。
リスクを分散できる

インデックス投資は1つの商品で数百~数千もの企業に分散投資できます。分散投資で軽減できるリスクは以下のとおりです。
- 企業の倒産リスク
- 業界の景気変動リスク
- 地域経済の悪化リスク
- 為替変動リスク
複数の企業や業界、国に資産を分散させると、安定した運用が可能になります。市場全体が下落する場合を除けば、個別リスクの影響を最小限に抑えられる点がインデックス投資の大きな魅力です。
2008年のリーマンショックでは個別株で90%以上下落した銘柄もありました。しかし、インデックス投資のS&P500は約50%の下落に留まり、数年後に元の額まで回復した実績があります。
初心者でも始めやすい
インデックス投資は企業分析や銘柄選定の知識がなくても始められます。投資家は日経平均やS&P500に連動する商品を選ぶだけで、プロと同等の分散投資ができるためです。つみたてNISAの対象商品の多くがインデックスファンドであり、金融庁も初心者に適した投資方法として推奨しています。
インデックス投資は感情に左右されずに機械的な投資ができるため、投資経験の浅い方でも失敗しにくい点がメリットです。定期的な積立設定をすれば自動的に運用されるので、日々の株価チェックや売買タイミングの判断も不要です。
少額から投資ができる

インデックス投資は個別株のような単元株数の制約がなく、自分の予算に合わせて自由に金額を設定できます。インデックス投資は証券会社によっては100円から始められます。少額投資のメリットは以下のとおりです。
- まとまった資金が不要になる
- 毎月の積立が継続しやすい
- 投資の練習ができる
- リスクを抑えて始められる
インデックス投資を少額で行えば無理のない金額で、徐々に投資額を増やす戦略も取れます。毎日や毎週、毎月など積立頻度も自由に選べるため、給料日に合わせた柔軟な資産形成が可能です。
市場全体の成長に乗れる
インデックス投資は経済成長の恩恵を受けられる投資方法で、個別企業の成否に関係なく、市場の成長に比例して資産も増加します。米国市場は過去200年以上にわたって長期的な成長を続けており、S&P500は年平均約10%のリターンを記録しています。
インデックス投資は複利効果があり、長期的に右肩上がりの成長が期待できる点が魅力です。複利効果を味方につければ資産は雪だるま式に増加し、20年後には元本の数倍になる可能性もあります。
インデックス投資のデメリット
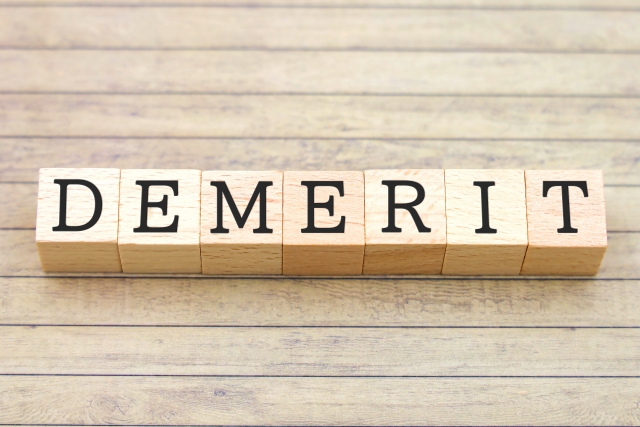
インデックス投資の主なデメリットは以下のとおりです。
- ハイリターンを狙いにくい
- 短期運用には向かない
- 元本割れのリスクがある
ハイリターンを狙いにくい
インデックス投資は市場平均のリターンを目指すため、個別株のような大きな利益は期待できません。数百~数千の銘柄に分散投資する仕組み上、一部の銘柄が急騰しても全体への影響は限定的です。
インデックス投資は年率10%を超えるような高いリターンを狙う投資家にとって、物足りない可能性があります。市場が停滞している時期はインデックス投資も同様に低迷します。短期間で資産を大きく増やしたい方は、個別株やアクティブファンドの併用を検討しましょう。
» 高配当株投資の正しい知識を伝授!
短期運用には向かない

インデックス投資は長期的な資産形成を前提とした投資方法です。短期間では市場の変動が大きく、元本割れのリスクが高まります。インデックス投資が短期運用に向かない理由は以下のとおりです。
- 複利効果を活かせない
- 売買手数料がかさむ
- 市場の一時的な下落で損失を受ける
- 税金の負担が増える
投資期間が5年未満の場合、市場の短期的な変動に巻き込まれやすくなります。インデックス投資の真価は10年、20年という長期間で発揮されるため、短期的な利益を求める投資家には適していません。
元本割れのリスクがある
インデックス投資は元本保証がなく、市場全体が下落すれば資産価値も減少します。リーマンショックやコロナショックのような経済危機では、一時的に30%以上の下落も起こり得ます。インデックス投資も購入タイミングによっては長期間の含み損を抱えるリスクがある点に注意しましょう。
過去の暴落からの回復期間を見ると、多くの場合は3~5年で元の水準に戻っています。インデックス投資ではパニック売りを避けて、保有し続ける忍耐力が試されます。
インデックス投資の始め方

インデックス投資を始めるために欠かせない、以下の項目を解説します。
- 口座開設の方法
- インデックスファンドの選び方
- 投資信託の購入プロセス
口座開設の方法
インデックス投資を始めるためには証券口座の開設が必要です。すでに1つ口座を持っている方も、手数料や商品ラインナップによっては2つ目の口座開設をしたほうがお得な場合があります。口座開設の手順は以下のとおりです。
- 証券会社の公式サイトにアクセスする
- 必要事項を入力する
- 本人確認書類をアップロードする
- 審査完了を待つ
- ログインID・パスワードを受け取る
証券口座では特定口座(源泉徴収あり)を選択すると確定申告が不要になり、税金の心配なくインデックス投資を始められます。ネット証券を選べばマイナンバーカードとスマートフォンで本人確認が完了し、最短で当日から取引が可能です。
インデックスファンドの選び方

インデックスファンドを選ぶ際は投資対象と手数料を重視しましょう。日本株や米国株、全世界株など、投資家の考えに合った地域や資産を選択します。インデックスファンド選びのポイントは以下のとおりです。
- 信託報酬の低さ
- 純資産総額の大きさ
- 運用実績の安定性
- 分配金の有無
インデックスファンドの信託報酬は年率0.2%以下を目安に選びましょう。インデックスファンドの純資産総額が100億円以上あれば、繰上償還のリスクも低くなります。同じ指数に連動するインデックスファンドでも運用会社によって手数料が異なるため、比較検討が大切です。
投資信託の購入プロセス
投資信託の購入は証券会社のWebサイトやアプリから簡単に手続きできます。投資信託の購入方法は以下のとおりです。
- 商品を検索して選択
- 目論見書を確認
- 購入金額を入力
- 決済方法を選択
- 注文内容を最終確認
- 取引パスワードで認証
投資信託で積立投資を希望する場合は毎月の購入日と金額を設定すれば、自動的に買い付けが行われます。クレジットカード決済を選べばポイントも貯まり、お得に投資を続けられます。投資信託の約定日は注文の翌営業日となり、受渡しは3営業日後が目安です。
インデックス投資で失敗しないためのポイント

インデックス投資で失敗しないためのポイントは以下のとおりです。
- リスク許容度を理解する
- 継続的な積立投資を心がける
- 定期的にポートフォリオを見直す
リスク許容度を理解する
リスク許容度とは投資で損失が出た場合に精神的・経済的に耐えられる限界です。投資家は年齢や収入、資産状況、家族構成によって許容できるリスクが異なります。30%程度の株価下落に耐えられない方が株式100%のポートフォリオを組むと、市場急落時にパニック売りをしてしまいます。
証券会社の無料診断ツールを活用し、自分に合った資産配分を見つけましょう。リスク許容度は生活環境の変化で変わるため、ポートフォリオの定期的な見直しも必要です。
継続的な積立投資を心がける

積立投資は毎月決まった金額を投資する手法です。積立投資は「ドルコスト平均法」の効果を得られます。ドルコスト平均法とは定期的に同じ金額で購入を続ける投資手法です。
株価1万円のときに1万円投資すれば1口購入でき、株価5,000円に下落したときは2口購入できます。価格が高いときは少なく、安いときは多く購入する仕組みにより、投資家は平均取得単価を抑えられます。
積立ドルコスト平均法では投資タイミングを考える必要がなく、感情に左右されずに機械的な投資を続けられる点もメリットです。月1万円の積立でも20年続ければ複利効果で資産は大きく成長し、相場の変動を味方につけた資産形成が可能になります。
定期的にポートフォリオを見直す
ポートフォリオは時間とともにバランスが崩れるため、定期的な見直しが必要です。株式が値上がりすれば株式比率が高まり、想定以上のリスクを取ってしまう可能性があります。ポートフォリオ見直しのポイントは以下のとおりです。
- 年1回の定期チェックを行う
- 当初比率から5%以上のずれを確認する
- ライフステージの変化に応じてバランスを見直す
ポートフォリオのバランスを見直す手段の一つに、ノーセルリバランスと呼ばれる方法があります。ノーセルリバランスとは保有資産を売却せずに、新規資金でポートフォリオ比率の低い資産を多めに購入する投資手法です。比率が小さくなった資産を追加購入することで、当初の資産配分に戻せます。
インデックス投資で資産形成を着実に進めよう
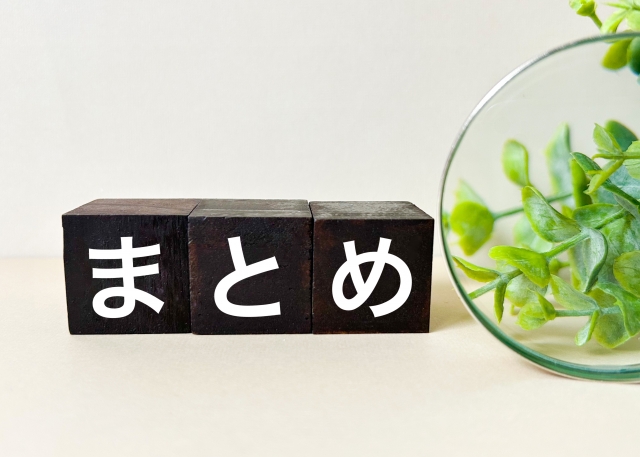
インデックス投資とは市場指数に連動する運用を目指す投資方法です。個別銘柄の分析が不要で、低コストで分散投資ができる点がインデックス投資の魅力です。インデックス投資は少額から始められ、長期的な資産形成に適しています。
すでに投資を始めている方もインデックス投資を組み合わせれば、より安定したポートフォリオを構築できます。少額から始めて、インデックス投資でコツコツと資産形成を始めましょう。