
- どの金融商品に投資すればいいか迷っている
- 個別株だけでの運用に限界やリスクを感じている
- 投資信託の種類が多すぎてどれを選べば良いかわからない
投資信託について理解せずに始めると、思わぬ損失につながります。この記事では投資信託の基礎知識や種類、メリット・デメリット、選び方をわかりやすく解説します。記事を読めば、自分の目的やリスク許容度に合った商品を見極めるヒントを得ることが可能です。
投資信託への投資で失敗しないためには、自分に合ったファンドを選ぶ必要があります。手数料や運用実績をしっかり比較し、分散投資でリスクを抑えながら賢く資産を育てましょう。
投資信託とは投資家から集めた資金をプロが運用する金融商品

投資信託は投資家から集めた資金を1つのファンドにまとめ、資産運用の専門家が運用する金融商品です。投資信託の投資先は運用のプロであるファンドマネージャーが選びます。投資信託では株式や債券などに分散して投資できるため、個人が1つの銘柄を運用するよりもリスクを抑えることが可能です。
運用成果によって発生した利益や損失は出資額に応じて投資家に分配されます。投資信託は投資の専門知識がない方でも、手軽に複数の資産へ分散投資できる点が大きな魅力です。
» 株の配当に関する基礎知識から高配当銘柄の選び方まで解説
投資信託の種類

投資信託には投資対象によって複数の種類があり、積極的に利益を目指す商品から安定した成果を求める商品まで多様です。代表的な投資信託である以下について解説します。
- 株式投資信託
- 債券投資信託
- バランス型投資信託
- マネーマーケットファンド(MMF)
株式投資信託
株式投資信託は国内外の会社の株に投資する金融商品です。ファンドマネージャーが複数の企業の株式に分散投資することで、1社に集中するリスクを避けられます。株式投資信託の収益源は株価の値上がりによる売却益(キャピタルゲイン)と、企業から受け取る配当金(インカムゲイン)です。
株式投資信託は運用方法によってインデックスファンドとアクティブファンドに分けられます。インデックスファンドは日経平均株価のような、市場全体の平均的な値動きに連動することを目指す商品です。アクティブファンドは市場の平均を上回る成果を目指して専門家が銘柄を選びます。
投資信託は投資する地域によっても以下のように分類されます。
- 国内株式型:日本の会社の株
- 先進国株式型:経済が発展した国(アメリカやヨーロッパなど)の株
- 新興国株式型:経済成長が期待される国の株
- 全世界株式型:世界中の会社の株
株価は経済の状況によって大きく変動するため、購入時よりも価値が下がるリスクに注意してください。
債券投資信託

債券投資信託は国内外の国や会社が発行する「債券」を中心に運用される投資信託で、安定した収益を求める方に適しています。債券はあらかじめ決められた利息を定期的に生み出す性質を持ち、株式のように価格が大きく変動しにくい点が特徴です。ただし、債券投資信託には以下のリスクがあります。
- 金利変動リスク
- 信用リスク
世の中の金利が上がると、すでに発行されている債券の価格が下落する可能性があります。投資している国や会社の経営状態の悪化も、債券の価値が下がる要因の一つです。
バランス型投資信託
バランス型投資信託は1つの商品で株式や債券など、さまざまな種類の資産にまとめて投資できる金融商品です。バランス型投資信託は自動で分散投資してくれるため、自分で資産の組み合わせを考える手間を省けます。市場の状況に合わせて資産の割合を自動で調整してくれるバランス型投資信託も存在します。
バランス型投資信託は大きな利益を積極的に狙うよりも、運用の手間をかけずにリスク分散を実現したい方に最適です。資産配分もファンドマネージャーが調整してくれるため、運用の知識がなくても安心して取り組めます。ただし、バランス型投資信託は手数料が高い場合があります。
MMF(マネーマーケットファンド)
MMF(マネーマーケットファンド)は安全性を重視しながら、預金より少しでもお金を増やしたい方におすすめの投資信託です。主に国債や信用力の高い企業の短期債券などに投資するMMFは、元本の変動が比較的少ない特徴があります。
MMFは株式投資信託と比べると大きな利益は期待できませんが、銀行の預金よりは高い利回りが見込める点が魅力です。次に投資する商品が決まるまで、一時的な待機資金の置き場所としてMMFがよく活用されます。必要なときにすぐ現金に換えやすく、手数料がかからない場合が多い点もMMFのメリットです。
投資信託のメリット
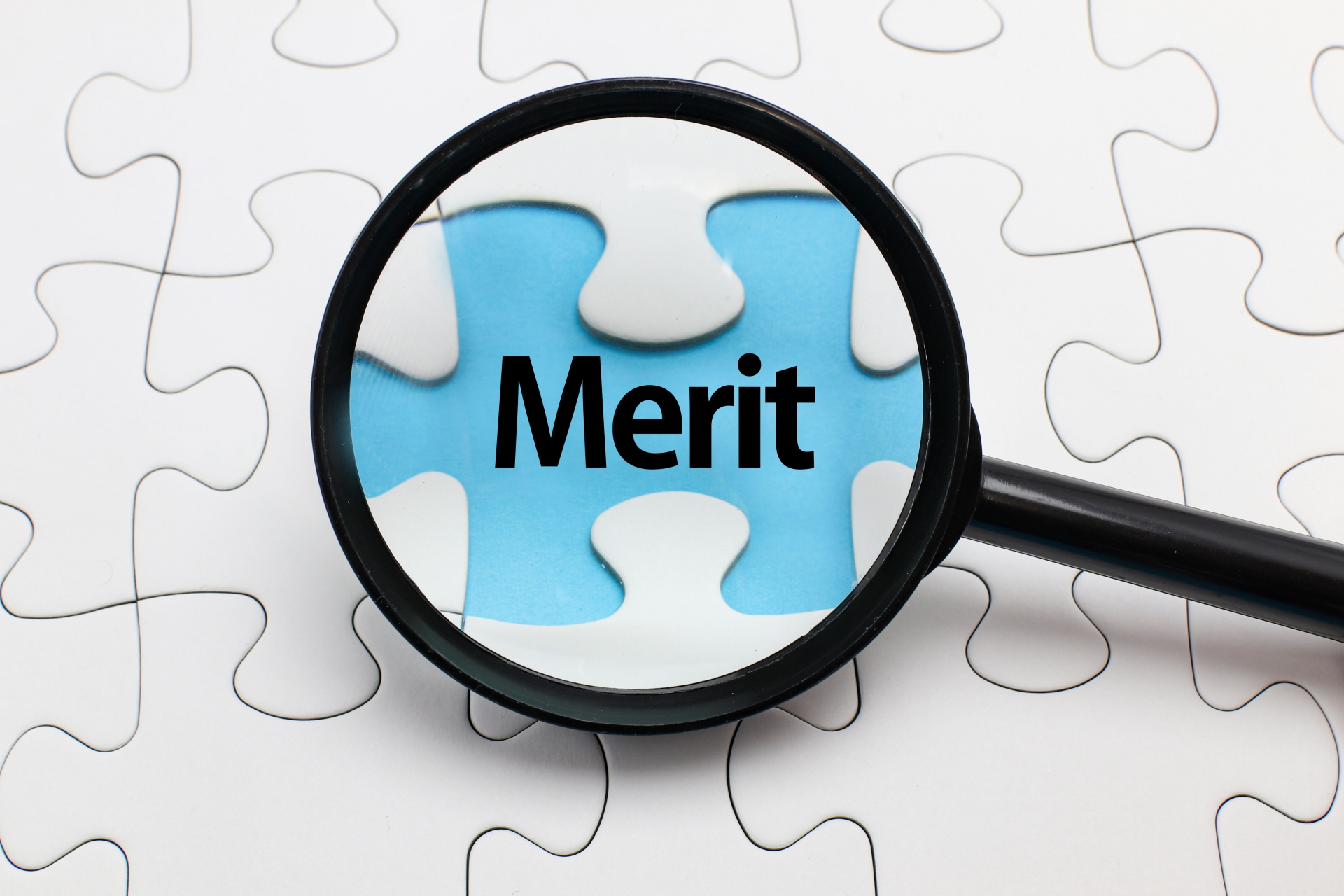
投資信託には以下のメリットがあります。
- プロに運用を任せられる
- 少額から投資できる
- 分散投資でリスクを低減できる
プロに運用を任せられる
投資信託ではファンドマネージャーが経済情勢や企業の動向を分析し、最適な投資先を選んで運用してくれます。自分で投資先を選ぶには会社の成長性を分析したり経済ニュースを追いかけたりする必要があり、多くの時間と手間がかかります。投資信託なら個人では難しい情報収集や分析もプロにゆだねることが可能です。
プロの力を借りて着実に資産形成を進められる点が投資信託の大きなメリットです。
» 絶対知っておくべき!株のキホンと買い方を伝授!
少額から投資できる

投資信託はまとまった資金がなくても少額から始められる金融商品です。投資信託の多くは月々1,000円といったお小遣い程度の金額から手軽に購入できます。小さな金額でも積み立てを続ければ、将来の大きな資産形成につながります。
積立型の投資信託は定期的に一定金額ずつ購入する「ドルコスト平均法」を実践することで、リスクを抑えた運用が可能です。少額から始められる投資信託は生活に負担をかけずに資産運用を始めたい方に向いています。
分散投資でリスクを低減できる
投資信託は1つの商品を買うだけで複数の資産に分けて投資するため、価格変動の影響を和らげる効果が期待できます。1つの企業の株価が下がっても他の企業の値動きが安定していれば、全体としての損失を最小限に抑えることが可能です。
個人で多くの銘柄に分散投資するには多くの資金と管理の手間がかかります。投資信託ではファンドマネージャーが異なる種類の資産を組み合わせて運用してくれるため、手軽に分散投資が実現できます。
投資信託のデメリット

投資信託はメリットがある一方で、以下のデメリットに注意が必要です。
- 元本保証がない
- 手数料がかかる
- 市場変動リスクがある
元本保証がない
投資信託は銀行の預貯金とは異なり、市場の値動きによって元本割れするリスクがあります。投資信託では株式や債券、不動産などの価格変動を伴う資産に投資するため、運用状況によっては損失が出るからです。元本割れが起こる要因には以下が挙げられます。
- 経済の不調
- 金利の変動
- 企業の業績悪化
投資信託を購入する際は資産が減るリスクもあると理解しておきましょう。分散投資や長期運用を意識すると、元本割れのリスクを軽減できます。
手数料がかかる

投資信託は専門家に資金の運用を任せる代わりに、手数料を支払う必要があります。投資信託の運用で発生する手数料の種類は、以下のとおりです。
- 購入時手数料
- 信託報酬(運用管理費用)
- 信託財産留保額
購入時手数料は投資信託を買うときに支払う費用です。投資信託には購入時手数料が無料の「ノーロード」と呼ばれる商品もあります。信託報酬(運用管理費用)は投資信託を持っている間、毎日少しずつ引かれ続ける費用です。信託財産留保額は投資信託を売るときに発生します。
基本的な手数料の他にも監査費用など、表面的には見えにくい「隠れコスト」も存在します。投資信託の手数料は長期的に見るとリターンに大きな影響を与えるため、事前にしっかり確認しましょう。
市場変動リスクがある
投資信託の市場変動リスクとは投資先の株式や債券などの価格が、経済情勢や金融市場の動きによって変動するリスクのことです。投資信託が組み入れている株式や債券の価格は国内外の経済や政治の状況によって常に変動します。市場の動きによって投資信託自体の価値である基準価額も日々上下する点に注意しましょう。
購入時よりも投資信託の基準価額が下がった場合、売却時に元本割れする可能性があります。
投資信託のリスクとリターン

投資信託では期待リターンが大きいほど価格変動リスクも高い傾向があります。投資信託で考慮すべきリスクと期待できるリターンについて解説します。
投資信託のリスク
投資信託は投資先の国や経済の状況によって影響を受ける商品であることから、以下のようなリスクに注意が必要です。
- 価格変動リスク
- 投資先の株式や債券などの値段が動くことで、投資信託の価値も上下するリスク
- 為替変動リスク
- 外国の資産に投資している場合、為替レートの変動によって円換算時の価値が変わるリスク
- 金利変動リスク
- 世の中の金利が動くと債券の価格が変動し、投資信託の価値に影響を与えるリスク
- 信用リスク
- 投資した会社や国の経営状態が悪化し、約束通りにお金が支払われなくなるリスク
- 流動性リスク
- 売りたいと思ったときに希望する価格ですぐに売れない可能性があるリスク
- カントリーリスク
- 投資先の国の政治や経済が不安定になることで資産の価値が下がるリスク
さまざまなリスクを理解しておくと、自分に合った投資信託を選びやすくなります。
リターンの考え方
投資信託で得られる利益は「トータルリターン」で考えましょう。トータルリターンとは値上がり益(キャピタルゲイン)と分配金(インカムゲイン)を合計した本当の利益を指します。たとえ分配金を多く受け取っていても投資信託の価値が下がっていれば、全体では損をしている可能性があるからです。
リターンは必ずしも毎年一定ではなく、市場環境や運用状況によって変動します。過去の実績が良くても将来のリターンを保証するものではない点に注意してください。目先の分配金の額だけに注目するのではなく、値上がり益も含めたトータルリターンで投資の成績を判断しましょう。
投資信託の選び方

投資信託を選ぶ際に重要な以下のポイントについて解説します。
- 投資目的に合ったファンドを選ぶ
- ファンドの運用実績を比較する
- ファンドのコストを比較する
投資目的に合ったファンドを選ぶ
投資信託を選ぶ際に目的に合わない商品を選んでしまうと、期待する成果が得られません。「いつまでに」「何のために」「いくら必要か」によって、選ぶべきファンドの種類や取るべきリスクの大きさが変わります。
長期的な資産形成(老後資金など)には全世界株式やS&P500といった株式中心のファンドが最適です。中期的な目標(5〜10年後の住宅頭金など)であれば、株式と債券を組み合わせたバランス型ファンドが適しています。短期的な資金(数年以内の車購入など)では値動きが小さい国内債券ファンドやMMFが有力です。
自分の投資目的や期間、リスク許容度を明確にするとブレのないファンド選びが可能です。投資信託は種類が豊富にあるからこそ、目的に応じて自分に合った商品を見極める必要があります。
ファンドの運用実績を比較する

投資信託を選ぶ際はファンドの運用成績を確認すれば、安定性と成長性を客観的に把握できます。ファンドの運用成績を見るときは以下の点に注目しましょう。
- トータルリターン
- シャープレシオ
- 純資産総額の推移
- 期間別の成績
- 下落時の動き
- 月次レポート
シャープレシオとは取ったリスクに対して、どれだけ効率良くリターンを得られたかを示す指標です。同じカテゴリーの投資信託でも3年・5年といった長期のリターンに差がある場合があります。短期的な成績だけでなく情報を総合的にチェックすることが、信頼できるファンド選びのポイントです。
ファンドのコストを比較する
投資信託は同じ運用成果でもコストの違いによって、最終的な利益に大きな差が生まれます。コストを低く抑えれば、手元に残る利益を大きくすることが可能です。
信託報酬は保有期間中ずっと発生し、長期運用ではリターンに与える影響が大きくなります。まずは手数料が無料の「ノーロードファンド」の商品から探しましょう。同じ指数への連動を目指すファンドを比較する際は、信託報酬が低いものを選ぶことが基本です。
信託報酬だけでなく実際に運用でかかった費用を含めた「実質コスト」の比較も忘れてはいけません。実質コストには売買委託手数料や監査費用などが含まれます。年に一度発行される「運用報告書」で実質コストを確認できるため、過去数年分をチェックしましょう。
投資信託で気を付けるべきこと

投資信託で気をつけるべきポイントは以下のとおりです。
- リスク管理を徹底する
- 市場の分析と情報収集を行う
リスク管理を徹底する
投資の世界ではどんなに優れたファンドでも、予想外の出来事で価格が大きく下がる可能性があります。万が一のときに慌てて大きな失敗をしないように、以下のようなルールを決めておきましょう。
- 許容損失額の設定
- 損切りルールの設定
- 定期的なリバランス
リスクをゼロにはできませんが、分散投資や運用方針の見直しを通じて損失を最小限に抑えることは可能です。
市場の分析と情報収集を行う
常に変化する経済や金融情勢を把握すると、より的確な投資判断ができます。金利の動きや為替相場、世界経済のニュースなどはファンドの運用成績に大きく影響する要素です。投資信託はプロが運用するものですが、投資家も基礎的な情報に目を向ける必要があります。
情報収集には証券会社のレポートや金融メディアのニュース、投資信託の月次レポートなどを活用しましょう。さまざまな情報を定期的に確認する中で、市場の動きを理解する力も身に付きます。
» 【初心者向け】株式市場の仕組みを解説
投資信託の仕組みを理解して自分に合った資産運用を始めよう

投資信託は誰でも始めやすく、長期的に大きな資産形成を目指せる金融商品です。プロに運用を任せられ、少額から投資を始められる点が大きなメリットです。ただし、元本保証がないことや市場の変動リスクがある点に注意しましょう。
自分に合った投資信託を選ぶには投資目的を明確にし、ファンドの運用実績やコストを比較することが不可欠です。自分の目的やライフスタイルに合った投資信託を見つけ、無理のない範囲で資産形成に取り組みましょう。