
証券口座を開設して投資を始めたばかりで、購入する銘柄に迷っている人は多くいます。株式投資において銘柄選定は極めて重要です。この記事では、株式投資の基礎知識や得られる利益の種類、株の購入方法について解説します。記事を読めば、投資スタイルに合った銘柄の選び方や、リスクを抑えた株の買い方がわかります。
株式投資で成功するには、自分の投資目的に合った戦略的な銘柄選びが重要です。リスク分散のために複数の投資アプローチを組み合わせれば、安定した収益を目指せます。
株式投資の基礎知識
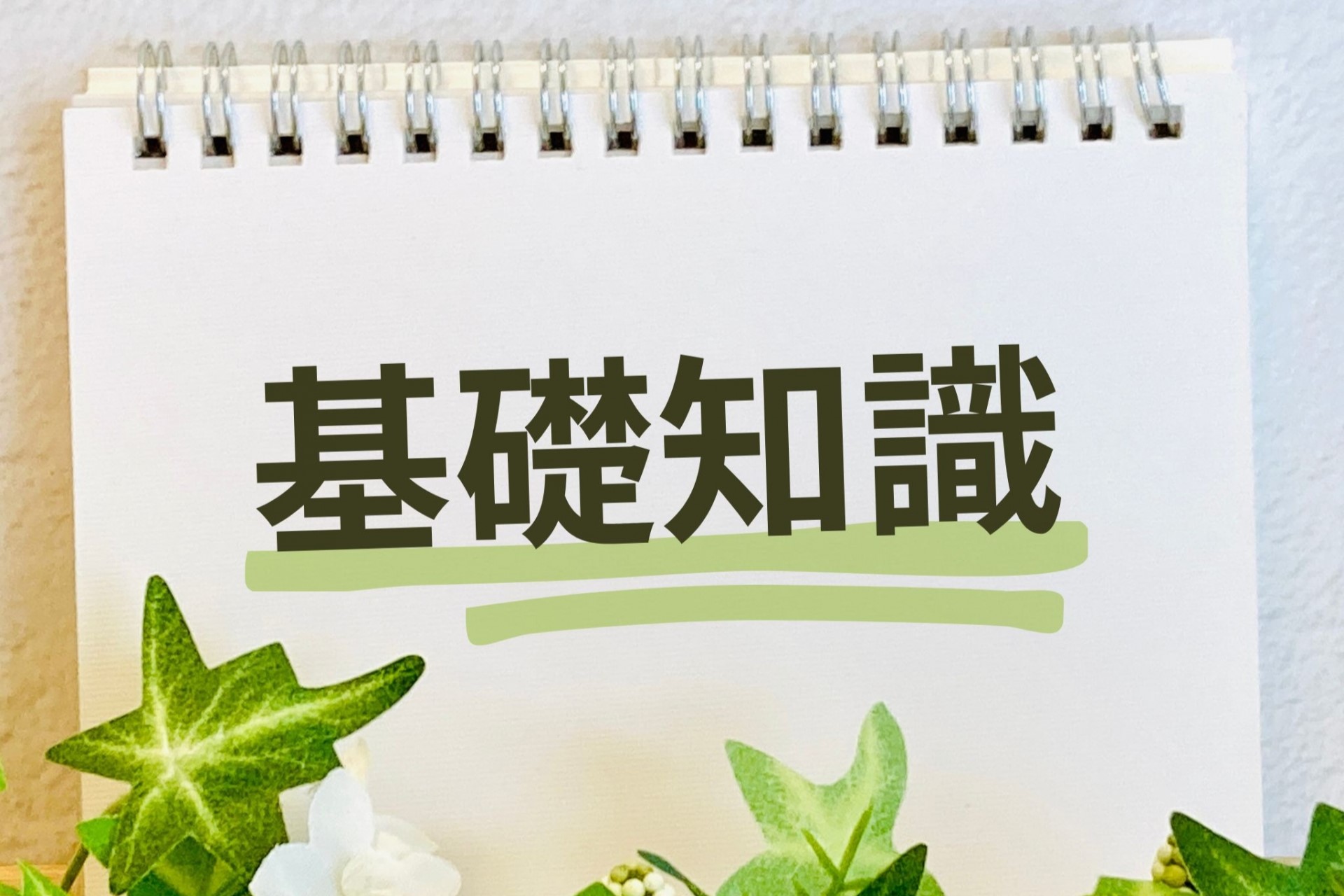
株式投資の基礎知識について、以下のポイントを解説します。
- 株式投資の仕組み
- 個人投資家が株式投資を行う意義
株式投資の仕組み
株式投資とは、企業の所有権の一部を購入して株主になることです。企業は事業拡大のために株式を発行し、投資家から資金を集めます。企業の利益が増えれば、株主に還元される仕組みです。株価は市場での需要と供給によって決まります。多くの人が買いたいと思えば株価は上がり、売りたい人が増えれば下がります。
株価に影響する主な要因は、以下のとおりです。
- 企業の業績や収益
- 将来の成長見通し
- 業界全体の動向
- 経済情勢や政治状況
株式の売買は、東京証券取引所などの証券取引所を通じて行われます。個人投資家は証券会社に口座を開設し、証券会社を通じて株式を売買します。株式投資は、市場が開いている時間内であればスムーズに売買できる高い流動性を持つ点が特徴です。
» 【初心者向け】株式市場の仕組みを解説
個人投資家が株式投資を行う意義
個人投資家が株式投資を行う意義は、長期的な資産形成を実現できる点にあります。銀行預金の金利が低い現代において、株式投資は資産を増やす有効な手段の一つです。株式投資を通じて経済や企業活動への理解が深まり、金融リテラシーも向上します。
日々の企業ニュースや経済情報をチェックすれば、社会全体の動きを把握する力が身に付きます。現在は税制優遇措置としてNISAやiDeCoなどの制度も用意されているため、効率的な資産形成が可能です。
株式投資で得られる利益の種類

株式投資で得られる利益の種類は、以下のとおりです。
- 配当金(インカムゲイン)
- 売買差益(キャピタルゲイン)
- 株主優待
配当金(インカムゲイン)
配当金は株式投資で得られる利益の一つです。企業が利益の一部を株主に還元する仕組みで、年に1〜4回、株式の保有数に応じて、支払われます。株主として配当を受け取るには、権利確定日に株式を保有している必要があります。株式を権利確定日に保有するには、数日前に購入しておく必要があるため、注意してください。
» 株の配当に関する基礎知識から高配当銘柄の選び方まで解説
株価における配当金の割合を「配当利回り」と言い、年間配当金÷株価×100(%)で求められます。1株1,000円の株式が年間50円の配当を出す場合、配当利回りは5%です。配当利回りが高いほど、投資額に対する配当金の割合が大きいことを意味します。
» 配当利回りとは?計算方法や高配当株の選び方を解説
高配当株は安定した収入源となりますが、以下の点に注意が必要です。
- 業績悪化による減配・無配リスク
- 利益に対する約20%の税金
- 配当性向の問題
企業の業績が悪化すると配当が減る(減配)または無くなる(無配)可能性があります。日本では配当金に約20%の税金(所得税・住民税)が課されます。受け取った配当金を再投資する投資戦略で、複利効果を得る方法も人気です。
» 株の配当金にかかる税金をわかりやすく解説!
増配(配当金の増加)傾向にある企業は財務状況が良好な場合が多いため、銘柄選びの際の参考になります。
売買差益(キャピタルゲイン)
売買差益(キャピタルゲイン)とは、株式を購入した価格よりも高い価格で売却すると得られる利益です。キャピタルゲインは値上がり益とも呼ばれ、株式投資における主要な収益源の一つです。キャピタルゲインを得るには、成長性の高い企業や割安な株価の銘柄を見極める必要があります。
株価のトレンドや出来高、テクニカル指標なども参考にして売買タイミングを判断すれば、大きな利益を得る可能性が高まります。投資スタイルによってリスクと期待リターンは異なるため、自分に合った投資方法を見つけてください。短期売買は大きな利益を狙えますが、リスクも高くなります。
一方、長期投資は比較的リスクを抑えながら、時間をかけて資産を増やしていく方法です。
株主優待
株主優待は、企業が株主に対して提供する独自の特典制度です。企業が株主に対して自社製品やサービスを無料または割引価格で提供する制度で、配当金とは別の株主還元策として人気があります。株主優待制度を設けていない銘柄もあるため、購入前によく確認してください。
株主優待を受けるには、企業が定めた権利確定日に一定数以上の株式を保有している必要があります。多くの企業では100株(単元株)から優待が受けられますが、中には1株でも優待が受けられる銘柄もあります。主な株主優待の内容は、以下のとおりです。
- 自社製品
- 商品券や食事券
- サービス利用の割引券
- 施設の利用権
優待の権利確定日は企業によって異なり、年に1~4回設定されているケースが多い傾向です。長期保有者向けに特典が優遇される場合もあります。優待内容を調べるには、企業の公式IRサイトや優待専門のウェブサイトが参考になります。優待目的だけで株を選ぶのではなく、企業の財務状況や成長性も考慮してください。
株の買い方

証券口座で株を買う方法は、以下のとおりです。
- 購入資金を準備する
- 銘柄を選ぶ
- 注文する
購入資金を準備する
投資を始める前に、購入資金を準備してください。適切な資金計画を立てれば、リスクを抑えながら投資を進められます。証券口座への入金方法には、銀行やネットバンクからの振込、ATMでの入金などがあります。各証券会社によって入金方法や手数料が異なるため、利用している証券口座の条件をよく確認してください。
投資は余裕資金の範囲で行いましょう。初心者のうちは、全資産の5〜10%程度から始めると安全です。外国株投資を検討している場合は、為替手数料も考慮してください。
銘柄を選ぶ

良い銘柄選びは投資の成功に大きく影響します。銘柄選びには明確な基準を持ちましょう。銘柄を選ぶ際は、企業の財務状況を確認してください。損益計算書や貸借対照表、キャッシュフロー計算書などの財務諸表を見ると、企業の収益性や安定性を判断できます。安定した収益を上げている企業を選びましょう。
主な投資指標は、以下のとおりです。
- PER(株価収益率)
- PBR(株価純資産倍率)
- ROE(自己資本利益率)
PERは企業の利益に対する株価の割合、PBRは企業の純資産に対する株価の割合、ROEは投下資本に対する利益率を表します。配当利回りが高く、安定した配当政策を持つ企業は長期投資に向いています。投資先は自身が理解しやすい業界の銘柄を選びましょう。
自分の職業や趣味に関連する業界であれば、業界の動向や将来性について独自の視点で分析できます。銘柄を選ぶ際は、定期的に企業のニュースや業界動向をチェックしてください。情報収集を怠らず、企業の将来性を常に評価すれば、成功への近道となります。
注文する
株の注文方法には大きく分けて「成行注文」と「指値注文」の2種類があります。成行注文は現在の市場価格で、すぐに売買できる方法です。迅速な取引を重視する場合に適していますが、市場の変動が大きいときには、想定外の価格で約定するリスクもあります。一方、指値注文は自分の希望する価格を指定して注文する方法です。
価格を自分でコントロールできる点がメリットですが、指定した価格に達しない場合は取引が成立しません。実際に注文する際は、以下の点に注意して手続きを進めてください。
- 購入する株数
- 注文方法
- 注文の有効期限
- 取引時間
購入する株数は、通常100株単位の単元株数で取引します。注文方法は成行または指値を選択し、注文の有効期限は当日限りか週末までなどの指定可能です。取引時間は通常9~15時半です。注文はスマートフォンアプリやパソコンから簡単に行えます。
画面の指示に従って必要事項を入力し、最終確認をして、注文を確定させましょう。取引前に手数料や税金についても確認しておくと安心です。
» 株式投資でかかる税金をわかりやすく解説!
初心者におすすめの株の買い方

初心者におすすめの株の買い方は、以下のとおりです。
- 少額投資から始める
- 損切りラインを設定する
- 分散投資する
» 自分に合った戦略を見つける!株式投資の始め方と注意すべきリスク
少額投資から始める
少額投資から始めるのは、投資初心者にとって賢明な選択です。少額であれば万が一の損失時のリスクを抑えられるだけでなく、実践を通じて投資の仕組みを学べます。最近は100株未満から購入できる「単元未満株」の制度があり、主要ネット証券では数百円から株式投資が可能です。
投資信託も100円程度から購入できます。初心者には、以下の方法がおすすめです。
- ドル・コスト平均法の活用
- 月5,000〜10,000円の投資
- 収入の5%程度の投資
毎月一定額を積み立てる「ドル・コスト平均法」を活用すれば、無理のない金額から始められます。初心者に適している投資先は、投資信託やETFです。投資信託やETFは1つを購入するだけで多くの銘柄に分散投資できるため、リスクを抑えながら市場全体の成長を取り込めます。
少額投資の最大のメリットは、心理的な負担が小さく、失敗しても経験が貴重な学びになる点です。投資は長期的な視点で考え、少しずつ経験を積み重ねましょう。
損切りラインを設定する

損切りラインの設定は、投資リスクを管理するうえで重要です。投資金額の10〜20%を損切りラインとして決めておくと、大きな損失を防げます。10万円分の株を購入した場合、9万円(10%の下落)または8万円(20%の下落)を損切りラインとして設定します。
株価が損切りラインを下回ったら、感情を挟まずに売却しましょう。損切りは「失敗」ではなく「リスク管理」の一環です。プロの投資家でも損切りは日常的に行っています。損切り後は冷静に原因を分析し、次の投資に活かしてください。市場環境や投資戦略に応じて、損切りラインの定期的な見直しが必要です。
損切りラインを設定するときは、利益確定ラインも同時に設定しておくと、投資のバランスが取れます。初心者は、厳格な損切りルールを守れば大きな損失を防げるため、必ず損切りラインを設定してから投資を始めてください。
分散投資する
分散投資は、リスクを減らしながら安定したリターンを目指す投資方法です。一つの銘柄だけに投資すると、大きく値下がりした場合に大きな損失を被ります。しかし、投資先を複数にわけておけば、一つの銘柄が値下がりしても全体では大きな損失になりにくいメリットがあります。分散投資の手法は、以下のとおりです。
- 業種・セクター分散
- 地域分散
- 時間分散
業種・セクター分散では、ITや金融、ヘルスケアなど異なる業種に分散投資します。地域分散は、国内株だけでなく、米国株やアジア株など国際的に分散する方法です。時間分散は一度に全額投資せず、定期的に分割して投資する方法を指します。分散投資の適切な銘柄数は、一般的に10〜30銘柄程度とされています。
銘柄ごとの値動きの違いによって全体のリスクを抑える効果が見込めるためです。ただし、あまりに多くの銘柄に投資すると管理が難しくなり、リターンも薄まる可能性があるので注意してください。銘柄数を増やすだけでは、分散効果が得られません。
自動車関連の株ばかり10銘柄持っていても、自動車業界全体が不振になれば同時に値下がりします。リスクを減らすためにも、相関関係の低い銘柄を選びましょう。
まとめ

株式投資は主に配当金や売買差益、株主優待の3つの利益が得られます。投資銘柄を選ぶ際は、配当利回りや株主優待の内容だけでなく、企業の業績や成長性を考慮してください。初心者は少額投資から始めると、値下がり時の損失を抑えられるだけでなく、実践を通して投資経験を積めます。
投資は余裕資金で始め、分散投資を心がけてください。実際に株を購入する前に、損切ラインを明確に定めて、必ず守りましょう。投資を続けるうえで、定期的なポートフォリオの見直しが大切です。保有銘柄の決算情報を確認し、経済状況の変化に注意を払えば、投資判断の精度を高められます。
株式投資の基本を押さえて、リスクを抑えつつ投資を継続してください。投資は株式市場から退場しないことが重要です。焦らず自分のペースで投資の知識と経験を積み重ねていきましょう。