【TOB事例】DDグループが非公開化へ! MBOの狙いと戦略の考察とそこから予想されるMBO候補銘柄
2025.07.16投稿
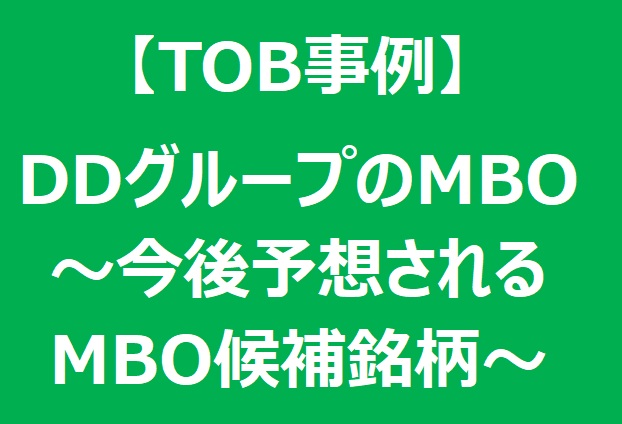
外食産業を取り巻く厳しい経営環境の中、DDグループがポラリス・キャピタル・グループ(以下、ポラリス)と組んでMBO(マネジメント・バイアウト)を実施し、株式の非公開化を目指すことを発表しました。
この大胆な戦略の背景には何があるのでしょうか? 本記事では、今回のTOB(株式公開買付け)の目的、買付価格の妥当性、そして非公開化後の経営戦略について詳しく解説します。
なぜ今、非公開化なのか? MBOの目的と背景
今回のTOBは、DDグループの経営陣と投資ファンドのポラリスがタッグを組んで行うMBOです。ポラリスが設立した特別目的会社「PCGVI-1社」がDDグループの全株式取得を目指し、上場廃止(非公開化)を進めます。
MBOの構造と目的
MBOとは、企業の経営陣が参加して自社の株式を買い取り、非公開化する手法です。これにより、買収後も現在の経営陣が引き続きコミットし、長期的な視点で企業価値の向上を目指すことができます。
DDグループの場合、創業社長である松村氏がMBO後も経営に携わることで、経営の継続性と安定性を保ちつつ、抜本的な改革を進める狙いがあります。
非公開化を選んだ理由
DDグループを取り巻く経営環境は、人件費や食材費、光熱費の高騰、さらには少子高齢化による市場の縮小など、非常に厳しい状況にあります。このような状況を打開するためには、不採算店舗の閉鎖、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進、海外展開への再挑戦といった大規模な改革が急務でした。
しかし、上場企業である限り、これらの施策は短期的な業績や株価に影響を与えやすく、迅速な意思決定が難しいという課題があります。
そこで、株式を非公開化することで、短期的なプレッシャーから解放され、より機動的かつ大胆な経営体制を構築し、中長期的な視点での改革をスピーディーに実行することを選択したのです。
DDグループとポラリス、それぞれの狙い
DDグループ側の狙い
DDグループは、ポラリスとのMBOを通じて経営基盤を強化し、中長期的な企業価値向上を目指します。ポラリスが持つ豊富なノウハウやネットワークを活用することで、マーケティング強化や業務効率化といった課題を迅速に解決し、企業価値を高められると判断しました。今回のMBOは、DDグループが厳しい環境を乗り越え、持続的な成長を実現するための重要な一歩となります。
公開買付者(ポラリス)側の狙い
ポラリスは、DDグループの将来的な成長余地に着目しています。自社の投資先である「宣伝会議」との連携によるブランド知名度向上支援や、多店舗展開企業への投資経験から培ったマーケティング効率化・ブランディング手法の提供など、DDグループの事業とシナジーを生み出すことで、企業価値を最大化し、投資リターンを獲得することを狙っています。
買付価格は妥当なのか? その評価手法を解説
今回のTOBにおける普通株式1株あたりの買付価格は1,700円です。この価格は、株主にとって妥当な水準なのでしょうか?
市場株価との比較(プレミアム水準)
提示された買付価格1,700円は、直近の市場株価に対して高いプレミアム(上乗せ)を含んでいます。
- TOB公表前営業日(2025年7月7日)の終値1,448円に対し、約17.4%のプレミアム
- 過去1ヶ月平均1,430円に対し、約18.9%のプレミアム
- 過去3ヶ月平均1,343円に対し、約26.6%のプレミアム
- 過去6ヶ月平均1,321円に対し、約28.7%のプレミアム
このように、市場価格と比較して十分な上積みが提供されており、株主にとって魅力的な価格設定と言えるでしょう。
株式価値評価レンジとの比較
今回のTOB価格1,700円は、第三者算定機関であるPwCによる株式価値評価レンジと照らしても適切と判断されています。
PwCは、市場株価基準法やディスカウント・キャッシュフロー法(DCF法)を用いてDDグループの株式価値を評価しました。その結果、1,700円という価格は、市場株価基準法による評価レンジ上限(約1,469円)を上回り、DCF法による評価レンジ内(約1,687円〜2,370円)に位置すると報告されています。
つまり、市場価格ベースの評価よりも高く、事業価値に基づく評価レンジの下限付近にある水準であり、少数株主にとって妥当な価格水準であることが示されています。
第三者評価と交渉経緯
DDグループが設置した特別委員会は、PwCの算定結果や助言を基に、TOB価格の公正性を慎重に審査しました。その過程で買付者側と複数回の交渉が行われ、当初の提案価格からの引き上げを要請。その結果、1株1,700円がポラリスおよび松村氏にとって提示可能な上限価格であるとの最終提案が示されました。
特別委員会も「独立当事者間の交渉と同等のプロセスを経て決定された価格」であり妥当と判断し、取締役会もこの価格を支持しています。これらの経緯から、買付価格1,700円は、市場水準と評価算定の両面から適正であると考えられます。
非公開化後の未来:新しい経営戦略とガバナンス
非公開化後、DDグループはどのような経営体制となり、どのような成長戦略を描くのでしょうか。
ポラリスによる強力な支援
非公開化後は、ポラリスが筆頭株主(スポンサー)となり、その経営資源を活用した支援がDDグループに提供されます。具体的には、ポラリスの既存投資先である「宣伝会議」との提携によるウェブ媒体での特集記事配信などを通じて、DDグループや運営ブランドの認知度向上を図る施策が検討されています。また、ポラリスが多店舗展開ビジネスで培ってきたマーケティング効率化やブランディング手法の導入支援も行われる予定です。
ポラリスはこれらのノウハウやネットワークを提供することで、DDグループ全体のシナジー効果を最大化し、競争力強化と業績向上に貢献する方針です。
松村社長の継続関与と新体制
MBO後も、創業社長である松村厚久氏は引き続き経営に携わります。
TOB成立後も取締役として経営を担い、新会社に一定の持分(約5%)を再出資することで、引き続きオーナー経営者としてコミットする予定です。これにより、非公開化後も現経営トップのビジョンやノウハウが維持され、ポラリスとの協働による新しい体制で事業が運営されます。
また、取締役会にはスポンサーであるポラリスからも役員が派遣される見込みで、現経営陣と投資家が一体となった強固なガバナンス体制が構築されるでしょう。
非公開化後の成長戦略
上場廃止後は、短期的な株主の目を気にすることなく、中長期的な視点で大胆な経営改革と成長戦略が実行される計画です。
具体的には、これまで課題であった不採算店舗の整理や業態ポートフォリオの見直しを加速します。さらに、デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進して業務効率化やマーケティング強化を図り、新たな海外展開にも再挑戦することを検討しています。これらの戦略は、非公開化のメリットを最大限に活かし、ポラリスの支援のもとで企業価値の向上と持続的な成長を目指すものです。
財務的観点:TOB資金の調達方法と松村氏の再出資スキーム
今回のTOBの資金はどのように調達されるのでしょうか。また、松村社長の再出資スキームについても見ていきましょう。
買収資金の出資・借入構造
TOBの資金は、エクイティ(自己資金)とデット(借入金)の組み合わせで調達されます。
- エクイティ部分: ポラリスが運営する投資ファンド「ポラリス・ファンドVI」を中心に、関連する共同投資ファンド(Crown、Jewel、Tiara)が出資します。総額で約200億円規模の自己資金が投入される計画です。
- デット部分: 三井住友銀行(SMBC)を主幹とするシンジケートローンが組成され、SMBCから約206.5億円、トラスト・キャピタル・メザニン投資事業組合から約30億円、NECキャピタルソリューションから約20億円の借入れが予定されており、合計で約256億円の買収ローンが組まれます。
これらエクイティ出資金と借入金を合わせ、TOB決済資金(普通株全株の買付代金約308億円)に充当されます。この借入金には、買収対象株式やDDグループの資産を担保とするLBOファイナンスのスキームが用いられ、TOB後にDDグループは公開買付者の連帯保証人となる予定です。
松村氏の再出資スキーム
本件MBOでは、経営トップである松村氏も一定の資本参加を維持します。
松村氏個人は保有するDDグループ株式のうち、譲渡制限付株式を除く約499.39万株(発行済株式の27.59%)をTOBに応募して売却します。一方、松村氏が全株を保有する資産管理会社「株式会社松村屋」(持株比率8.21%)についてはTOBには応募しない契約を結んでいます。
TOB完了後、松村屋保有株はスクイーズアウト手続(強制的に少数株主から株式を買い取る手続き)を経て、公開買付者(SPV)と松村屋のみが株主となった段階で、同社に対し現金で譲渡される予定です。この譲渡価額はTOB価格と同等の1株1,700円で評価され、松村屋の保有株式数に1,700円を乗じた金額から債務控除等を行った額となります。松村屋株式の譲渡は上場廃止後の2025年11月下旬が予定されており、譲渡対価は約25.3億円になる見込みです。
松村氏は自身と松村屋で得たこれらの株式売却代金の一部を用いて、公開買付者である新会社へ再出資を行います。具体的には、TOB後に公開買付者が増資を行い、松村氏が1株あたり1,700円(TOB価格と同一評価)で新株を引き受ける形で出資する契約となっており、これにより松村氏はMBO後の新株主構成で約5%の株式を継続して保有する予定です。
この再出資スキームは、松村氏が引き続き経営者として会社価値向上にコミットするインセンティブを保ちつつ、TOB価格の均一性(少数株主との平等な条件)も確保されるよう設計されています。
今回のMBOは、DDグループが厳しい経営環境を乗り越え、将来の成長を実現するための重要な戦略転換と言えるでしょう。非公開化によって、より柔軟で迅速な経営判断が可能となり、ポラリスの強力な支援のもと、抜本的な改革が進められることが期待されます。DDグループの今後の動向に注目が集まります。
DDグループMBOに続くTOB候補銘柄
DDグループと同様に外食・アミューズメント・ホテル・不動産といった事業を営み、かつ株価がPERやPBRで割安に放置され、さらにオーナー経営色が強い企業については、経営陣が主導する形で株式を買い取り、上場廃止(非公開化)を選ぶ可能性があります。
以下では、将来的にMBOの可能性があるとされる4つの注目銘柄を厳選し、それぞれの企業の強み、課題、そしてなぜMBOの候補となりうるのかを解説します。
藤商事 (6257) – パチンコ機メーカーの構造転換と再投資
企業概要・ビジネスモデル
遊技機(パチンコ・パチスロ機)メーカー大手で、人気アニメコンテンツとのタイアップ機種に強みを持っています。近年は「スマートパチスロ/パチンコ」など、新規制対応の次世代機開発に注力し、業界の変化に対応したビジネスモデルへの転換を図っています。
割安性と業績
業界低迷の影響で業績は伸び悩むものの、財務指標上は著しい割安感があります。予想PERは10倍程度、PBRは0.5倍前後と、純資産の半値以下で評価されており、配当利回りも約5%と高水準です。
株主構成とオーナー色
創業一族である松元邦夫会長と松元正夫副会長がそれぞれ21%超を保有し、合わせて約42%を占める筆頭株主です。創業家が実質的な経営権を握るオーナー企業であり、長期的な視点での事業展開が可能です。
成長課題とMBO候補としての理由
パチンコ業界は遊技人口の減少や規制強化で市場縮小傾向にあり、販売台数の確保や新機軸へのシフト、海外市場開拓が課題です。
MBO候補としての注目理由は、株価の著しい割安さに加え、創業家が約4割超の株式を握っているため、経営陣主導のTOBが比較的スムーズに成立する見込みがある点です。非公開化することで、規制対応のための長期開発投資や、大胆な事業再編(不採算部門の整理、新規事業への挑戦)を市場の短期的な圧力から離れて進めやすくなります。
PBR0.6倍未満という市場からの低評価は、創業家にとって企業を安価に買い戻す好機と捉えられる可能性も秘めています。
フージャースホールディングス (3284) – 割安不動産デベロッパーの真価発揮
企業概要・ビジネスモデル
首都圏を中心に「DUO(デュオ)」ブランドのマンション分譲を手掛ける不動産デベロッパーです。ファミリー向け中規模マンションに強みを持ち、近年は地方都市や再開発案件にも進出しています。
割安性と業績
好業績にも関わらず市場評価は低く、予想PERは7倍台、PBRも1倍程度に過ぎません。配当利回りも5%を超え、財務指標上は著しく割安な水準です。これは不動産市況への過度な悲観や、中小型株ゆえの流動性リスクが織り込まれている可能性がありますが、利益成長実績を踏まえると修正余地は大きいと考えられます。
株主構成とオーナー色
創業者の廣岡哲也氏(現会長)が筆頭株主として経営を主導しています。過去にはアクティビスト(旧村上ファンド系)が筆頭株主となり経営関与を試みましたが、同社は自己株TOBを実施して村上側の持株を買い取り、創業者側が株式支配力を強めるなど、経営陣(創業者)が主導権を握り続けるオーナー企業としての側面が色濃いです。
成長課題とMBO候補としての理由
マンション市場は金利上昇や資材高騰の逆風があり、用地取得競争も激化しています。しかし、財務基盤は比較的健全で、含み資産や在庫の評価見直し余地もあります。
MBO候補としての注目理由は、創業者が経営権を固めていることに加え、株価が著しく割安な現状です。上場維持コストを払い続けるよりも、非公開化して内部留保や資産を成長投資に振り向けたいという判断があり得ます。以前にアクティビストに狙われた経験からも、市場に翻弄されない経営を望む経営陣の意向は強いと見られます。MBOにより、長期視点での土地投資や新事業展開を柔軟に遂行できるメリットがあります。
テーオーシー (8841) – 資産豊富な不動産賃貸業の秘めたる価値
企業概要・ビジネスモデル
東京・五反田の「TOCビル」など大型商業ビル賃貸を中核とする不動産会社です。ホテルニューオータニ系列の一社であり、大型不動産の含み資産を抱える、都心開発のパイオニア的存在です。
割安性と業績
同社の株価は資産価値に対して大幅なディスカウント状態です。PBRは0.6倍前後と純資産の半分程度の評価に留まっており、東証スタンダードの中でも際立つ低PBR銘柄です。主力ビル建替え計画の見直しによりPERは一時的に高めですが、豊富な含み資産から見れば依然として割安と評価されています。
株主構成とオーナー色
創業家である大谷(オオタニ)家が経営権を掌握しており、関連企業を通じ約半数近い株式を保有しています(ニューオータニ、大谷興産、オオタニ・ファンドなど)。このようにオーナー企業色が極めて強く、主要な経営判断は創業家の意向に沿って行われます。
成長課題とMBO候補としての理由
主力の五反田TOCビルは老朽化に伴う建替え計画が進められていましたが、一旦見直しとなり不透明感が残ります。しかし、都心一等地の大型物件群を抱える強みがあり、財務基盤も盤石です。
MBO候補としての注目理由は、極めて低い株価評価(PBR約0.6倍)です。創業家にとって、自社ビル群の含み資産価値を市場価格に拘束されずに引き出すには、非公開化が有効な手段となりえます。また、創業家が約50%近い株式を掌握していることからTOB成立のハードルも低いでしょう。
MBOにより、長期視点での大型再開発(TOCビルの再構築計画再始動など)やグループ再編を柔軟に進められるメリットがあります。昨今の東証改革で低PBR銘柄への圧力が増す中、抜本策としてMBOが選択肢に浮上する可能性も十分に考えられます。
オークワ (8217) – 地域密着スーパーの構造改革と再評価
企業概要・ビジネスモデル
和歌山県を地盤とする大手スーパーマーケットチェーンで、近畿・東海エリアに店舗網を展開しています。創業家出身の大桑弘嗣氏が代表取締役社長を務める地域密着経営が特徴です。
割安性と業績
小売業界の競争激化の中で業績は足踏み状態ですが、株価はPBR0.5倍程度と著しく割安に放置されています。PERは利益低迷の影響で一時的に高めですが、これは収益改善の余地があることを示唆しています。
株主構成とオーナー色
創業家の大桑一族が経営を担い、大桑社長個人で7.2%の株式を保有するほか、地元関係者で構成する「オークワ共栄会」が約8%を持つなど、創業家および地元勢力が一定の影響力を保っています。経営の意思決定にはオーナー家の理念が反映されています。
成長課題とMBO候補としての理由
地方スーパーゆえに市場成熟による成長鈍化や、大手との競合に直面しています。出店や店舗改装に投資がかさみ収益率が低下している点や、物流効率化、DX対応といった構造改革の余地が課題です。
MBO候補としての注目理由は、株価の割安放置(PBR0.5倍以下)が経営陣にとって大きな課題である点です。オーナー家が主導しやすい体制であることから、地元金融機関などの協力を得て経営陣による株式非公開化に踏み切るシナリオも考えられます。
非公開化すれば、店舗のスクラップ&ビルドや業態刷新など長期的な構造改革を腰を据えて行えます。地方企業であるため株式市場での資金調達メリットが限定的であることも、上場維持を再考する要因となりえます。