【TOB事例】株式会社トラストに対するTOBから考える流通株式比率不足による親子上場解消TOB候補銘柄4選
2025.05.15投稿

中古車輸出のトラストが親会社VTホールディングスのTOBで非公開化へ。
上場維持基準未達と親子上場の利益相反解消が背景にあります。この記事では、買付価格410円と約4割のプレミアムが示す意味と、同様の条件下で今後注目すべき銘柄を解説していきます。
TOBに至った背景
株式会社トラスト(東証スタンダード・証券コード3347)は、中古車の海外輸出やレンタカー事業、南アフリカでの新車ディーラー運営など、自動車関連の多角的事業を展開する企業です。親会社は自動車ディーラー持株会社のVTホールディングス(東証プライム・7593)で、VTホールディングスはホンダ・日産の販売店や中古車輸出企業(トラスト等)を傘下に持つ企業グループです。トラストは2004年に新興市場へ上場しましたが、その後VTホールディングスが株式の約7割超を保有する親子上場の状態となっていました。
近年、東京証券取引所は市場再編を通じて上場企業に対し流通株式比率などの上場維持基準を厳格化しました。スタンダード市場では「流通株式比率25%以上」の維持基準が定められており、トラストはこの基準を満たせなくなるリスクを抱えていました。実際、親会社による持株比率拡大などでトラストの流通株式比率は一時17%程度まで低下したとの指摘もあり、上場維持基準に不適合となる可能性があったのです。上場企業が一定期間内に基準不適合を解消できない場合、監理銘柄指定を経て上場廃止となる制度もあります。
このような状況の下、トラストでは親会社VTホールディングスとの親子上場の構造的課題も意識されていました。親子上場では、親会社が子会社の経営権を握ったまま子会社も上場しているため、少数株主との間で利益相反(コンフリクト)の懸念が指摘されます。例えば親会社が子会社との取引条件を支配し、子会社の利益を親会社に吸い上げるようなケースが起きれば、子会社の少数株主に不利益となりかねません。こうした問題から、海外では親子上場は稀で、日本でもガバナンス改革の流れで親子上場解消(完全子会社化や資本関係見直し)の動きが活発化しています。
VTホールディングスは自社グループの経営効率向上も図る観点から、トラストを完全子会社化(非上場化)する決断を行いました。その背景には、上記の上場維持基準の問題に加え、上場子会社を抱えることで生じる上場維持コストの削減や、グループ内資源の最適配分を容易にする狙いもありました。トラストが上場を維持するためには基準充足のための対応や開示義務などが必要でしたが、非公開化することでそれらのコストや手間を省き、グループ経営を一本化するメリットが見込まれます。
以上のように、親会社による子会社株式の公開買付け(TOB)に至った背景には、①トラストの流通株式比率が上場維持基準に抵触する恐れ、②親子上場ゆえの少数株主との利益相反リスクの存在、③グループ経営効率化(上場コスト削減・資本戦略の自由度向上)という理由がありました。
TOBの概要
VTホールディングスは2025年5月15日から、トラスト株式を対象としたTOB(株式公開買付け)を実施しました。主要な条件は以下のとおりです。
- 公開買付者(買付け主体):VTホールディングス株式会社
- 対象会社(被買付け):株式会社トラスト
- 買付け価格:1株あたり410円(TOB発表前営業日終値291円に対して約40.9%のプレミアム)
- 公開買付期間:2025年5月15日 ~ 2025年7月11日
- 買付け株数の予定:7,192,500株(上限・下限設定なし)※トラストの発行済株式数に対し全株取得を目指す
- 公開買付代理人:東海東京証券株式会社
- 今後の予定:上場廃止を前提。TOB成立後、VTホールディングスはトラストを完全子会社化する手続きを進める予定
- 買付け目的:上場子会社の少数株主との構造的な利益相反の解消等(親子上場の解消)
上記のように、買付価格410円は市場株価に対して約4割高い水準で設定されました。公開買付け期間中、トラスト株は市場でも概ね買付価格付近まで上昇し、投資家は市場売買でもTOB価格に近い値段で売却できる状態となりました。VTホールディングスは全株取得を目指すTOBであるため応募上限はなく、最終的に少数株主から応募があった株式はすべて買付けられる見込みです。
トラストの取締役会はこのTOBに対し賛同の意見表明を行っています。親会社による子会社TOBでは、対象子会社側の取締役会が少数株主の利益に照らして意見表明を行うのが通例ですが、トラスト経営陣も本TOBによる完全子会社化に同意しました。
少数株主への影響としては、TOB期間中に応募(または市場売却)し株式を手放すことでプレミアム価格での現金化が可能となります。一方、TOBに応じずに残った株主についても、買付け後にVTホールディングスが株式の90%以上を取得できれば株式売渡請求により強制的に買い取られるか、または株式併合により1株未満の端数にされ現金化される見込みです。いずれにせよトラスト株は2025年中に上場廃止となる予定であり、一般株主は株式を市場で取引できなくなります。
TOBの時系列を振り返ると、2023年頃から親子上場解消の機運が高まる中でVTホールディングスも検討を進め、2025年5月14日にTOB実施を公表、5月15日から買付け開始という流れでした。TOB期間終了後、所定の決済手続きを経て応募株主に対価が支払われ、その後速やかに上場廃止の手続きが取られる見込みです。
まとめると、今回のTOBは親会社が子会社を完全子会社化する典型的なケースであり、買付け価格は410円(約41%プレミアム)、全株取得による非公開化、少数株主は市場売却かTOB応募で応じる、という概要になります。
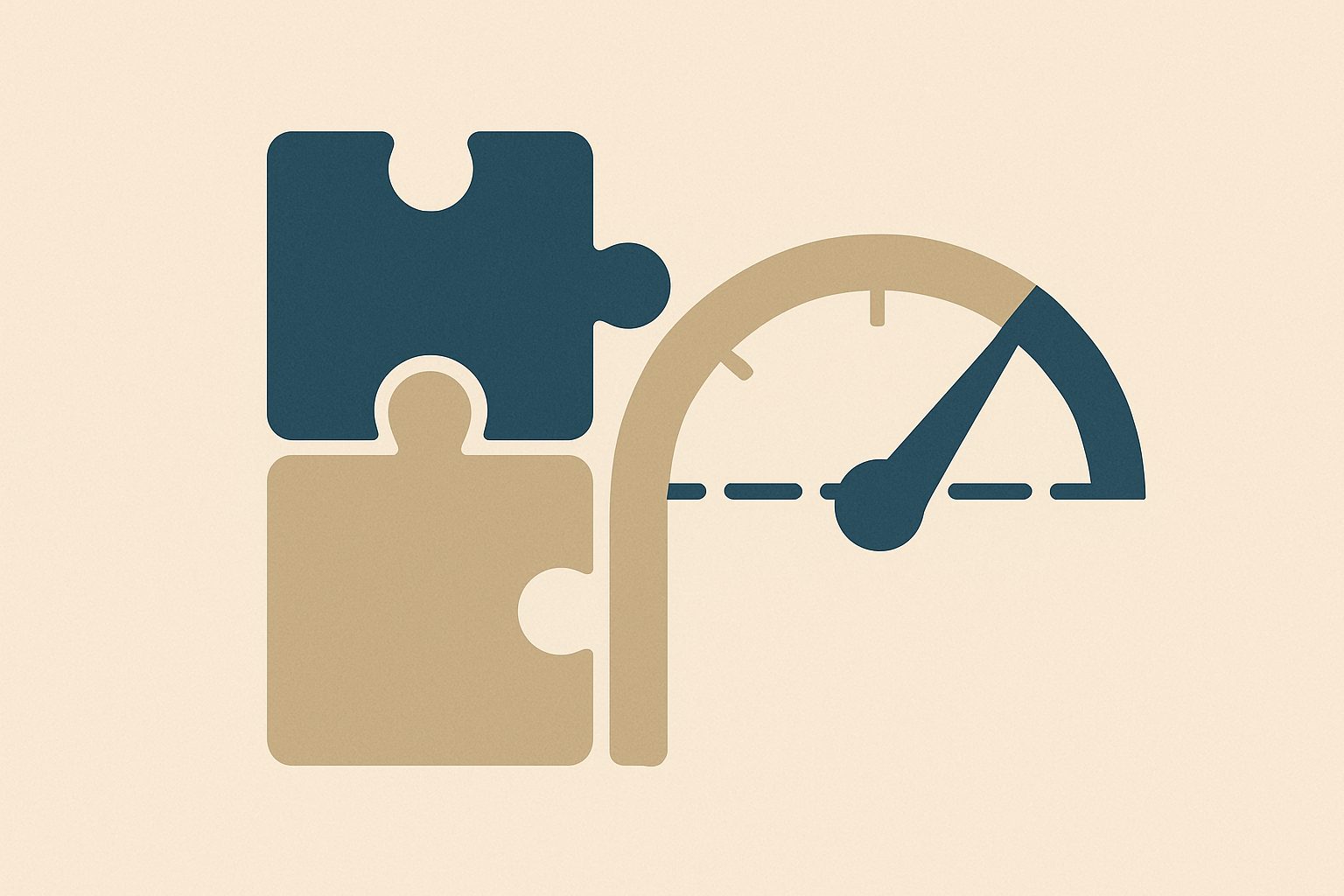
TOB企業に共通する特徴
今回のトラストのように親会社が上場子会社をTOBで買収・非公開化するケースには、いくつか共通した背景・特徴があります。
- 親子上場状態:親会社が子会社株の過半数を保有し経営支配しているケースです。日本市場には多数の親子上場企業が存在してきましたが、親会社と子会社の双方が上場していることで企業グループ内に上場会社が複数存在する状態となります。トラストもVTホールディングスの連結子会社として上場していました。このような企業では、近年親子上場解消への圧力が高まっています。
- 上場維持基準未達のリスク:東証プライム市場では流通株式比率35%以上、スタンダード市場では25%以上などの維持基準があります。親子上場の場合、親会社が大株主として大きな比率を占めるため子会社の流通株式比率が低くなりがちです。例えばトラストは親会社が約72%を保有し流通株比率が25%程度と基準ギリギリでした。また、日本ハウズイングなど他社の例では流通株式比率が14%程度しかなく、このままでは上場廃止になりかねないためMBO(経営陣による株式公開買付け)で株主に売却機会を提供したケースもあります。このように上場維持基準に抵触することが親子上場解消の直接の引き金となる場合があります。
- 少数株主との利益相反リスク:親子上場では前述の通り親会社と少数株主の利害不一致が問題視されます。親会社はグループ全体最適を優先して子会社に働きかけますが、その過程で子会社の少数株主の利益が損なわれる恐れがあります。この構造的なガバナンス上の問題(=構造的な利益相反)は、近年のコーポレートガバナンス・コードでも解消が求められるようになりました。親会社による完全子会社化は、この問題を一挙に解決し得る手段として位置付けられます。
- 親会社側のM&A戦略・意図:親会社が積極的なM&A戦略を持ちグループ再編を進めている場合、子会社のTOBを決断しやすくなります。例えばNTTグループは2020年にNTTドコモをTOBで完全子会社化し、2025年にはNTTデータにもTOBを実施すると発表しました(1株4000円)。またAEON(イオン)グループは2023~2025年にかけて上場子会社の統合を相次ぎ発表しており、2025年2月にはイオンディライトにTOB(1株5400円)を表明し基本合意、イオンモールも株式交換による完全子会社化を協議開始としています。このように、親会社がグループ戦略上子会社を取り込むメリットが大きいと判断した場合、TOBに踏み切る傾向があります。逆に言えば、親会社側に資金力と統合意志があり、市場や当局からの親子上場解消圧力も高まっている状況が重なると、TOB実施の可能性が高まります。
- TOBプレミアムの付与:親子上場解消TOBでは少数株主の同意を得るため、市場価格に対して一定のプレミアム(上乗せ幅)を付けるのが通例です。一般的に30~40%程度のプレミアムが付与されることが多く、今回のトラストのように約40%のプレミアムが付いた例もあります。プレミアム水準はケースによって異なりますが、親会社による子会社TOBの場合は親子関係ゆえ対抗買収者が現れにくいため、プレミアムは適度な水準(低すぎず、高すぎず)に設定される傾向があります。株主にとっては、市場株価では得られない価格で売却できる機会となります。
以上の特徴から、「親会社が過半数保有」「流通株が少ない」「親子上場の利益相反懸念」「親によるグループ戦略の一環」といった条件が重なる企業では、親会社によるTOBによって非上場化が図られるケースが増えています。実際、2024年にはTOB件数が年間100件を超え17年ぶりの高水準となり、その多くは親子上場解消や事業再編を目的としたものでした。この流れは2025年も続いており、親子上場解消の動きは今後さらに加速する可能性が高いと指摘されています。
一般投資家としてどう対応すべきか
親会社によるTOBが発表された場合、少数株主(一般投資家)は適切に対応する必要があります。基本的に選択肢は2つです。
- 市場で売却する – TOB発表後、対象株の株価は公開買付価格近辺まで急騰するのが通常です。市場価格が買付価格にほぼサヤ寄せ(接近)したタイミングで、自分の持ち株を株式市場で売却する方法です。メリットは即座に現金化できる点です。TOB期間の終了や決済を待たず、発表直後の値上がり局面で利益確定できます。ただし市場価格は買付価格よりわずかに低いことが多く、TOB価格との差額(いわゆる「サヤ」)分だけ受取額は減る可能性があります。
- TOBに応募(買付代理人経由で売却)する – 発表された公開買付価格で株式を売却できる確実な方法です。指定された証券会社(公開買付代理人)に口座を用意し、期間中に応募手続きを行います。メリットは公開買付価格そのままの金額で売却できる点です。デメリットとしては、TOB決済日まで資金を受け取れないため現金化が市場売却より遅れること、応募手続きの手間がかかることが挙げられます。また応募後に株価が上振れしても応募を撤回することは原則できません。
一般投資家が注意すべきは、発表されたTOB条件が妥当か検討することです。親子上場TOBの場合、対抗買収者の出現は期待しにくく、提示価格以上で売却できる機会は限られます。そのため提示プレミアム(上乗せ幅)が概ね適正であれば、期間内に売却(市場または応募)するのが無難です。近年の日本のTOBでは平均30~50%程度のプレミアムが付与されるケースが多く、トラストの場合も約41%のプレミアムが付与されました。この水準は一般的な範囲といえます。
もしTOB価格が企業価値に比べ著しく低いと感じる場合、少数株主として意見表明する方法もあります。株主提案権や意見広告、あるいは議決権行使で不満を示すことで、場合によっては価格修正(プライスの引き上げ)に繋がることもゼロではありません。実際に親子上場TOBで投資ファンドが安値に反対し、買付価格が引き上げられた事例(例:NECによる子会社TOBでの価格見直しなど)もあります。もっとも、日本では買収防衛的な動きがない限り大幅な価格改善は稀であり、基本的には提示価格での売却を前提に行動する方が現実的です。
TOB成立後の対応も念頭に置きましょう。TOB期間中に売却しなかった場合でも、最終的に株式が強制的に買い取られる(キャッシュアウトされる)ことがあります。この際、上場廃止後に現金化されるまで時間がかかったり、手続きが煩雑になるケースもあります。市場で売却できる機会があるうちに手放すことで、こうした不確実性を避けられます。

スタンダード市場上場の親子上場企業4社と再編候補の根拠
今回は、トラスト同様に東京証券取引所スタンダード市場に上場しており、(1) 親会社が議決権ベースで株式の過半を保有する親子上場企業で、(2) 流通株式比率が上場維持基準(25%)を下回る懸念があり、(3) 親会社によるTOBやMBO、株式交換など再編が行われやすい条件を備えている銘柄をいくつかご紹介させていただきます。
大阪製鐵(5449)
- 親会社と保有比率:親会社は日本製鉄株式会社で、議決権ベース60.62%を保有しています。
- 流通株式比率:日本製鉄による過半支配に加え、アクティビストファンドであるストラテジックキャピタル(Intertrust T Japan)が2024年10月時点で約9.5%を保有(その後さらに買い増しし10%超に達したと報道されています)。日本製鉄の60.6%と自己株式7.9%を合わせると、流通株式比率は25%を下回る水準に低下する懸念があります。
- 上場市場:東証スタンダード市場
- 時価総額:約1,100億円(2025年5月現在)
- 再編候補の根拠:少数株主であるアクティビストが株式を買い進めた結果、上場維持基準である流通株比25%割れのリスクが高まりました。親会社の日本製鉄は対抗策として、自社保有株の一部をディスカウントTOB(公開買付)で処分するなど親子上場問題解消に動き始めており、いずれ親会社による完全子会社化(TOB)も視野に入ると見られます。また日本製鉄自身、グループ再編戦略の中で上場子会社の整理に積極的と報じられており、資金力も十分です。
近鉄百貨店(8244)
- 親会社と保有比率:親会社は近鉄グループホールディングス株式会社で、議決権ベース63.03%を保有しています。
- 流通株式比率:親会社の支配比率が高く、流通株式比率25%未満で上場維持基準に抵触する恐れが指摘されました。実際、2023年3月期時点で基準未充足であったため、同社は立会外分売による株式分散策を実施し、流通株比率を引き上げています。この結果、スタンダード市場の25%基準を一応クリアしたものの、親会社が依然6割以上を握る状況に変わりはありません。
- 上場市場:東証スタンダード市場
- 時価総額:約770億円(2025年5月現在)
- 再編候補の根拠:東証の市場再編に際し流通株比率の不足が表面化した典型例です。親会社と少数株主の利益相反リスクが指摘されており、東証からの要請で親子間の「自立協議」も始まっています。親会社の近鉄GHDは鉄道・流通グループの戦略上、百貨店事業の位置づけを再検討しており、過去にはグループ内再編(近鉄百貨店と近鉄商業開発の統合など)も行っています。親会社は財務規模が大きく(鉄道事業等で培った資金調達力あり)、今後少数株主への配慮からTOBによる完全子会社化も現実味を帯びると見られています。
ユタカ技研(7229)
- 親会社と保有比率:親会社は本田技研工業株式会社(ホンダ)で、議決権ベース69.66%を保有しています。
- 流通株式比率:ホンダが約7割を握るため市場流通分は3割程度に留まります。筆頭少数株主だったフィデリティ投信系ファンドが一時8%超保有していましたが、その後持株比率を引き下げたため現在は少数株主の持株はすべて10%未満に分散しています。従って直近の流通株式比率は約30%と基準は辛うじて充足するものの、親会社の追加取得などで容易に25%割れし得る状態です。
- 上場市場:東証スタンダード市場
- 時価総額:約350億円(2025年5月現在)
- 再編候補の根拠:ホンダ本体が株式の7割を保有し事実上完全支配している一方、株価指標ではPBR1倍割れで収益力も平凡とされ、市場からの評価が低迷しています。ホンダは過去に八千代工業(当時上場子会社)をプレミアム付きTOBで完全子会社化し、その後事業売却した実績があり、親子上場の解消に前向きな企業と目されています。ユタカ技研もホンダの戦略上、グループ再編(例えば他社との提携強化や売却)を柔軟に行う余地があり、少数株主との利益相反に配慮してホンダがTOB/MBOで非公開化するシナリオが取り沙汰されています。
三菱ロジスネクスト (7105)
親会社・持株比率: 親会社は三菱重工業(7011)で、議決権ベースの持株比率は約64.6%にのぼります。
流通株式比率: 東証スタンダード市場の上場維持基準25%を満たしておらず、流通株式比率は直近で25%未満となっています。親会社の高い持株比率ゆえ浮動株が不足し、上場維持基準に抵触するリスクが現実的です。
上場市場: 東証スタンダード市場(旧東証1部から市場再編時にスタンダードを選択)。
時価総額: 約2,200億円規模と推定されます。
再編候補理由: 親会社の三菱重工は資金力・実行力があり、他の重工大手と同様に親子上場解消に前向きとみられます。実際、2021年8月に三菱重工が当社を完全子会社化する検討に入ったと報じられた経緯があり、TOB(株式公開買付)による再編観測が市場で取り沙汰されました。親会社はすでにNTTや川崎重工など多くの企業が子会社上場を解消している潮流を認識しており、上場維持基準への抵触リスク解消とガバナンス強化のため、当社のTOB実施による完全子会社化を検討しやすい状況です。三菱重工自身も過去に事業統合・再編(フォークリフト事業の統合など)の実績があり、少数株主との利益相反問題を回避するためにも、当社の上場廃止(親子上場解消)に踏み切る可能性が高いと考えられます。
さいごに
最後にプレミアム狙いの事前投資戦略についても触れておきます。
親子上場関連株は「いずれTOBでプレミアム獲得できるのでは」と期待して先回り買いする投資家が増えてきていると思います。実際、親子上場解消が噂されると株価が思惑で上昇することもあります。ただし、いつTOBになるか確証はなく、長期間放置される可能性や、最悪基準未達で上場廃止(TOBなしで株主が市場で売る機会を失う)リスクもあります。したがってこの手法は中長期のリスク許容度がある中級者以上の投資家向きともいえます。
当サイトでもTOB候補銘柄を紹介していますが、不確実性の高いなかでTOBだけを目的に積極的に買い向かうのは得策ではありません。TOBだけを目的にすると、TOBが実行されるまでは機会損失を被ることも多いので、必ずTOBとあわせてプラスαの材料をもつ銘柄に投資をしておきたいところです。
プラスαの材料としては、たとえば以下のようにTOBがなくても株価が上がったり、リターンが見込めるような銘柄が理想的です。
- TOB+高配当
- TOB+黒字化銘柄
ぜひ、「TOB+α」の銘柄を探してみましょう!