【さくらインターネット】大幅下方修正!今後の株価はどうなる?経営戦略は正しい?
2025.07.29投稿
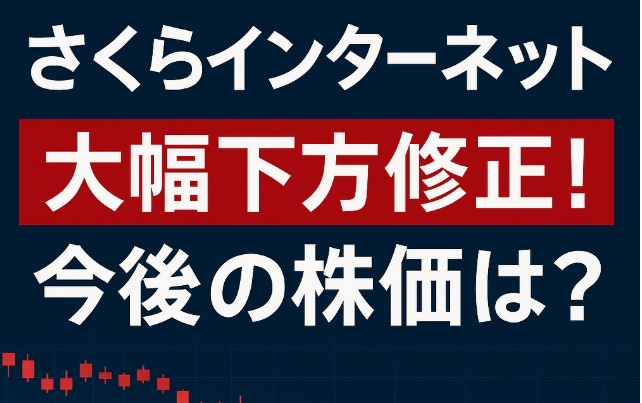
さくらインターネットの将来性や株価について、最新の業績動向、事業戦略、そして競合環境を踏まえて深く掘り下げていきます。
さくらインターネットの株価、今後はどうなる?【将来性予測】
なぜ今、さくらインターネットの将来性が注目されているのでしょうか?
さくらインターネットは、最近の生成AIブームの中で特に注目を集めています。
同社は生成AIに不可欠なGPUインフラストラクチャーサービスを提供しており、この分野の需要が爆発的に拡大したことで、その事業内容に高い関心が寄せられるようになりました。
しかし、2025年7月28日に発表された2026年3月期の業績予想下方修正により、株価の下落が見込まれ、同社の将来性について改めて多くの投資家や関係者が議論するきっかけとなっています。
この修正の背景には、生成AI向け大型案件の終了がありましたが、同時にクラウドサービスやレンタルサーバーといった他の事業は堅調に推移しているという複雑な状況があります。
さくらインターネットの株価はこれまでどのように推移しましたか?(急騰・暴落・テンバガーの背景)
さくらインターネットの株価は、ここ数年で劇的な変動を経験してきました。
特に2023年から2024年にかけての生成AIブームの時期には、GPU需要の急拡大を背景に、同社の株価は急騰し、「テンバガー」(株価が10倍になること)を達成するほどの勢いを見せました。これは、同社が国内におけるGPUインフラ提供の主要プレイヤーとして認識されたためです。
しかし、2025年7月28日の業績予想下方修正発表を受けて、PTS株価はストップ安をつけるほどの衝撃が走りました。この変動は、成長への期待と現実のギャップが市場に与える影響の大きさを物語っています。
株価の短期的な変動要因は何ですか?(PTS・ストップ安・需給から読み解く)
さくらインターネットの株価が短期的に大きく変動する主な要因は、市場の期待と実際の業績発表とのギャップです。特に、大幅な下方修正のようなネガティブなニュースが出た際には、発表直後の時間外取引であるPTS(私設取引システム)で大きく売られ、翌日の市場でストップ安となることもあります。
これは、投資家が一斉に株を手放そうとするために起こる現象です。株価は需要と供給のバランス、すなわち「需給」によって決まりますが、悪いニュースが出ると売りが優勢になり、結果として株価が急落します。
今回の下方修正も、この需給バランスが崩れた典型的な例と言えるでしょう。
なぜ大幅下方修正が発表されたのですか?【2026年3月期業績分析】
今回の大幅な業績予想修正は、具体的にどのくらいの影響がありますか?(売上・利益の具体的な数値)
さくらインターネットが2025年7月28日に発表した2026年3月期の業績予想下方修正は、同社の業績に非常に大きな影響を及ぼす見込みです。具体的な数値を比較すると、当初2025年4月28日に公表された予想から大きく変更されました。
| 業績予想(FY2026) | 4月28日発表 | 7月28日修正後 | 差異(減少幅) | 下方修正率 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 404億円 | 365億円 | △39億円 | △9.7% |
| 営業利益 | 38億円 | 3.5億円 | △34.5億円 | △90.8% |
| 経常利益 | 34億円 | 4億円 | △30億円 | △88.2% |
| 当期純利益 | 24億円 | 2億円 | △22億円 | △91.7% |
この表からわかるように、売上高は約1割の減少にとどまりましたが、営業利益、経常利益、当期純利益は、当初予想に比べて約9割という極めて大幅な減額となりました。
これにより、通期の営業利益は前期比で約91.6%減となり、実質的にほぼゼロに近い利益という厳しい見通しへと一変しています。

生成AI向け大型案件終了は、さくらインターネットにとってどれほど痛手だったのでしょうか?
生成AI向けの大型案件が継続を見込んでいたにも関わらず終了したことは、さくらインターネットにとって非常に大きな痛手でした。この影響で、GPUインフラサービスからの売上予想は当初の158億円から85億円へと半減しています。
この事業は、AIブームの中で同社の成長を牽引する主要な収益源となっていたため、その売上が突然半分になったことは業績全体に壊滅的な影響を与えました。特に、GPUサーバーへの巨額な先行投資が行われていたため、売上が計画通りに伸びない中で減価償却費やデータセンター費用、電力費といった固定費が急増し、利益を圧迫する直接的な要因となりました。
なぜ下方修正を事前に予測できなかったとの見方があるのでしょうか?
下方修正を事前に予測できなかったとの見方があるのは、4月時点の決算説明会での経営陣の説明と今回の発表内容に、一部で食い違いがあるように見えるためです。
4月の説明会で、経営陣は前期に「スポット(一時的)案件が入り、利益が過剰に伸びた」と振り返っており、今期の予想には「見込みが明らかになっている案件以外は織り込んでいない」と説明していました。また、「国立研究開発法人の大口案件が多かったが、ABCI(国策のAIブリッジングクラウド)の稼働開始で需要が分散し、大型案件がなくなる一方でクラウドサービスが伸びていく想定」とも明言していたのです。
これらの発言から、大型案件が途切れるリスクは認識されていたはずだと考えることができます。
それにも関わらず、GPUインフラサービスの売上を当初大幅に増加する計画を立て、それが3ヵ月という短い期間のうちに大きく未達になったという事実は、当初の見込みが楽観的すぎた可能性を示唆しています。
経営陣は「継続を見込んでいた案件が突然終了した」と説明していますが、国策のABCI稼働による需要シフトや、大口顧客の予算・計画変更といった要因も背景にはあったと考えられます。急速に変化するAI市場の不確実性が高かったことも要因の一つですが、投資家から見れば、より慎重な業績見通しを示す余地はあったのではないかという評価になるでしょう。
さくらインターネットのビジネスモデルと成長戦略の妥当性は?
収益の柱「GPUインフラサービス」の特性とリスクは何ですか?
さくらインターネットの収益の柱の一つである「GPUインフラサービス」は、AIの機械学習やデータ解析に不可欠な高性能GPUサーバーを貸し出すサービスです。このビジネスの特性は、大口顧客のスポット利用によって売上が大きく変動しやすい点にあります。
例えば、大規模なAIモデル学習のために数ヶ月間だけ数百台のGPUを占有利用するような大型案件があれば、売上が一時的に急増します。しかし、その案件が終了すると、稼働率が急落し、売上も減少するというリスクを抱えています。
また、この事業は、データセンター設備や高価なGPU機器への莫大な先行投資が必要となる固定費型です。一度設備を整えれば稼働率が上がるほど利益率も上昇しますが、稼働率が低下すると減価償却費などの固定費負担が利益を一気に圧迫します。
実際、GPU投資の拡大に伴い、減価償却費が前年同期の8.8億円から15.3億円へと約1.7倍に急増し、売上計画の未達と相まって、四半期赤字転落の直接的な要因となりました。
このように、GPUインフラサービスは急成長の可能性を秘める一方で、一部大型顧客の利用動向に大きく左右される変動性が高く、予測が難しいビジネスと言えます。
安定収益を支える「クラウド・レンタルサーバ」事業の現状と役割は?
一方、さくらインターネットのもう一つの柱である「さくらのクラウド」やレンタルサーバーといった従来サービスは、企業や個人にインターネット経由でサーバーやストレージなどを提供するストック型(継続課金型)のビジネスモデルです。この事業は多数の中小規模顧客に支えられており、毎月安定した利用料収入が得られる構造のため、売上が比較的予測しやすく、緩やかな成長傾向を辿ります。
同社のレンタルサーバーとクラウドサービス部門は着実にARR(年次経常収益)を積み上げており、両者合わせて142億円規模のARRを確保しています。これらの安定した収益源は、外部環境の変動にも比較的強く、景気動向や個別案件の影響で突然売上が半減するようなリスクは小さいのが特徴です。
GPUサービスの変動性を補う、安定した収益基盤としての重要な役割を担っています。
政府の「ガバメントクラウド」は、さくらインターネットの新たな成長ドライバーとなりますか?
政府が推進する「ガバメントクラウド」は、さくらインターネットにとって新たな、そして非常に大きな成長ドライバーとなる可能性があります。ガバメントクラウドとは、日本の行政機関向けの共通クラウド基盤のことであり、さくらインターネットは2023年11月に国内企業で初めてサービス提供事業者に選定されました。現在、デジタル庁が定める119項目の要件達成に向けた開発を急ピッチで進めています。
この取り組みの信頼性は高く、一度認定されれば国や自治体からの需要が本格的に流入する可能性が高いです。政府案件であるためハードルは高いものの、「国策」的な追い風もあり、データ主権や経済安全保障の観点からも政府の後押しを受けています。
行政機関のシステム移行には時間を要するため、短期的に目に見える成果が出にくいかもしれませんが、中長期的には政府需要という安定したストック収益源を得られる可能性があり、同社クラウド事業の底上げに大きく寄与するでしょう。
また、ガバメントクラウドへの取り組みを通じて得られる高度なセキュリティや運用ノウハウは、他の民間顧客にも付加価値として還元されると期待されます。
さくらインターネットが掲げる「高付加価値型GPU基盤」戦略は成功するでしょうか?(NVIDIA B200、ラインナップ拡充の狙い)
さくらインターネットが掲げる「高付加価値型GPU基盤」戦略は、同社の将来を左右する重要な鍵となるでしょう。この戦略の柱の一つは、最新のGPU技術をいち早く導入することです。
同社は2025年8月には新型GPUである「NVIDIA B200」(NVIDIA Blackwell世代)の提供開始を予定しており、これは前世代のGPUに比べて最大2倍のAI性能と1.5倍のメモリ帯域を持つとされ、特に大規模モデルの推論性能を飛躍的に向上させます。
この戦略のもう一つの狙いは、大型案件中心だったGPUクラウドの販売を中小規模の顧客にも広げることです。
クラウド型スパコンや生成AIプラットフォームといった多様な高性能GPU基盤を拡充し、大口顧客への依存から脱却し、よりバランスの取れた売上構成への転換を目指しています。これにより、一つの大型顧客に業績が左右されるリスクを低減し、GPUインフラ事業をより持続的な収益源に変えていくことが期待されます。
高性能GPUを大量導入した設備基盤は既に整備されつつあり、これを遊休化させずに、いかに付加価値高く稼働させるかが今後の成功の鍵となるでしょう。
パートナー戦略や新規市場開拓の具体的な狙いと進捗状況は?
さくらインターネットは、事業の成長をさらに加速させるため、新規市場の開拓とパートナーネットワークの活用に軸足を移しています。
新規市場としては、ガバメント(官公庁)領域に加え、医療分野や重要インフラ分野といった高度な信頼性や国内拠点が求められる領域を特に重視しています。これらの分野は、今後AI計算資源の需要が見込まれ、同社のGPUクラウドやIoT/エッジサービスを組み合わせたソリューション提供の余地が大きいと考えられます。ガバメントクラウドでの正式認定取得はその大きな一歩であり、官公庁関連の商談に参入しやすい地盤を築きつつあります。
また、パートナー戦略としては、クラウドインフラを販売するパートナー企業との提携プログラムを拡充し、SIerやソフトウェア企業と協業することで、エンドユーザーに最適な形でサービスを提供する体制を整えています。これにより、自社営業だけでは届きにくい業種や地域の需要を掘り起こし、「パートナー経由の販売と技術支援」というモデルでクラウド基盤の普及を図る狙いです。
特に中小企業や地方自治体は信頼関係のある地元のIT事業者経由でクラウドを採用するケースも多いため、パートナーネットワーク戦略は新市場浸透の有効な手段と言えるでしょう。この戦略は、国内AIインフラのハブとして多様なプレイヤーを巻き込み、ローカルエコシステムの強みを生かすことを目指しています。

競合他社と比較したさくらインターネットの強みと課題は?
グローバルクラウド大手(AWS、Azure、GCP)との差別化ポイントは何ですか?
さくらインターネットがグローバルクラウド大手であるAWS(Amazon Web Services)、Microsoft Azure、Google Cloudと差別化する主要なポイントは、国内完結性、きめ細やかなサポート、そして国内エコシステムの構築にあります。
グローバル大手は、NVIDIAの最新GPUを搭載した大規模な計算クラスターをオンデマンドで提供し、自社開発の専用半導体(AWSのInferentia、GoogleのTPUなど)による性能・コスト優位性、そして広範なAIサービスエコシステムを武器にしています。
これに対し、さくらインターネットは、サービスが国内データセンターで提供されるため、データが日本国内で完結できるという点が大きな強みです。これにより、金融機関や官公庁など、データ主権やセキュリティ面での厳格な要件を持つ顧客からの需要を獲得できます。
また、単にGPU算リソースを貸し出すだけでなく、AI活用に関するコンサルティングからモデル導入支援、運用代行まで一貫した手厚いサポートを提供できる点も差別化要因です。これは画一的なサービスを提供する海外大手には真似しにくい、日本企業向けのきめ細かな対応と言えるでしょう。
国内の主要競合(GMO、IIJ、NTT他)との比較で、さくらインターネットの優位性はありますか?
国内の主要競合であるGMOインターネット(GMOクラウド)、IIJ(インターネットイニシアティブ)、NTT系各社なども、生成AIブームを受けてGPUクラウドサービスを提供・拡充しています。これらの国内競合も、NVIDIAの最新GPUを導入し、国内クラウドとしての信頼性や日本企業向けのサポートを強みとしています。
この中でさくらインターネットの優位性としては、GPUビジネスに2016年から取り組み、長年のノウハウを蓄積してきた点が挙げられます。常に空きラックを確保し、急な需要増にも迅速に対応できる設備運用力を持つことで、新GPU世代への移行も含めたサービス提供の俊敏性で先行者利益を得てきました。
また、北海道石狩データセンターを拠点とし、冷涼な気候と再生エネルギー活用による効率的な運用(大規模GPUの水冷化など)で、持続的に高いTDPのGPUを稼働できる環境を整えていることも強みです。さらに、中小規模の顧客も多く抱えてきた実績から、柔軟で顧客目線の対応に定評があるサポート品質も優位点と言えるでしょう。
さくらインターネットが持つ「ローカル性(国内完結)」の価値とは何ですか?
さくらインターネットが持つ「ローカル性(国内完結)」は、特に日本市場において非常に大きな価値を持ちます。同社のサービスはすべて国内データセンターで提供されており、ユーザーのデータが完全に日本国内で完結できることを強調しています。これは、企業の機密情報や個人データを取り扱う上で、データ主権やセキュリティ面での高い安心感を提供します。
例えば、社内機密文書データを用いた生成AI活用(社内向けChatGPTのようなRAG構築)など、特定の要件を持つ場合に、データを完全に日本国内DC内に留めた運用や、閉域網接続、厳格な権限管理、通信暗号化といったセキュリティ要件に合わせたソリューションを提供できます。
このような特性は、海外クラウドを忌避する金融機関や官公庁からの需要を取り込む上で不可欠です。
実際、さくらインターネットは政府の「ガバメントクラウド」構想にも積極的に関与しており、日本のクラウドとしての地位を確立しつつあります。物理的な距離が近いことによる低遅延・高スループット接続や、日本の商習慣に即した柔軟な契約形態に対応しやすい点も、「日本のクラウド」であること自体の付加価値を高めています。
「さくらインターネット ひどい」という評価はなぜ見られるのですか?
「さくらインターネット ひどい」という評価が見られる場合、それは主に今回の大幅な業績予想下方修正と、それに伴う株価の急落に対する投資家の失望感から来ている可能性が高いです。特に、生成AIブームで株価が急騰し、将来性への期待が膨らんでいた中で、継続を見込んでいた大型案件の終了という予期せぬ事態が発生し、利益が大幅に減少する見通しとなったため、一部の投資家からは「期待を裏切られた」という厳しい評価が出ることがあります。
また、事前にリスクを十分に予測し、より保守的な業績見通しを示すことができなかったのではないか、という見方も「ひどい」という評価に繋がっているかもしれません。
しかし、これはあくまで短期的な業績変動と、それに対する市場の反応を示すものであり、同社の長期的な事業戦略や技術力、国内での立ち位置そのものを否定するものではない点も理解しておく必要があります。
【株価見通し】さくらインターネット株は今が買い時ですか?

中長期的な株価に影響を与える主要な要素は何ですか?
さくらインターネット株の中長期的な株価に影響を与える主要な要素はいくつかあります。
まず、AI推論市場全体の持続的な成長です。生成AIブームは一過性ではなく、各企業が業務へのAI実装を本格化させる「第二波」がこれから来ると見られており、これにより膨大な計算資源が必要となるでしょう。さくらインターネットは、この市場拡大期にGPUインフラサービスに経営資源を集中し、幅広い顧客層を取り込もうとしています。
次に、政府の「ガバメントクラウド」事業の進捗と成果です。同社が正式に認定され、国や自治体からの需要を本格的に獲得できれば、長期的な安定収益源が確保され、株価を下支えするでしょう。
さらに、「高付加価値型GPU基盤」戦略の成功も重要です。NVIDIA B200のような最新GPUの導入と、大口から中小口まで多様な顧客へのラインナップ拡充が、遊休GPUリソースの稼働率向上と売上分散に繋がるかが鍵となります。
最後に、パートナー戦略による市場開拓の加速も、中長期的な成長を支える要素です。
投資判断で注目すべき今後の重要指標はどこですか?(GPU稼働率、ガバメントクラウド進捗など)
さくらインターネットへの投資を検討する上で、今後特に注目すべき重要指標は以下の通りです。
- GPU稼働率の向上: 現在、GPUインフラサービスの売上が計画に対して遅れている主な原因は、GPU設備の稼働率が想定ほど高くないためです。今後の四半期決算で、この稼働率がどこまで早期に引き上げられるか、そしてそれによって売上が回復するかが最重要指標となります。
- ガバメントクラウド事業の進捗: 正式認定に向けた開発の進捗状況や、認定後の具体的な案件獲得状況が注目されます。行政機関のシステム移行は時間を要しますが、着実に案件を獲得できるかどうかが中長期的な収益安定の鍵となります。
- 新型GPU(NVIDIA B200など)の販売促進: 2025年8月から提供開始予定のNVIDIA B200などの最新GPUが、どれだけ市場のニーズを捉え、新規顧客や既存顧客からの受注に繋がるかが、GPU事業の成長を左右します。
- 顧客セグメントの分散: 特定の大型案件への依存度を低減し、中小規模顧客からの安定的な収益を増やす戦略が機能しているか、顧客構成の変化にも注目が必要です。
- 営業利益率の改善: 先行投資によるコスト負担が続く中で、収益性の改善が見られるかどうかも重要な指標です。
これらの指標の動向を継続的に注視することで、同社の業績回復と成長戦略の実現性を見極めることができるでしょう。
さくらインターネットの現状は「一時的停滞」と「継続的停滞」のどちらだと考えられますか?
さくらインターネットの現状は、現時点では「一時的停滞」である可能性が高いと考えられます。
今回の業績下方修正は、生成AIブームによる特需後の揺り戻しと、将来の成長に向けた積極的な先行投資による利益圧迫が重なった結果と見ることができます。同社自身も、今回の落ち込みは「生成AI市場の波の谷間」における一時的なものであり、中長期的には再成長軌道へ戻る可能性が高いとの見解を示しています。
その根拠として、生成AI関連需要自体は依然拡大基調にあること、そして同社自身が大規模GPU投資を継続し、次世代ニーズに備えている姿勢が挙げられます。2025年夏には最新GPUのサービス投入を行い、市場の裾野拡大に努めるなど「次の波」への備えを怠っていません。
また、クラウド・レンタルサーバー事業という安定収益源が着実に積み上がっている点も踏まえると、現在の業績悪化は一時的な谷と位置付けるのが妥当でしょう。
しかし、この「一時的」落ち込みを本当に一過性のものにできるかどうかは、今後の戦略遂行にかかっています。高付加価値GPUサービスによる需要喚起、新規市場(官公庁・産業分野)からの案件獲得、パートナー経由の販路拡大といった施策が奏功すれば、同社は再び成長軌道に乗り、今回の業績悪化は一時的な踊り場だったと証明されるでしょう。
もしGPU設備の稼働率向上が遅れ、投資回収が滞れば、重い減価償却負担が続くことで停滞が長引くリスクも否めません。
結論として、さくらインターネットは今まさに「一時的停滞か継続的停滞か」を分ける岐路に立っており、今後の同社の手腕が問われる正念場にあると言えるでしょう。
関連記事
【さくらショック?】生成AIブームとGPU需要停滞リスク:日本データセンター業界への影響分析
