【TOB事例】インフロニアHDによる三井住友建設TOBの背景と今後TOBの可能性がある建設株3選
2025.05.15投稿
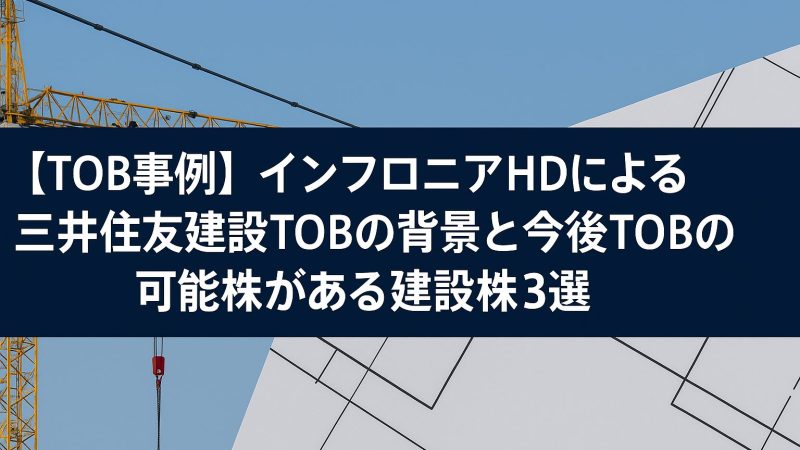
インフロニア・ホールディングスが三井住友建設を1株600円でTOBし、完全子会社化と上場廃止を目指します。資材高騰や人手不足で低迷する中堅ゼネコン再編の象徴で、割安株やアクティビストの動向が今後のTOB候補選定の鍵となります。
今回の記事では、TOBの背景とあわせて、今後同様の状況でTOBの可能性が見込まれる3銘柄の紹介をさせていただきます。
TOBに至った背景と目的
三井住友建設は国内中堅ゼネコンとして土木・建築両分野で事業を展開してきました。しかし近年、建設業界は資材価格の高止まりや人手不足、2024年施行の時間外労働規制による生産性低下などにより厳しい経営環境が続いています。加えて人口減少で公共工事の新規投資は縮小傾向にあり、中堅企業にとって単独での成長は課題となっていました。
三井住友建設自身、近年の収益力は低迷しておりROE(自己資本利益率)は5%台、PBR(株価純資産倍率)は1倍を下回る水準(2023年3月期で0.94倍)に留まっていました。
こうした低い株価評価は、企業価値向上を求める物言う株主(アクティビスト)の台頭を招き、実際三井住友建設の大株主上位には旧村上ファンド系の関係者と見られる投資家(南青山不動産、野村絢氏、レノ株式会社)が名を連ね、合計で約30%近い株式を握っていました。経営陣にとって、株主への説明責任を果たし企業価値を抜本的に高めるためには、抜本策が求められていたといえます。
こうした中、インフロニア・ホールディングス(インフロニアHD)は三井住友建設との事業統合を模索し始めました。インフロニアHDは2021年に前田建設工業・前田道路などを中核に発足した新興のインフラサービス統合企業で、中長期計画「Vision 2030」の下で事業領域拡大を掲げています。三井住友建設の参加により、インフロニアHDはグループ全体の建設エンジニアリング能力を強化し、設計・施工から維持管理までインフラ事業のバリューチェーン全体をカバーする体制を目指しています。
一方の三井住友建設も、インフロニアHDとの協業により国内建設事業の一層の強化や海外事業の拡大、DX推進や人材育成面でグループシナジーを享受できると判断しました。実際、インフロニアHDは総合インフラサービス企業への飛躍を目標に2025年3月に中期経営計画を刷新しており、その中でM&Aを通じた競争力強化を示唆していました。三井住友建設の技術力や顧客基盤を取り込むことは双方の戦略に合致し、業界再編の流れにも沿うものだったのです。
以上の背景から、インフロニアHDは2024年末頃から三井住友建設との交渉を本格化し、経営統合に向けた協議を開始しました。三井住友建設側でも社外取締役を含む特別委員会を設置し、独立した立場から提案を精査する体制を整えています。こうして企業価値向上と業界再編という双方の目的が合致し、最終的にインフロニアHDによるTOB実施という決断に至りました。
買収後、三井住友建設はインフロニアHD傘下で他のグループ会社(前田建設工業、前田道路、前田製作所、ジャパンウインド開発)とともに非上場の完全子会社となる予定です。

TOBの概要と今後のスケジュール
2025年5月14日、インフロニアHDと三井住友建設はTOB実施に合意したと発表しました。買付価格は1株あたり600円で、三井住友建設の発行済株式全てを取得すると約941億円規模の買収になります。この600円という価格は、発表前営業日の終値542円に約10.7%のプレミアム(上乗せ幅)を加えた水準です。
この価格に至るまでには複数回の交渉が行われており、当初インフロニアHD側は1株480円(直前株価に約10.9%のプレミアム)を提示しましたが、特別委員会は「著しく乖離している」と難色を示しました。その後段階的に530円→560円→570円と提案価格が引き上げられ、最終的に600円で合意に達した経緯があります。
特別委員会と三井住友建設取締役会はこの600円を「株主にとって受け入れ可能」と判断し、TOBへの賛同を決議しています。このように第三者算定機関の評価や法務アドバイザーの助言を踏まえ、公正な価格決定プロセスが進められました。インフロニアHD側・三井住友建設側双方に大和証券やSMBC日興証券、法律事務所といった専門家がアドバイザーとして付き、手続の公平性を確保しています。
買付けは2025年7月上旬開始を目指す予定で、公正取引委員会等の必要な手続き(フィリピン当局の競争法審査など)が完了次第、速やかにTOBが開始されます。TOBの買付期間は30営業日程度が予定されており、全株取得を目指すため下限成功条件(例えば2/3以上の応募など)が設定される見込みです。
三井住友建設の取締役会は本TOBに賛同を表明し、株主に応募を推奨する決議を行いました。これはすなわち本件が友好的買収であることを意味しており、買収後に現経営陣が排除されるような敵対的TOBではない点に注意が必要です。
インフロニアHDは既に三井住友建設株主の一部(シティインデックスイレブンス社など)と応募契約を締結しており、所定の条件でTOB開始すれば当該株主が全株応募する取り決めになっています。このことからインフロニアHDとしては所定の応募が得られる見通しであり、TOB成立に自信を示していると考えられます。一般株主にとっても、取締役会がお墨付きを与えた上での現金によるプレミアム買収提案であり、応じるか否かの判断材料はほぼ出揃った状況といえるでしょう。
事例から見る「TOBになりやすい会社」の特徴
今回の三井住友建設のケースは、日本株市場においてTOBの標的になりやすい企業の特徴を端的に示しています。一般に、近年増加しているTOB事例を分析すると、以下のような傾向が指摘されています。
- 特徴①:親会社等の不在(または親会社が株式を大量保有) – 親会社が50%以上保有する上場子会社は、その親会社によるTOB(完全子会社化)が起こりやすい傾向にあります。一方、三井住友建設のように明確な筆頭株主が不在で株主構成が分散している企業も、外部から経営権取得を狙われやすくなります。実際三井住友建設では信託銀行が13%で筆頭でしたが、特定の事業会社による支配は受けていませんでした。このように防衛的な大株主がいないことはTOBリスク(あるいは機会)の一つです。
- 特徴②:株価が割安で業績も伸び悩み – TOBを仕掛ける側にとって、企業価値に比べ株価が割安な銘柄ほど買収コストが低く魅力的です。特にPBRが1倍を下回るような企業は市場評価が低いことを意味し、投資ファンドなどから「宝の持ち腐れ」と見做されやすい傾向があります。三井住友建設も前述の通りPBRが1倍前後で推移し、純資産に比して株価が低迷していました。さらに直近のPERも100倍近い水準であり、利益水準の低さ=経営効率の悪さが浮き彫りになっていました。収益力低下や停滞感のある企業は、外部から「もっと効率的に経営できる」という目で見られ、買収ターゲットになりがちです。
- 特徴③:キャッシュリッチだが活用が遅れている – 一般論として、手元資金が潤沢であるのに成長投資や株主還元に活かされていない企業も狙われやすいと言われます。過大な現預金を抱えたまま低収益な事業を続けている場合、買収して内部留保を活用すれば価値向上余地があると判断されるためです。三井住友建設については特段の過剰資金は指摘されていませんでしたが、同業他社ではこの要因で株主提案を受けた例もあります。
- 特徴④:アクティビストの存在 – 最近の日本市場では物言う株主(アクティビスト)による株式取得が相次いでいます。とりわけ建設セクターでは村上世彰氏系列のファンドが大手・中堅ゼネコン株を次々と買い増ししている状況があります。彼らは業績に比して株価が低迷する企業に対し、経営改善策や大胆な資本政策(自社株買いやM&A)を要求します。三井住友建設も実際に村上系ファンドが大量保有し、最終的にインフロニアHDへの身売りという形でその要求に応えた側面があります。アクティビストが株主に入っている会社は、経営陣が自発的に改革を行うか、さもなくばTOBなどの劇薬で企業価値向上を図るか、いずれにせよ何らかの変化が起こりやすいと言えるでしょう。
以上の特徴をまとめると、「親会社にとって完全子会社化する動機がある」か「第三者にとって割安で放置されている」企業がTOBの対象になりやすい傾向があります。投資家としては、自分の保有株がこれらに該当するか注意を払い、仮にTOB提案が出た場合でも慌てず提示プレミアムの妥当性や今後の見通しを冷静に判断することが重要です。
将来TOBの可能性がある類似企業3選
では、三井住友建設と事業分野や規模、財務体質、株主構成が類似しており、将来的にTOBの対象となりうる企業にはどのようなものがあるでしょうか。ここでは例として3社を紹介します(※あくまで事例分析に基づく可能性の指摘であり、実際にTOBが起きるかは不確実です)。

西松建設(コード:1820)
トンネル工事などに強みを持つ中堅ゼネコンです。三井住友建設と同程度の売上規模を持ち、やはり過去に業績低迷から株価が低評価に甘んじていました。その結果、村上ファンド系の資金が2019年以降に株式を買い増し約25%を掌握、一時は経営陣と2年越しの攻防戦に発展しました。最終的に西松建設は自社株TOB(自己株買付による実質的買収防衛)を実施して村上勢と和解し、2021年末には伊藤忠商事を引受先に迎えて約10%の資本参加を得ています。
現在は伊藤忠が筆頭株主となったことで一旦安定しましたが、依然として独立系の立場であり、将来的に伊藤忠による追加TOBや他社との提携が取り沙汰される可能性は残っています。西松建設のケースは三井住友建設と同様に株主構成の変化が起爆剤となった例であり、“次の一手”にも注目が集まります。
安藤ハザマ(コード:1719)
2013年に安藤建設と間組が合併して誕生した中堅ゼネコンです。ビル建築から土木工事まで幅広く手掛け、売上規模は三井住友建設に近いものの、こちらも筆頭株主に親会社を持たない独立系です。
安藤ハザマについては、先述の村上系ファンドが株式を買い増している銘柄の一つと報じられており、実際に大量保有報告書が提出されたとの情報もあります。「物言う株主」に睨まれた状況下、将来的に経営陣がMBO(経営陣買収)や他社との資本提携によって株主の要求に応える可能性も否定できません。現在、安藤ハザマの業績は黒字を維持しているものの、大手に比べ規模のハンデがあるため業界再編の波にさらされやすい立場にあります。株価指標面でもPBR1倍前後で推移しており、引き続きTOBリスク・チャンスのある企業と言えるでしょう。
淺沼組(コード:1852)
大阪に本拠を置く中堅ゼネコンで、関西圏の民間建築に強みを持ちます。淺沼組も独立系で特定の親会社はおらず、株主には機関投資家の他、村上系ファンドとみられる持株も報告されています。規模的には三井住友建設よりやや小さいものの、堅実な経営で財務基盤は比較的安定しています。しかしながら成長余地の限界や世代交代期の経営課題を抱えており、ここ数年は株主還元策の強化などに努めている状況です。
こうした中で、さらなる企業価値向上策として他社との経営統合が選択肢に上がる可能性は否めません。実際、同社株は一部の投資ファンドから「割安」と評価するレポートも散見され、将来的にTOBの誘因が揃えば動きが出てもおかしくない状況です。
まとめ
以上の3社はいずれも三井住友建設と同じ建設業界に属し、規模や株主構成も類似点が多い企業です。共通するのは「現状のままでは株主価値向上に限界があり、外部資本の導入余地がある」という投資家目線での評価です。また、今回のような建設会社銘柄は配当利回りが高いこともあり、「高配当TOB待ち銘柄」としても魅力的といます。
近年、東京証券取引所がPBR1倍割れ企業に改善を促す動きを強めていることもあり、経営陣自らが改革に乗り出さない企業は市場から淘汰される圧力が高まっています。もちろん、ここで挙げた企業が必ずTOBされるわけではありませんが、一般投資家としては日頃から企業の財務指標や大株主動向に目を配り、「次の三井住友建設」がどこになる可能性があるのかアンテナを張っておくことが重要でしょう。

さいごに
最後にプレミアム狙いの事前投資戦略についても触れておきます。
親子上場関連株は「いずれTOBでプレミアム獲得できるのでは」と期待して先回り買いする投資家が増えてきていると思います。実際、親子上場解消が噂されると株価が思惑で上昇することもあります。ただし、いつTOBになるか確証はなく、長期間放置される可能性や、最悪基準未達で上場廃止(TOBなしで株主が市場で売る機会を失う)リスクもあります。したがってこの手法は中長期のリスク許容度がある中級者以上の投資家向きともいえます。
当サイトでもTOB候補銘柄を紹介していますが、不確実性の高いなかでTOBだけを目的に積極的に買い向かうのは得策ではありません。TOBだけを目的にすると、TOBが実行されるまでは機会損失を被ることも多いので、必ずTOBとあわせてプラスαの材料をもつ銘柄に投資をしておきたいところです。
プラスαの材料としては、たとえば以下のようにTOBがなくても株価が上がったり、リターンが見込めるような銘柄が理想的です。
- TOB+高配当
- TOB+黒字化銘柄
ぜひ、「TOB+α」の銘柄を探してみましょう!