将来の成長性に期待!AIエージェント関連の注目日本株をカテゴリー別に紹介
2025.05.04投稿
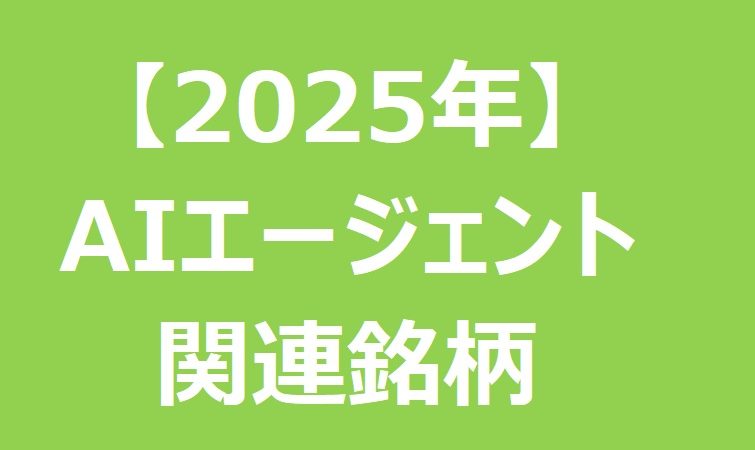
AIエージェントとは、人間のように自律的に考え、複雑なタスクをこなしてくれるAIのことです。従来のチャットボットや音声アシスタントが「質問に答える」レベルだったのに対し、AIエージェントはユーザーの目的を理解し、複数のプロセスを組み合わせて目標達成に動く点が特徴です。例えばスケジュール調整や情報収集、ドキュメント作成などを専属の秘書のようにサポートし、フィードバックから学習してさらに賢くなります。こうしたAIエージェントは、少子高齢化や人手不足に直面する日本にとって生産性向上の切り札と期待されています。
実際、日本政府もAIを産業競争力強化の柱と位置付けており、自動運転や業務効率化などAI活用分野への支援を国策として積極化しています。野村総研の推計によれば、2030年頃には日本企業のAI利用率は50%を超え、国内の法人向けAIエージェント数も約200万〜900万体に達すると予想されています。これはAIエージェントが電気に匹敵する汎用技術として社会に浸透し、人々の働き方を大きく変革する可能性を示唆します。
もっとも、日本企業はAIエージェント導入に慎重な面もあります。PagerDutyの調査によれば、「AIエージェントを迅速に導入している」企業は世界平均32%に対し日本ではそれを下回り、約7割の企業が「現在模索中」と回答したとの報告があります。慎重さの裏返しとして、日本企業は業務品質やリスク管理を重視しながらAI活用を検討しているとも言えるでしょう。それでもNTTデータによるOpenAI社ChatGPTの企業向け提供開始など2024年以降、国内でもAIエージェント普及の動きが本格化してきました。2025年は「AIエージェント元年」とも称され、関連株への注目が高まっています。
以下では、将来の成長性が期待される日本のAIエージェント関連銘柄をカテゴリー別に紹介します。自然言語処理やチャットボット、音声認識、自動運転支援、業務効率化といった分野ごとに、厳選した注目企業を取り上げます。それぞれ企業概要、AIエージェントとの関連性、成長性の根拠、初心者・中級者向けワンポイントアドバイスを整理しますので、ぜひ投資の参考にしてください。
自然言語処理(NLP)関連
PKSHA Technology(3993) – 自然言語処理アルゴリズムの提供企業
企業概要:
PKSHA Technology(パークシャ・テクノロジー)は、東京大学発の機械学習スタートアップで、自然言語処理を中心としたアルゴリズムソリューションを提供する企業です。文章や会話の理解、画像認識、予測分析などAIエンジンを開発し、金融・製造・サービス業など幅広い企業にライセンス提供やカスタムAI開発を行っています。トヨタ自動車が株式の2.3%を出資していることからも、大企業から技術力を評価されていることが伺えます。
AIエージェントとの関連性:
PKSHAは元々チャットボットや対話エンジンの技術を持ち、2023年以降は自社AIをより自律的に動く「AIエージェント」へと進化させる取り組みを強化しています。2025年4月には新サービス「PKSHA AI Agents」をローンチし、社内ヘルプデスクや顧客対応などに特化したエージェント型AIソリューションの提供を開始しました。これは従来のチャットボット・ボイスボットに能動的にタスクを遂行する機能を追加したもので、PKSHAグループ全体で人事や営業領域への導入も進めています。すでに全国47都道府県で7,000体以上のAIエージェントが稼働中といい、国内AIエージェント数でNo.1シェアを謳っています。
成長性の根拠:
同社の強みは高い日本語処理能力と大企業との協業実績です。前述のトヨタだけでなく、LINEヤフーや地方銀行などとも連携し、業界特化型AIチャットボットを開発してきた実績があります。また生成AIの隆盛にいち早く対応し、自社プロダクトへのChatGPT統合など機能拡充を進めています。社内問い合わせ自動化サービスでは顧客企業で年間8,000時間の工数削減を実現した例もあるとされ、企業のDXニーズに応えるソリューションとして引き合いが増えています。今後は2025年の大規模アップデート(カンパニー制導入)に向け、さらなるサービス発表が予定されており、国内AIエージェント市場のリーダー企業として中長期的な成長が期待できます。
初心者・中級者向けワンポイントアドバイス:
PKSHAは時価総額数百億円規模のグロース株で、業績よりも将来性への期待で株価が動きやすい傾向があります。値動きがボラティリティ高めのため、初心者は少額から分散投資で臨み、中級者は調整局面を狙った押し目買いを意識すると良いでしょう。大企業との提携ニュースやAI関連のテーマ性で株価が急騰することもある反面、調整も大きいため、長期視点で技術力に賭ける投資がおすすめです。
チャットボット関連
モビルス(4370) – チャットボット国内シェアNo.1のCX支援企業
企業概要:
モビルス株式会社は、企業のカスタマーサポート向けチャットボットやデジタル接客ツールを提供するソフトウェア企業です。コールセンター向けの対話システム「MOBI AGENT」や自動応答チャットボット「MOBI BOT」などを開発し、金融機関・通信会社・自治体など多数の導入実績があります。同社は2017年度以降7年連続でチャットボット市場売上シェアNo.1を獲得しており、国内チャットボット業界のリーディングカンパニーです。
AIエージェントとの関連性:
モビルスの製品はまさに対話型AIエージェントの先駆けと言えます。同社のチャットボットはFAQ回答だけでなく、対話の文脈を理解して適切なガイダンスを行ったり、有人対応とのスムーズな切替えが可能です。近年はLINEやMicrosoft Teamsなど外部プラットフォームと連携したチャットボットも提供し、顧客対応エージェントを様々なチャネルで活躍させています。また音声認識AI「MOBI VOICE」も展開し、電話音声から自動で要件を聞き取るボイスボットにも力を入れています。これらは高度化すれば問い合わせ対応を人に代わって自律処理するAIエージェントそのものと言えるでしょう。
成長性の根拠:
チャットボット市場はここ数年で急成長を遂げており、モビルスも売上を順調に伸ばしています。特に顧客企業のDX推進や人手不足対応のニーズから、金融業や自治体での導入が加速しています。同社は市場調査会社ITRのレポートで2017~2023年度連続シェア1位と評価される実績に加え、LINEヤフー株式会社から「マーケティングソリューションパートナー」に認定されるなど、大手プラットフォーマーとの協業関係も築いています。さらに近年の生成AIブームでチャットボットの対話精度向上が見込まれる中、既存顧客基盤を持つモビルスは新技術の適用によりサービス価値を高めやすい立場です。2023年には大手通信会社との資本業務提携も行い、財務基盤強化と事業シナジー創出が図られています。このようにトップシェアの地位と新技術トレンドの追い風を受け、チャットボット界の優等生として今後も安定成長が期待されます。
初心者・中級者向けワンポイントアドバイス:
モビルスの株価は上場以来やや落ち着いた推移でしたが、AIブームで注目が集まると出来高が増える傾向があります。ディフェンシブ寄りのグロース株と言え、業績は堅調でも急騰・急落しにくい面があります。初心者の方は長期保有でじっくり企業成長を狙う戦略が合っているでしょう。一方、中級者は生成AIとの連携などニュース材料に敏感に反応する可能性も踏まえ、話題性で短期的に伸びた場合は利確タイミングを検討するなどメリハリを付けた運用も有効です。業界トップとはいえ時価総額規模は小さめなので、投資配分はポートフォリオの一部に留めるのが無難です。
音声認識関連
アドバンスト・メディア(3773) – 音声認識「AmiVoice」で国内トップクラス
企業概要:
アドバンスト・メディアは、音声認識エンジン「AmiVoice(アミボイス)」を開発・提供する国内有数の音声認識専業ベンダーです。1997年創業と歴史も長く、医療分野の音声入力やコールセンター通話のテキスト化、会議の自動議事録作成など多様な用途で同社の技術が使われています。最新のディープラーニング技術を採用したAmiVoiceは高い認識精度を誇り、金融・医療・製造など各業界の専門用語にも対応できる柔軟性があります。例えば大手金融グループのりそなホールディングスでは、同社の文字起こし支援アプリ「ScribeAssist」がグループ13社で導入されており、業務効率化に貢献しています。
AIエージェントとの関連性:
音声認識はAIエージェントの「耳と口」に当たる重要技術です。アドバンスト・メディアは音声認識に加え、音声合成や対話管理の技術も組み合わせて音声対話型AIアバターの開発を進めています。例えば2023年9月には、自社の音声対話システムにOpenAIのChatGPTを連携させ、茨城県公認VTuber「茨ひより」をAI化した案内システムを茨城県庁で試験設置しました。来庁者が話しかけると庁内の案内や質問回答を自然な会話で返すAI受付嬢のような役割を果たし、話題となりました。また2024年9月には、会議議事録作成ソリューションを統合した新プラットフォーム「VoXT One」をリリースし、その中でChatGPTと連携した議事録エディタ(ProVoXT)を提供開始しています。これはAIが会議音声をテキスト化し要約や整理まで行うもので、まさに音声AIエージェントが実務を代行する先進例と言えます。
成長性の根拠:
音声認識市場は、コールセンターの省力化ニーズや議事録作成の効率化ニーズなどを背景に着実に拡大しています。アドバンスト・メディアはその分野で高いシェアを持ち、近年は生成AIとの融合によって新たなサービス価値を創出しています。前述のVoXT Oneのように、自社の強みである音声認識にChatGPTの言語生成能力を組み合わせることで、一段上の付加価値(要約や対話機能など)を提供可能になりました。さらに官公庁や金融機関での採用例が増えており、安定したストック収益(音声認識サービスの利用料収入)も積み上がりつつあります。2024年11月の株式市場ニュースでは、チャットGPTブームの中で音声認識×生成AIの文脈で同社が取り上げられ、株価も注目を集めました。総じて、音声AIの老舗企業が最新AIトレンドを取り込み再成長を図っている状況であり、中期的にも堅調な業績拡大が見込まれます。
初心者・中級者向けワンポイントアドバイス:
アドバンスト・メディアは業績に波がある傾向があり、黒字転換や大型受注のニュースで株価が動きやすい銘柄です。初心者の方は直近業績や受注動向を注視しつつ、中長期では「音声AI需要は堅い」という視点で持つのも一案です。配当は無く株価変動も大きめのため、短期で成果を求めず腰を据えて技術力の強さに賭ける姿勢が求められます。中級者の方は、生成AI関連のテーマに乗って物色される局面では出来高増加に伴うトレンド転換を狙うなど、テクニカル面も活用してみましょう。いずれにせよテーマ性と実需を兼ね備えた銘柄ですので、中長期の成長ポテンシャルに期待して継続チェックすることをおすすめします。
自動運転支援関連
アイサンテクノロジー(4667) – 高精度3D地図で自動運転を支える先駆者
企業概要:
アイサンテクノロジーは、自動運転に不可欠な高精度3次元地図(HDマップ)の生成技術を持つ企業です。もともと測量ソフトやGIS(地理情報システム)を手掛けてきた老舗で、そのノウハウを活かし自動運転用地図や位置情報サービスに進出しました。自動運転実証実験が各地で行われる中、同社の高精度地図データは公道上のセンチメートル単位の位置特定を可能にし、各プロジェクトで採用が進んでいます。加えて、道路インフラの点検や都市計画にも3D地図活用が広がっており、官民から注目される存在です。
AIエージェントとの関連性:
自動運転車は言わば「車輪のついたAIエージェント」です。AIが認識・判断・操作を自律的に行うため、自動車分野でもAIエージェント技術が鍵となります。アイサンテクノロジーは直接AIアルゴリズムを開発する会社ではありませんが、AIが正確に環境認識し行動するためのデータ基盤(高精度地図)を提供しています。車載AIがカメラやセンサーで捉えた情報を地図と照合することで、自車位置を正確に把握し、安全な経路選択を可能にします。同社は国内外の自動運転関連コンソーシアムにも参加しており、オープンソースの自動運転OS「Autoware」を推進する団体では設立メンバーとして貢献しています。さらに2023年には三菱商事と共同で「A-Drive」社を設立し、自動運転のワンストップサービス事業に乗り出しました。これは地図データ提供のみならず、自動運転車両やシステム・インフラまで含め包括支援する試みで、AIエージェントとしての車両運行をトータルに支援する体制と言えます。
成長性の根拠:
自動運転は2030年代に60兆円規模の市場になるとの予測もあり、国策としてもレベル4(特定条件下での無人運転)実現に向け法整備や補助金が進んでいます。2023年4月には改正道路交通法が施行され、条件付きで無人自動運転移動サービス(レベル4)が解禁されました。これを受けて地方での自動運転バス運行が始まるなど、実用化が具体的に動き出しています。アイサンテクノロジーはこの流れの中で地図インフラ提供という独自ポジションを築いており、競合が限られるため恩恵を受けやすい状況です。実際、同社の業績は自動運転関連受注の増加で拡大基調にあります。また三菱商事との合弁事業は資金力と営業力のバックアップをもたらし、大型プロジェクトへの参画機会を広げています。以上より、自動運転社会の到来とともに中長期で飛躍が期待される銘柄です。
初心者・中級者向けワンポイントアドバイス:
アイサンテクノロジーは小型株かつテーマ色が強いため、材料ニュースにより株価が急騰・急落しやすい側面があります。初心者の方はテーマの盛り上がりに飛び乗るより、業績推移を見極めて割高感のない水準でコツコツ買う方が安全でしょう。一方で、自動運転関連のニュース(法規制緩和や大手企業との提携発表など)が出ると短期的に株価が跳ねることも多いので、中級者の方は情報収集を密に行いイベントドリブン型の短期取引に活用する手もあります。ただしテーマ株特有のボラティリティには注意が必要です。将来性は大きいものの収益化には時間がかかる可能性もありますので、投資スタンスとしては腰を据えて次世代インフラ構築に参加する気持ちで臨むと良いでしょう。
業務効率化(エンタープライズAI)関連
NTTデータ(9613) – 大手SIによる生成AI活用とスマートエージェント
企業概要:
NTTデータは言わずと知れた国内最大級のシステムインテグレーターで、金融機関や官公庁をはじめ幅広い業界のITシステム構築を担っています。近年はDX(デジタルトランスフォーメーション)需要の追い風も受け、コンサルから開発、運用まで一貫サービスを提供する体制を強化しています。グローバル展開も積極的で、世界50カ国以上で事業を展開する日本発グローバルSI企業です。安定した収益基盤を持ちながら、新技術への対応にも意欲的で、AI分野でも独自のフレームワーク開発や海外企業との連携を進めています。
AIエージェントとの関連性:
NTTデータは生成AI(Generative AI)を企業システムに安全に実装する先導役として注目されています。2025年4月、OpenAI社との戦略的提携を発表し、ChatGPT Enterpriseの日本初の販売代理店となりました。これにより大手企業向けにChatGPTを組み込んだ業務支援AIの提供を本格化しています。同社はAIエージェント活用コンセプト「SmartAgent™」を掲げており、金融・製造・公共など業種別に業務特化型AIエージェントを開発・提供するとしています。例えば、社内の膨大な資料から必要情報を探し出したり、会議の内容を解析してアクションアイテムを提案したりと、人に代わって考え動くAI社員のようなサービスを構想しています。NTTデータはこの提携により2027年度末までに関連事業で累計1,000億円規模の売上を目指す計画で、まさにAIエージェントを次の成長ドライバーと位置付けています。
成長性の根拠:
最大の根拠は、NTTデータが持つ顧客基盤と信用力です。同社は金融機関の勘定系システムなど超ミッションクリティカルな領域を長年担ってきた実績があり、国内企業からの信頼は絶大です。そのNTTデータが提供する生成AIソリューションであれば、「情報漏洩のリスクが低く安心して使える」と多くの企業が導入に前向きになると考えられます。実際、提携発表時にはまず大手企業100社に対し専門人材による導入支援を行うとされており、トップ企業から順次AIエージェント活用が進む可能性があります。またNTTデータは日本だけでなく欧米やアジアにも顧客を抱えるため、一度確立したソリューションはグローバル展開によるスケールメリットが期待できます。現在は人手不足でIT技術者の生産性向上が課題となっており、自社内開発にもAIエージェントを活用して効率化を図る動きがあります。こうした内外両面でのAI需要に対応できるのは同社の強みで、中長期での安定成長シナリオに組み込まれています。
初心者・中級者向けワンポイントアドバイス:
NTTデータは時価総額も大きく業績安定した優良株で、AIテーマとはいえ急騰劇よりも着実な株価推移が見込まれます。初心者にとっては安心感のある銘柄であり、配当も年数%出ていますから長期保有にも適しています。AIエージェント分野での成長が本格化すれば中長期で株価水準の切り上げも期待できますが、短期的には日経平均やNTTグループ全体の動きに左右されやすい点には留意しましょう。中級者の視点では、ディフェンシブ×グロースのバランスが取れた銘柄としてポートフォリオのコアに位置付けるのも良いでしょう。目先のテーマ熱に惑わされず、四半期決算での受注状況やAI関連売上の進捗をチェックしつつ腰を据えて付き合うことで、着実なリターンを狙える銘柄と考えられます。
参考:TOB候補銘柄
別途「【TOB候補】NTTデータグループ(親子上場)」という記事でも取り上げていますが、NTTグループとしてのTOBの可能性も排除できない点も留意点です。その点でも監視銘柄としておくのもよいでしょう。
オープングループ(6572) – オフィス業務のデジタルレイバー創出企業
企業概要:
オープンアソシエイツ(旧社名:RPAホールディングス)は、ホワイトカラー業務を代替するソフトウェアロボット、いわゆるRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の提供で国内をリードする企業です。主力の「BizRobo!」は定型的なPC作業を自動化するツールで、銀行の事務処理やメーカーの受発注処理など様々な現場で活用されています。同社は2013年頃から国内に先駆けRPA事業を開始し、「オフィスにロボットを普及させる」というビジョンを掲げ急成長しました。近年はグループ内でAI関連の新規事業にも投資し、画像認識やチャットボット分野のスタートアップ支援など事業ポートフォリオを広げつつあります。
AIエージェントとの関連性:
RPAはある意味、特定タスクに特化したシンプルなAIエージェントと捉えることができます。決められた手順で人間の代わりに業務をこなすという点で、広義のエージェント技術と言えます。RPAホールディングスは近年、従来型RPAに加えて機械学習や自然言語処理を組み合わせた高度な知的プロセス自動化(IPA)領域に注力しています。例えば、紙の書類をAI-OCRで読み取りRPAで入力処理まで完結させるソリューションや、チャットボットとRPAを連携させ問い合わせ対応からバックエンド処理まで自動化する取り組みなどです。つまり、単なるロボットに留まらず判断力を備えたAIエージェント的なロボットを実現しようとしています。またGenerative AIについても研究を進めており、生成AIが作成した文章をRPAが別システムに登録するといった一連の自動化も視野に入れています。こうした動きは、最終的に人間の知的作業を丸ごと代替するAIエージェントの創出につながるでしょう。
成長性の根拠:
日本社会では今後も労働力人口の減少が避けられず、業務自動化ニーズは長期的な追い風です。同社は「人とテクノロジーの共創で新たな事業を創る」というミッションを掲げ、RPAを皮切りに生産性革命を牽引してきました。ピーク時ほどの急成長は落ち着いたものの、依然として売上は緩やかながら拡大基調にあります。また、RPA市場で培った顧客網(金融、製造、サービス業など大手多数)は新たなAIソリューション展開の下地として有力です。実際グループ会社を通じてAIスタートアップと協業し、既存顧客にAI導入提案を行うケースが増えています。さらに政府のデジタル庁創設や中小企業のIT投資支援策など、政策的にも業務DXは追い風です。米国やアジア展開を視野に入れており、ソフトウェアのサブスクリプション収入を世界規模で積み上げるポテンシャルがあります。総合すると、短期の派手さは薄れても底堅いニーズに支えられた成長ストーリーは健在と言えます。
初心者・中級者向けワンポイントアドバイス:
同社の株価は上場直後に急騰した経緯がありますが、その後は業績成長の鈍化もあって落ち着きを取り戻しています。株価水準は一時期より割安感が出ているものの、再成長への確信が持てるまでは大きく動きにくいかもしれません。初心者の方は業績推移や新規案件のニュースを注視しつつ、「攻めすぎない範囲」で中長期投資を検討すると良いでしょう。中級者の方でテーマ性を狙う場合、生成AIやDX関連の材料と絡めて物色されるタイミングを狙う手もあります。ただし流動性が極端に高い銘柄ではないため、大量の売買は板に影響を与えやすい点に留意が必要です。足元の堅実路線に期待しつつ、再ブレイクの芽も持つ銘柄としてポートフォリオのスパイスに加えるイメージが適当でしょう。
今後の展望とまとめ
AIエージェント関連株は、以上に紹介したように様々な業種・領域にまたがって存在しています。日本企業は慎重ながらも確実にAIエージェント活用へ舵を切りつつあり、政府の推進策や海外AI企業との連携も相まって、市場規模は今後飛躍的に拡大するでしょう。特に2025年以降は企業内の情報検索や定型業務はAIエージェントが当たり前に行う時代が来るとの見方もあり、関連するサービス提供企業のビジネスチャンスは大きいと考えられます。
投資家にとっては、AIブームによる短期的な過熱感には注意しつつも、腰を据えて有望企業の成長を追う姿勢が肝要です。大企業系の安定株から新興の専門特化株までバラエティに富むため、自身のリスク許容度に応じて銘柄を選びましょう。初心者であればNTTデータのような安定感のある企業から入り、中級者であればPKSHAやアイサンテクノロジーのような尖った成長株にも分散投資してみるといった戦略が考えられます。
最後に、AI技術の進歩は非常に速く、新たな有望企業が登場する可能性もあります。常に最新の業界動向や企業のIR情報に目を配り、変化に柔軟に対応する投資判断を心がけましょう。AIエージェントは人々の生活や産業構造を変えるポテンシャルを秘めています。その波に乗る企業の成長ストーリーに期待しつつ、適切なリスク管理のもとで将来のリターンを狙っていきたいところです。
以上、AIエージェント関連の注目日本株をカテゴリー別に紹介しました。皆様の投資リサーチの一助になれば幸いです。ぜひ今後の相場動向や各社のニュースもチェックしながら、未来を先取りする投資チャンスを掴んでください。