【2025年6月テーマ株】国内初の仮想通貨取引所IPOに期待 – ビットバンク上場観測と関連注目株の分析
2025.05.07投稿
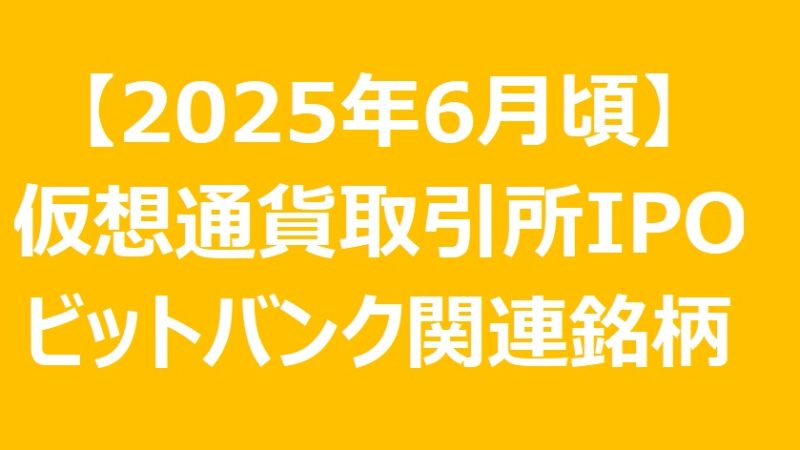
暗号資産(仮想通貨)が誕生してからわずか十数年。ビットコインは今年ついに1BTC=1万5千ドルを超え、市場規模は日本株全体の時価総額に匹敵するまで拡大しました。けれども日本の投資家にとって、暗号資産ビジネスは依然として「非上場ベンチャーの領域」であり、株式市場と交わる機会は限られてきました──その常識を覆す一歩となりそうなのが、暗号資産取引所「ビットバンク」のIPO(新規株式公開)観測です。
同社はアルトコイン取扱数で国内トップクラスを誇り、初心者からヘビーユーザーまで幅広い層を取り込んできた取引所。2025年半ばをめどに東京証券取引所への上場を目指すと表明したことで、「国内初の暗号資産取引所IPO」という歴史的ニュースが現実味を帯びてきました。もし上場が実現すれば、ビットコインETF誕生に沸く米国市場さながらに、日本株市場でも暗号資産関連銘柄の再評価が一気に進む――そんな期待が高まっています。
本記事では、ビットバンクのビジネスモデルや上場の意義を読み解きつつ、出資企業であるミクシィ・セレスをはじめ、SBIホールディングスやマネックスグループなど関連度の高い日本株を網羅的に分析。各銘柄の直近株価の動きやチャート傾向、暗号資産市況との連動性、そして今後の投資ポイントを初心者にも分かりやすく解説します。
「仮想通貨そのものは触ったことがないけれど、関連株なら投資対象として検討したい」「含み益銘柄を事前に押さえておきたい」という投資家にとって、ビットバンクIPOは絶好のリサーチ機会です。暗号資産市場と日本株市場が本格的に結び付こうとするいま、次のテーマ株を先回りで掴むためのヒントを、ぜひ最後までお読みください。
ビットバンクとは?事業内容と業界での立ち位置
ビットバンク株式会社は2014年設立の暗号資産(仮想通貨)取引所運営企業です。運営する取引所「bitbank(ビットバンク)」は、国内最大級の取引量を誇り、ビットコインやイーサリアムをはじめとする多数の銘柄の売買が可能です。特にアルトコイン(ビットコイン以外の暗号資産)取引に強みを持ち、取扱銘柄数は国内No.1(2023年時点で40銘柄以上)とされています。公式サイトでも「500円からビットコインをはじめられる」と手軽さをアピールしており、日本円の即時入金・出金などユーザビリティにも定評があります。
ビットバンクの収益源は主に取引手数料であり、その業績は暗号資産市場の出来高に大きく左右されます。実際、2021年12月期には仮想通貨価格高騰による取引活発化で営業収益約101億円・経常利益約51億円を計上しましたが、翌2022年は相場低迷で営業収益0.94億円・経常損失25.6億円と急減速しました。2023年12月期には再び黒字回復しています。このように市場環境に業績が連動しやすい点は暗号資産取引所ビジネスの特徴であり、ビットバンクも例外ではありません。
業界内でのポジションとしては、国内ではbitFlyer(ビットフライヤー)やCoincheck(コインチェック)などと並ぶ大手交換業者の一角です。特にCoincheckが初心者向けアプリや販売所サービスでユーザー数を伸ばす一方、ビットバンクは板取引(取引所形式)で安い手数料と高流動性を提供し、中上級者や積極的トレーダーから支持を集めています。2024年下期時点のデータでは、ビットバンクはアルトコイン取引高で国内シェアトップ、Coincheckはビットコイン現物取引高で国内トップという棲み分けがみられます。またビットバンクは取引手数料が板注文の場合メイカー(指値)で-0.02%と“取引するほど得をする”仕組みを採用しており、この点も流動性向上に寄与しています。以上から、ビットバンクは豊富な銘柄数と高い流動性を武器に国内暗号資産取引インフラの中核を担っていると言えます。
ビットバンク上場の意義と市場へのインパクト
そんなビットバンクが2025年半ばを目途に東京証券取引所への新規株式公開(IPO)を目指しているとの報道があり、業界内外で注目を集めています。これは2024年末のオンラインイベントで廣末紀之CEO自身が明らかにしたもので、市場関係者の間では期待感が高まっています。実現すれば、国内の暗号資産交換業者としては初の株式上場となり、画期的な事例となります。
ビットバンク上場の意義は大きく二つあります。第一に、暗号資産業界の企業が伝統的な株式市場で評価を受ける初めてのケースとなることで、業界の信頼性・成熟度が飛躍的に向上する可能性がある点です。米国では既に2021年4月にCoinbase(コインベース)社がナスダック上場を果たしており、暗号資産交換業者のIPO第一号となりました。日本でもこれに倣ってビットバンクが上場すれば、「暗号資産企業=未上場のベンチャー」というこれまでのイメージを覆し、一般の株式投資家にも門戸が開かれることになります。業界に対する社会的信用の向上や人材・資本の流入促進などポジティブな波及効果が期待できます。
第二に、市場(株式市場・暗号資産市場の両方)へのインパクトです。ビットバンクIPOが正式に発表されれば、関連銘柄や競合他社の株価にも連想買いの動きが広がるでしょう。例えば米国では2024年末にビットコインETFの承認やトランプ政権の誕生期待を背景にビットコイン価格が急騰し、11月初めから1か月余りで+55%以上上昇して過去最高値10万ドル超えとなりました。この局面でCoinbase株が+60.7%、ロビンフッド株が+66.8%とビットコイン以上に株価が上昇し、市場混乱期でも暗号資産関連株だけが二桁の上昇を遂げたと報じられています。同様に日本でも、ビットバンク上場が具体化すれば「暗号資産関連株ブーム」のような現象が起きる可能性があります。実際、2024年7月の上場準備発表時も、市場では関連企業の株にポジティブな材料と受け止められました。
また国内政策面でも追い風があります。日本政府・自民党は近年「Web3(分散型インターネット)を国家戦略の一つに位置付ける」と表明し、暗号資産やブロックチェーン産業の育成に前向きな姿勢を示しています。2023年度には企業が保有する暗号資産の期末時価評価課税(含み益への課税)を一部撤廃するなど、税制面の整備も進みました。こうした環境下でのビットバンクIPOは「満を持して」の上場と言え、市場全体に与える心理的インパクトは大きいでしょう。暗号資産市場と伝統的金融市場の距離が縮まる象徴的イベントとして、日本の投資家にとっても一つの転換点になる可能性があります。
ミクシィ・セレスなど出資企業への影響とシナジー
ビットバンクの上場観測は、同社に出資している企業にとっても重大な意味を持ちます。現在ビットバンクの大株主は、創業者の廣末社長(約30.7%)に次いで株式会社ミクシィ(26.99%)と株式会社セレス(23.05%)となっています。両社は2021年9月にビットバンクとの資本業務提携を結び、ミクシィが約70億円、セレスが約5億円を出資しました。この出資によりビットバンクは両社の持分法適用関連会社となり、ミクシィとセレスはビットバンク株の将来価値に大きなレバレッジを持つ形となっています。
ビットバンクが順調に上場すれば、ミクシィとセレスには評価益(含み益)が発生します。参考までに、Coincheckを傘下に持つマネックスグループはCoincheckの米国NASDAQ上場により株式の約8割を保有し、その持分評価額は約13億米ドル(約1,950億円)に達すると発表されています。Coincheck株は初値こそ振るわなかったものの終値ベースでは時価総額約17.4億ドル(約2,700億円)を付けました。仮にビットバンクも時価総額2,000億円規模で上場した場合、ミクシィの持分約27%は評価額540億円、セレスの持分約23%は評価額460億円となります。これはミクシィの現在の時価総額(約2,000億~2,600億円台)の2~3割に相当し、セレスに至っては時価総額(約255億円)の約2倍にも匹敵する規模です。もちろん実際の上場時の株価によりますが、少なくとも両社にとってビットバンク株は「隠れた含み資産」であり、上場によってその価値が顕在化する点は見逃せません。
加えて、ビットバンクと出資企業のシナジー(相乗効果)も注目ポイントです。ミクシィはSNS「mixi」や人気ゲーム「モンスターストライク」で知られる東証プライム上場のIT企業ですが、近年はスポーツ事業(プロスポーツチーム経営や配信)やライフスタイル事業など多角化を進めています。暗号資産領域への参入もその一環で、ビットバンクとの提携発表時には「当社(ビットバンク)の最先端の暗号資産技術力と、ミクシィの幅広いユーザーベース・コンテンツ群を組み合わせ、新たな価値創出を図る」と述べられました。具体的な施策として、ミクシィはスポーツNFTマーケットプレイスの開設(2022年発表、ブロックチェーン「FLOW」活用)や、暗号資産を活用した新サービス検討などを進めています。ビットバンク上場で得た資金や信用力を背景に、ミクシィが自社サービス内で暗号資産決済・NFT取引を導入する、あるいはユーザー向けキャンペーンでビットコインを配布するといったコラボも将来考えられるでしょう。エンタメ×クリプトの新展開により、ミクシィ自体の企業価値向上にもつながる可能性があります。
一方のセレスは、ポイントサイト「Moppy(モッピー)」等を運営する企業で、フィンテック・暗号資産分野への積極投資で知られます。ビットバンクへの早期投資もその戦略の一環です。セレスは自社事業として、モッピーで貯めたポイントをビットコインなど暗号資産に交換できるサービスを提供しており、提携先のビットバンクが交換インフラを担っています(※モッピー経由でビットバンク口座開設すると特典がもらえるキャンペーン等も実施)。またセレスは日本企業で初めて株主優待に暗号資産を採用したことでも話題になりました。100株以上保有の株主に対し、ビットコインやリップル(XRP)などを贈呈する優待制度を2021年に導入し、株主からも好評を得ています。このように自社サービス・株主施策に暗号資産を取り入れる先進企業であるセレスにとって、ビットバンク上場は出資リターンだけでなく提携関係強化の追い風となるでしょう。評価益が財務に計上されれば配当や事業投資余力が増し、さらなるフィンテック分野の展開も期待できます。
株価面では、両社とも暗号資産市況に連動した値動きを示す場面があります。セレス株は2022年の暗号資産冬の時代に一時年初来安値1,100円台まで沈みましたが、その後ビットコイン反発局面の2023年末には3,800円台の高値(直近52週高値3,852円)まで急騰しました。直近は2,000円前後で推移していますが、依然として1年で株価3倍超と乱高下しています。ミクシィ株は時価総額が大きい分値動きはマイルドですが、ここ数年は主力ゲームの成長鈍化で低迷していた株価が、ビットバンク出資以降は底堅く推移し、2023年~2024年にかけて3,000円台を回復しています(2023年初は2,000円台前半→2024年末に3,500円近辺)。ビットバンク上場となれば両社株には「含み益銘柄」として改めて脚光が当たる可能性が高く、業績・ニュースと合わせて注意深くウォッチしておきたいところです。
その他の仮想通貨・Web3・フィンテック関連注目銘柄
ビットバンク上場観測をきっかけに、暗号資産やWeb3分野に関連する他の日本株にも関心が集まっています。以下、主要な注目銘柄とそれぞれの暗号資産分野での取り組みを概観します。
SBIホールディングス(8473)
日本の金融サービス大手で、暗号資産業界でも先駆者的存在です。子会社を通じて暗号資産取引所「SBI VCトレード」を運営し、交換・販売・貸暗号資産サービスを提供しています。さらに2022~2023年にかけてはビットバンクの競合であったBITPoint(ビットポイントジャパン)を買収し100%子会社化しました。SBIグループ全体の暗号資産口座数はBITPoint統合により約95万口座、預り残高3,000億円超と国内最大級に達しています。
またSBIはマイニング事業(テキサス州などでのBTCマイニング)や、セキュリティトークンの発行プラットフォーム、海外取引所・マーケットメイカー(英国B2C2社)への出資など、多方面で暗号資産ビジネスを展開しています。制度改革にも積極的で、国内初の暗号資産ETF実現に向けた提言活動も行っており、まさに業界をリードする存在です。
株価は本業の証券・銀行事業の影響も受けますが、2024年前半にはビットコイン上昇に連動して年初安値3,137円→7月高値4,254円まで大幅上昇し、その後調整を挟みつつ再び年末にかけて高値圏(4,100円台)で推移しました。暗号資産へのエクスポージャーが高いため「ビットコイン連動株」として物色されやすく、米国規制緩和など外部要因でも連想買いが入る傾向があります。
マネックスグループ(8698)
オンライン証券大手ですが、2018年にCoincheckを買収して以来、暗号資産事業がグループの重要な柱となっています。傘下のCoincheck(コインチェック)は国内有数の取引所で、アプリダウンロード数累計700万・口座数約220万とユーザー基盤が最大級です。Coincheckでは販売所サービスのほか、NFTマーケットやIEO(トークン新規公開)事業、電気・ガス料金支払いでビットコインが貯まる独自サービスなども手掛けています。
マネックスはこのCoincheck事業価値を引き出すため、2023年~2024年にCoincheck Groupを米ナスダック市場に上場させる(SPACとの合併によるDe-SPAC上場)プロジェクトを推進しました。そして現地2024年12月11日、ついにCoincheck Group, N.V.(ティッカー:CNCK)の上場が実現し、日本の暗号資産交換業者として初の海外上場ケースとなりました。上場後、Coincheck株は合併SPACの終値を約9%上回る堅調な滑り出しとなり、それを受けて翌12日の東京市場でマネックス株も一時9%近く急騰しています。
マネックスはCoincheck株の約8割(1億9百万株)を引き続き保有し、持分評価額は約16億ドル(約2,400億円、1ドル150円換算)にのぼるとされています。この含み益の一部は特別配当(2024年度末に10円/株の記念配当)として還元される予定で、親会社株主にも恩恵が及ぶ見通しです。マネックスの株価は、Coincheck買収時の2018年にも急騰劇がありましたが、その後低迷。しかしCoincheck上場計画が具体化した2023年後半から再評価が進み、2024年末には約17年ぶりの高値圏に達したとも報じられています。
暗号資産事業の成長期待とともに、従来の証券ビジネス(米国子会社トレードステーションなど)の動向も絡むため値動きは複合的ですが、引き続き「国内版コインベース」的な存在として注目の銘柄です。
GMOインターネットグループ(9449)
インターネットインフラ・決済事業で有名なGMOも、暗号資産分野では古参プレイヤーです。2017年より「GMOコイン」という取引所/販売所サービスを開始し、ビットコインや主要アルトコインの売買、FX取引(レバレッジ取引)を提供しています。特色は銀行振込だけでなく同社のネット銀行・決済サービスと連携したスムーズな入出金や、FXノウハウを活かした高機能な取引ツールです。
また2018年には自社でマイニング事業にも乗り出し、北欧などでマイニングセンターを運営するとともに、世界初の7nmマイニングチップ搭載マシンを開発・販売するなど技術開発にも挑戦しました(※現在はマイニング機材開発は撤退)。さらに、米国で日本円連動型ステーブルコイン「GYEN」を発行するなどブロックチェーン活用も進めています(GYENは規制対応のため一時発行停止を経て再開)。
GMOインターネットはグループ全体で金融サービスを展開しており、暗号資産もその延長線上に位置付けています。株価は同社の主要収益源であるドメイン・ホスティングや決済事業の業績に影響されますが、暗号資産市場好調な時期には関連収益(マイニング収入や取引手数料収入)の増加期待から材料視される傾向があります。暗号資産価格の上昇局面ではGMOコインの利用者・取引高も増えるため、ビットコイン高騰=GMO利益増要因として意識される銘柄です。
リミックスポイント(3825)
異色の存在と言えるのがリミックスポイントです。元々は電力事業や中古車販売支援などを手掛ける中小企業でしたが、2017年に暗号資産交換業「BITPoint」を立ち上げ、一躍関連株として脚光を浴びました。BITPointは一時、他社に先駆けて店舗決済に暗号資産を使えるサービスを提供したり、アルトコイン上場に積極的に取り組むなど意欲的でしたが、2019年にハッキング被害に遭い経営が揺らぎます。
その後、2022年にSBIホールディングスとの包括提携を発表し、BITPoint株の51%をSBIに譲渡、さらに2023年3月までに残り49%も売却しBITPoint事業を完全にSBIに譲り渡しました。この売却によりリミックスポイント本体は莫大な現金を得たと同時に、主力事業を手放す形になりました。しかし提携契約には業績連動のアーンアウト(収益分配)条項が含まれており、一定期間BITPointの利益が規定額を超えた場合はその一部がリミックスポイントに還元される仕組みになっています。つまり、完全売却後も間接的にBITPoint事業の成功にコミットしているのです。
現在リミックスポイントは、新たな収益源として暗号資産そのものへの投資を積極化しています。2023年から段階的にビットコインやアルトコインの自社購入を進め、2024年11月時点で総額35億円を投じてビットコイン約248.8 BTC、イーサリアム約227.9 ETH、ソラナ9,674 SOL、アバランチ11,876 AVAX、ドージコイン82.85万DOGE、リップル29.53万XRPを保有するに至りました。取得総額35億円に対し評価額は約43.6億円となっており、約8.6億円の含み益が出ていることも開示されています。
このように実質的に「自社を暗号資産ファンド化」しており、まさに米MicroStrategy社を彷彿とさせる戦略です。またSBIとはメタバースファンドを共同組成し、ブロックチェーンゲーム・メタバース関連企業への投資も行うなど、Web3領域のベンチャー支援にも乗り出しています。
株式市場では、BITPoint売却発表時にリミックスポイント株が急騰し、その後売却完了時には材料出尽くしで急落するという乱高下がありました。しかし最近では同社の暗号資産保有額=会社の価値と見る向きも増え、ビットコイン価格に連動した値動きが顕著になりつつあります。企業というより暗号資産投資信託に近い存在である点を踏まえ、ビットバンク上場時にも間接的な波及を受ける可能性があります(市場全体の盛り上がりによる暗号資産価格上昇など)。
メルカリ(4385)
フリマアプリ最大手のメルカリもフィンテック領域で暗号資産に関わっています。メルカリはキャッシュレス決済「メルペイ」を展開するなど金融サービスに注力しており、その一環で子会社メルコインを通じ暗号資産サービスを提供しています。
2022年よりメルカリのアプリ上でビットコインの現物取引サービス(少額からの購入に対応)を開始し、特徴として最小1円からの取引や、メルカリで得た売上金・メルペイ残高で直接暗号資産を購入可能としました。不用品販売で得たお金をそのままビットコイン投資に回せる手軽さが受け、2023年度の国内暗号資産口座新規開設数で業界トップになるなど、初心者層の取り込みに成功しています。このように既存プラットフォームと暗号資産のシームレスな融合を実現した点で、メルカリは日本版「PayPal+暗号資産」のような独自ポジションを築きつつあります。
株価面では、メルカリは上場直後の高成長期待から一転、最近は業績伸び悩みや投資フェーズ長期化で調整局面が続き、2024年初には直近安値1,631円まで下落しました(上場来高値は7,000円超)。ただし暗号資産事業はまだ収益貢献こそ限定的なものの、巨大ユーザー基盤×暗号資産という潜在力は大きく、暗号資産市場の追い風次第では見直される可能性があります。例えば2025年以降、ビットコインETF解禁などで個人の関心が高まれば、「メルカリでビットコイン投資」という流れがさらに広がり同社のフィンテック戦略強化につながることも考えられます。
三井住友トラストグループ(8309)
メガバンク系列ではありませんが、信託銀行最大手として資産管理ビジネスに強みを持つ三井住友トラスト(SMTH)も暗号資産・デジタルアセットに取り組んでいます。同社はビットバンクが設立した日本デジタルアセットトラスト準備会社(JADAT)に出資しており、分散型台帳技術を活用した次世代デジタル信託の構想を検討しています。具体的には、暗号資産やNFT、不動産ST(セキュリティトークン)などのデジタル資産を信託銀行の仕組みで預かり、安全に管理・継承できるサービスの開発を目指しています。
2022年には三菱UFJ信託と日本取引所グループが「デジタル資産マネー信託」構想を発表するなど、信託銀行業界全体でデジタル証券や暗号資産カストディへの関心が高まっています。三井住友トラストHDはそうした流れの中で先行投資を行っている金融株として位置付けられます。実際、2024年には同行がビットバンクと組むニュースもあってか株価も年初2,694円から夏に3,937円まで上昇し、その後も高値圏でもみ合う展開でした。
銀行株は利上げ局面の恩恵もありましたが、「デジタル資産関連ビジネスへの期待」も追い風となったと考えられます。保守的な金融機関までもが暗号資産インフラに参画している例として、投資家にとって押さえておきたい銘柄です。
gumi(3903)
ゲーム開発の中堅企業ですが、ここ数年で暗号資産・ブロックチェーン領域への大胆な舵切りを行っています。AR/VRやブロックチェーンゲームにいち早く参入し、2022年にはSBIと資本業務提携、さらにSquare EnixなどとともにWeb3ファンドを組成しました。
gumiグループはブロックチェーンゲームの開発・NFT発行を進めており、SBIホールディングスもその動きを支援しています。例えば、gumi子会社が開発するゲーム内トークンをSBI系取引所であるBITPointに上場させるなどの協業が計画されています。
投資面では、gumiは米国のOpenSea(NFTマーケット大手)に出資したり、人気ゲームIPを用いたNFTプロジェクトを立ち上げたりとグローバルなWeb3ビジネスにも関与しています。業績は開発投資先行で赤字が続いていますが、同社株は国内有数の「純粋Web3関連株」として個人投資家から注目され、材料が出る度に大きく動く傾向があります。
今後ビットバンクIPOで業界全体が活気づけば、間接的にこうしたWeb3銘柄にもテーマ買いが波及する可能性があります。
スクウェア・エニックス(9684)
こちらもWeb3絡みで補足します。世界的ゲーム企業のスクエニは2022年頃からブロックチェーンゲーム・NFTに意欲を示し、自社IPを用いたNFTデジタルコレクションやブロックチェーンゲーム(SYMBIOGENESISなど)の開発計画を明らかにしました。2023年には海外のWeb3ゲーム企業に出資するなど準備を進めています。従来の大手コンテンツ企業がWeb3技術に本腰を入れ始めたことは、市場全体の追い風となり得ます。
スクエニ株自体は業績要因で動く部分が大きいですが、同社社長が「ブロックチェーンゲームが今後の柱」と発言した際には株価が反応したこともあり、伝統的企業のWeb3参入という観点で中長期的な注目テーマです。
上記のように、日本株の中には暗号資産そのものから周辺インフラ・サービス、さらにはWeb3領域まで、多彩な形で関与する企業が存在します。それぞれ事業モデルや規模感が異なるため、一括りにせず個別に分析することが重要です。次章では、これら注目銘柄の株価動向・チャート傾向をもう少し詳しく見てみましょう。
注目銘柄の株価動向とチャート傾向
暗号資産関連株は総じて基礎となるビットコイン価格以上にボラティリティ(変動幅)が大きい傾向があります。これは事業のレバレッジ効果や市場のテーマ性によるもので、上昇局面では本家ビットコインより急騰し、下落局面ではビットコイン以上に急落するケースが少なくありません。
例えば2024年末のビットコイン急騰期、米国ではビットコインが1か月で+56%の上昇を記録したのに対し、関連株のロビンフッドは+66.8%、コインベースは+60.7%上昇しました。日本株でも類似の現象が見られ、Coincheck上場が実現した2024年12月にはマネックスGが一時+9%高と急騰し年初来高値を更新しました。一方、2022年~2023年前半の暗号資産低迷期には、多くの関連株が長期の調整局面に入り、年初来マイナス圏に沈んでいたと指摘されています。つまり、暗号資産関連株のチャートは「上げはより強く、下げもより急」というハイベータ(高感応度)の動きになりやすいのです。
個別に見ると、SBIホールディングスは暗号資産市場が活況だった2021年や2024年に株価上昇基調となりました。2024年は先述の通り1月安値≈3,100円→7月高値≈4,250円(+35%超)と大幅高となった後、ビットコイン調整と歩調を合わせるように8月にかけて反落しましたが、その後再度持ち直し年末には4,100円台まで回復しました。チャート上はボラティリティはあるものの高値と安値を切り上げるアップトレンドを維持しています。出来高も増加傾向で、ビットバンクIPOが現実味を帯びれば金融株としての側面も注目され一段高も期待できる位置にあります。
マネックスグループのチャートはさらに劇的です。Coincheck買収発表時の2018年には短期急騰、その後停滞しましたが、Coincheck上場接近報道(2023年秋)から急激に出来高が増え、株価も急伸。2024年12月上場実現直前には約17年ぶりの高値水準に達したとの分析もあります。上場当日は窓を開けて寄付き大幅高となった後、利益確定売りでやや伸び悩む場面もありました。典型的な「材料出尽くし」の動きですが、長期トレンドとしては依然上向きであり、Coincheck株の価値向上や新たなWeb3戦略(例:マネックスは今後NFT事業なども計画中)次第ではさらなる高値追いも視野に入ります。
セレスは小型株らしく急峻なチャートです。2023年は年初1,000円前後から年末にかけて3,000円台後半まで駆け上がり、52週高値3,852円/安値1,112円という激しい値幅を記録しました。出来高もビットコイン価格に連動して増減しており、特にビットバンク上場準備発表(2024年7月)前後やビットコインが10万ドル目前となった2024年末に盛り上がりを見せました。直近は2,000円前後で落ち着いていますが、再び仕掛け的な動きが入ると株価倍増も起こり得るボラティルな銘柄です。テクニカル的には、一目均衡表や移動平均線などでトレンド転換を確認しつつ、出来高急増のタイミングを捉えることが重要でしょう。
リミックスポイントはBITPoint売却を機に事業内容が大きく変わったため、チャート分析も難しい側面があります。売却発表時の2022年5月には株価が一時急騰(前日比+21%ストップ高など)、その後SBIへの最終譲渡完了時(2023年春)には材料消化で下落しました。しかし2024年に入り、同社の暗号資産大量購入が明らかになるにつれ、実質ビットコインETFのような値動きに近づいています。2024年11月のビットコイン最高値更新時にはリミックスポイント株も年初来高値を付け、出来高も増えました。足元ではビットコイン価格と時価総額(保有暗号資産評価額+α)が意識されているため、チャート分析というより暗号資産市場の分析がそのまま株価分析になるユニークなケースです。逆に言えば、ビットバンクIPOでマーケット全体が盛り上がるなら、リミックスポイント株も恩恵を受けやすいとも言えます。
メルカリは暗号資産関連部分がまだ小さいため、チャートへの直接影響は限定的です。ここ1年ほどは1,600~2,800円のレンジで推移し、暗号資産ニュースだけで大きく動くことはありませんでした。ただ2023年末~2024年初にかけての下落(2,700円台→1,600円台)には、市場全体の成長株売りに加えビットコイン調整による投資家心理悪化も多少影響していたようです。今後、暗号資産事業の収益貢献が具体化してくれば材料視されやすくなるでしょう。テクニカル的には長期下降トレンドからの反転を試みており、暗号資産というより本業の回復期待と相まって底打ち反転のチャートパターン(Wボトム形成など)に注目です。
全体として、暗号資産関連株を見る際はビットコイン価格との連動性に加え、個別企業のファンダメンタルとイベント時期を考慮する必要があります。今回のビットバンクIPO観測のように明確な材料がある場合、それに向けた期待上げが事前に起こり、発表直後に短期ピークをつける可能性もあります(いわゆる「噂で買って事実で売る」)。したがって、チャート上でも材料織り込み済みか否かの見極めが重要です。逆に、まだ材料が十分伝わっておらず割安に放置されている銘柄は先回り買いの好機となり得ます。暗号資産関連株はボラティリティが高い分、テクニカル分析とニュース分析を組み合わせた戦略が有効でしょう。
仮想通貨市場の見通しと関連株投資のポイント
最後に、暗号資産市場全体の展望と、関連株に投資する上での留意点を整理します。
暗号資産市場の今後の見通しとしては、中長期的には明るい材料が揃いつつあります。2024年には米国でブラックロックなど大手金融機関によるビットコイン現物ETFの上場がついに実現し、これによって一般投資家も間接的にビットコインに投資できる環境が整いました。また2024年末の米大統領選で誕生したトランプ政権は暗号資産に推進的とされ、規制緩和への期待も高まっています。こうした動きを追い風にビットコインは過去最高値を更新し、2025年に入っても高値圏を維持しています。
日本においても前述のように政府のWeb3推進方針や税制改正などエコシステム整備が進み、メガバンクや大手企業の参入も相次いでいます。加えて、2024年4月にはビットコインの4度目の半減期(マイニング報酬半減)があり、新規供給の減少による需給好転も見込まれます。歴史的に半減期後1~2年で強気相場になるパターンが繰り返されてきたこともあり、マーケット参加者の多くが2025年前後の暗号資産市場に期待を寄せています。
もっとも、短期的な変動リスクや不透明要因も無視はできません。規制リスクは依然存在し、各国当局の方針ひとつで市場心理が急変する可能性があります。また暗号資産自体のボラティリティは高く、投機的な過熱感が出た際には調整も避けられません。したがって関連株への投資にあたっては、暗号資産市場の先行きを楽観視しすぎず適切なリスク管理を行うことが肝要です。
関連株投資で注目すべきポイントをいくつか挙げます。
- ビットコイン価格動向のチェック:繰り返しになりますが、関連株はビットコイン価格と高い相関関係があります。ビットコインが節目の価格(例えば日本円換算で史上最高値更新など)を超える局面では関連株にも資金が集まりやすいです。一方、大幅下落局面では真っ先に売られる可能性があるため、暗号資産市場全体のトレンド把握は必須です。株式側から先行指標的に動くこともあるため、出来高推移や先物市場の動向も参考にしましょう。
- 規制・政策ニュース:国内外の規制変更や政策発表にも敏感になる必要があります。良い例が税制改正による期末評価課税の撤廃で、これにより日本企業が自社でトークン発行・保有しやすくなりました。ETF承認、中央銀行デジタル通貨(CBDC)の進展、海外での上場事例(今回のビットバンクIPOやCoincheck米国上場など)も大きな材料です。こうしたニュースは関連株のバリュエーション見直しにつながります。常に最新の政策動向をウォッチし、「次に恩恵を受ける銘柄はどこか?」とアンテナを張ることが求められます。
- 個別企業の戦略と業績:暗号資産関連といっても企業ごとにビジネスモデルや財務状況は様々です。例えばSBIやGMOのように本業がしっかり利益を出しており配当もある企業と、セレスやリミックスポイントのように暗号資産関連事業が収益の柱だが業績変動が大きい企業では投資妙味も異なります。前者は比較的ディフェンシブに構えつつ暗号資産の成長を取り込めますが、後者はハイリスク・ハイリターンです。自分のリスク許容度に応じ、個別企業の決算内容や財務体質も精査しましょう。ビットバンクIPOに直接絡むミクシィ・セレスなどは今後**持ち分株の含み益をどう扱うか(売却益計上や配当還元の可能性)**といった点も注目です。
- イベントスケジュール:投資タイミングを測る上で、ビットバンクIPOの正式発表時期や他の関連イベントの日程を把握しておくことも重要です。仮に「2025年◯月◯日に上場承認・◯月◯日に上場」という情報が出れば、その前後で需給が大きく動くでしょう。またCoincheck株の動向(NASDAQ上場後の業績発表など)や、国内初の暗号資産ETF申請動き、主要アルトコインの技術アップデート(例えばイーサリアムの大型アップグレード)なども、市場テーマとして関連株に飛び火する可能性があります。イベントドリブンの観点でカレンダーをチェックし、「噂で仕込んで事実で適宜利確」の機動力も求められます。
- 分散投資とポートフォリオ管理:暗号資産関連株は魅力的な成長分野ですが、値動きの荒さゆえに単一銘柄への集中投資はリスクが高いです。可能であれば複数銘柄に分散し、同じ関連株でも性質の異なる組み合わせ(例えば大型安定株のSBIと小型成長株のセレスを組み合わせる等)でポートフォリオを組むと、値動きの凹凸を平均化できます。また、ある程度利が乗った場合には一部利確して現金比率を高めるなど、利益確定と損切りのルールを決めておくことも大切です。ボラティリティを敵ではなく味方につける心構えで臨みましょう。
まとめとして、ビットバンクのIPOは日本の暗号資産業界における歴史的転換点となり得るイベントです。これを軸に関連銘柄を見渡すと、直接恩恵を受ける出資企業から、大手金融・IT企業、さらには新興のWeb3企業まで、多彩な投資機会が浮かび上がります。暗号資産市場自体が依然変動的であることを忘れず、十分な情報収集と分析に基づいて慎重かつ大胆に投資判断を行うことが肝要です。伝統金融と暗号資産の融合が進む中、ビットバンク上場の行方とその周辺の動きから目が離せません。新たなフェーズに突入したこの市場で、チャンスを的確に捉えられるよう、引き続き動向を注視していきましょう。