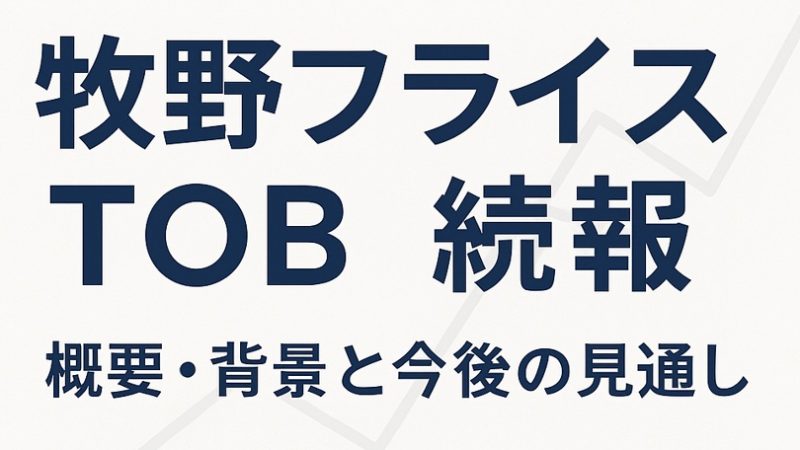
2025年6月3日、アジア系の大手投資ファンドであるMBKパートナーズ傘下の企業が、工作機械メーカー牧野フライス製作所の全株式を取得することを目的にTOB(株式公開買付け)を実施すると発表しました。買付価格は1株あたり11,751円に設定されており、牧野フライスの取締役会はこの提案に賛同し、株主に対して本TOBへの応募を推奨すると表明しています。この価格は前年末に提示されていた他社(ニデック)による案の1株11,000円を上回っており、経営陣は本提案が企業価値向上につながると判断しました。
今回は前回の「【TOB事例】ニデックによる牧野フライスへの敵対的TOB攻防の全容と背景分析」の続報として当TOBの概要を見ていきたいと思います。
概要解説 – 誰が、なぜ、どのような条件でTOBを実施?
誰がTOBを行うのか?
買収者はMMホールディングス合同会社という特別目的会社で、投資ファンドMBKパートナーズが運営しています。MBKパートナーズは日本やアジアで多数の企業買収実績を持つプライベートエクイティファンドで、日本国内ではコメダ珈琲店や黒田電気などへの投資で知られています。また、過去には韓国の大手機械メーカー(斗山工作機械=現DN Solutions)に投資した経験もあり、製造業の経営にも精通しています。
牧野フライス経営陣は「MBKは当社の理念を理解している」と評価しており、今回の提案は友好的な買収として位置付けられています(すなわち経営陣の合意の下で行われる買収)。
なぜTOBが行われるのか?
背景には、牧野フライスの企業価値を向上させ、中長期的な成長戦略を実現する目的があります。牧野フライスは高い精度の工作機械で世界的に評価されていますが、近年の株式市場では株価が割安水準にあるとの指摘もありました。投資ファンドによる非公開化(上場廃止)は、四半期ごとの業績に左右されず長期視点で事業改革や投資を行う環境を整える狙いがあります。
また、ニデックによる敵対的買収の試みが引き金となり、経営陣は株主価値を最大化する選択肢を模索してきました。MBKパートナーズの提示した条件は価格面で魅力的であるうえ、同ファンドが牧野フライスの経営方針を尊重する姿勢を示したことから、経営陣および特別委員会は本TOBを受け入れる判断を下しました。
どのような条件で行われるのか?
本TOBでは牧野フライス株式を完全子会社化(全株取得)することを目的としており、買付予定株数に下限が設定されています。成立には発行済株式数の3分の2以上の応募(約1,559万株以上)が必要です。これは、TOB成立後に残りの株主を整理するための手続(スクイーズアウト)として株式併合などを行う際に、株主総会での特別決議(議決権の3分の2以上の賛成)が必要となるため、その要件を満たすことを目的としています。
買付予定数の上限は設定されておらず、応募があれば可能な限り全株を取得する方針です。TOBが成立した場合、牧野フライス株式は上場廃止(非公開化)となる見通しで、買収者(MBK側)が牧野フライスを100%保有する体制に移行します。
背景と経緯 – ニデック提案から始まった買収劇
今回のTOBに至るまでの背景には、ニデック株式会社(Nidec)による買収提案が大きく関係しています。ニデックはモータ製造大手であり、工作機械分野への事業拡大を図る戦略の一環として、2024年12月に牧野フライスに対し事前協議なしでTOBによる買収(完全子会社化)を提案しました。提示価格は1株あたり11,000円で、経営陣の同意が得られなくても計画通り進める意向を示し、事実上の敵対的買収の姿勢を明らかにしました。この発表を受けて市場は敏感に反応し、報道当時牧野フライスの株価は一時12,530円まで急騰する場面もありました(買収競争への期待感からの上昇)。
ニデックの提案に対し、牧野フライス側は慎重な対応を取りました。経営陣は第三者による別の提案も模索し始め、企業価値を最大化するため最良の選択肢を探す方針を明確にします。2025年3月10日には、「複数の第三者から当社を完全子会社化する旨の初期的意向表明書を受領した」と開示し、他の買収候補の存在を公表しました。事情に詳しい関係者の情報として、その候補にはMBKパートナーズのほか、日本産業推進機構(NSSK)など複数の投資ファンドが含まれていたことが報じられています。これは牧野フライスに対する買収が争奪戦に発展する可能性を示唆する出来事でした。
牧野フライスはニデックに対し、他の提案との比較検討のため時間を確保するよう要請しました。具体的には、TOB開始予定日を当初計画の2025年4月4日から少なくとも5月9日まで延期し、さらにTOB成立条件として応募下限を発行済株式の3分の2以上に引き上げることを求めた文書を送付しています。これは、他の提案者と交渉する猶予を得るとともに、万一ニデックが買収に成功しても過半数程度ではなく特別決議が可能な2/3以上の株式取得を条件とすることで、安易な買収成立を防ぐ狙いがありました。
しかし、ニデックはこの要請に必ずしも応じず、2025年4月4日に予定通りTOBを強行開始します。このため牧野フライスは直ちに買収防衛策を発動しました。3月19日に予告していたとおり、「時間確保措置」として新株予約権(ワラント)を既存株主に無償割当てする決議を4月10日に全会一致で承認し、実行に移す準備を行ったのです。これはいわゆるポイズンピルと呼ばれる対抗措置で、新株予約権を行使して大量の新株を発行できる状態を作ることで、買収者(ニデック)の持株比率を希薄化させ買収コストを高騰させる効果があります。牧野フライスはこの措置により時間を稼ぎつつ、特別委員会の助言のもとで他の提案者との交渉を並行して進めました。
こうした強硬な対抗策を受けて、ニデック側は買収断念に追い込まれます。2025年5月8日, ニデックは牧野フライスに対するTOBを撤回すると表明しました。翌5月9日付で牧野フライスは「ニデックによる公開買付けの撤回及び新株予約権無償割当ての中止」を発表し、発動寸前だった買収防衛策を停止しています。結果としてニデックによる敵対的買収は未遂に終わり、牧野フライス経営陣は当初の目的どおり買収提案の比較検討に十分な時間を確保することに成功しました。
ニデック撤退後、浮上したのがMBKパートナーズによる買収提案です。牧野フライスは5月27日付の適時開示で、MBKパートナーズから法的拘束力のある買収提案を受領し、早期に最終合意に向け交渉を進める方針であることを発表しました。この提案は条件面でニデック案を上回り(価格引き上げなど)、経営陣にとっても友好的な内容であったため、特別委員会での検討を経て受け入れが決定されたとみられます。こうして6月3日にMBKによるTOB計画が正式に公表され、牧野フライスはその買収案に賛同の意を表明するに至りました。
今回のTOBの特徴 – 価格・非公開化・買収後の方針・資金調達・スケジュール
今回のMBKパートナーズによるTOBには、一般投資家にとって押さえておきたい特徴やポイントがいくつかあります。以下に主な点をまとめます。
- 買付価格とプレミアム: 買付価格は1株あたり11,751円に設定されています。これは前述のニデック提案(11,000円)を約7%上回る水準であり、過去の牧野フライス株価(ニデック提案前)と比べても大きなプレミアム(上乗せ幅)となっています。例えば、2024年12月の提案公表前の株価水準から見ると2割以上の上昇幅になるとの指摘もあり、株主にとって魅力的なオファーといえます(実際、TOB合意発表後の株価はこの水準近辺で推移しています)。
- 非公開化(上場廃止)と完全子会社化: 本TOBは牧野フライスを完全子会社化し非公開化することが目的です。TOB成立後、MBK側は牧野フライス株式の議決権を2/3以上取得する予定で、残存株主に対しては株式併合などの手法で強制的に株式を買い上げる「スクイーズアウト手続」を実施する計画です。これにより最終的に牧野フライスはMBKの100%子会社となり、東京証券取引所プライム市場から上場廃止となる見込みです。非公開化後も牧野フライスの社名や事業は存続する見通しですが、株主はMBKのみになるため一般投資家は株式市場で同社株を取引できなくなります。
- 経営維持と買収後の方針: MBKパートナーズは牧野フライスの現経営陣と事前協議の上でTOBを提案しており、経営陣の続投や事業方針の維持が図られるとみられます。牧野フライス側も「当社の理念を理解したパートナー」としてMBKを評価しており、強引なリストラや短期的利益のみを追求する経営方針転換は避ける意向です。むしろ非公開化によって中長期的な研究開発投資やグローバル戦略を推進し、企業価値を高めることを目指すと考えられます。また、MBKは過去に製造業への投資・経営支援実績(前述の韓国の工作機械メーカーなど)があるため、そのノウハウを活かし牧野フライスの国際競争力強化を支援すると予想されます。
- 買収資金の調達状況: 買収に必要な資金は約3,000億円規模にのぼると見込まれますが、資金調達の手当は既に完了しています。具体的には、MBKパートナーズのファンド(MBK Partners Fund VI, L.P.)から約1,610億円の出資を受け、さらに三菱UFJ銀行、みずほ銀行、横浜銀行、あおぞら銀行といった金融機関からシニアローン(融資)として最大約1,299.8億円、みずほ銀行系列のMCPを含むメザニンローンとして約129.98億円の借入れコミットメントを取得しています。これらの融資枠とファンド出資金により買付代金は賄われる計画であり、金融面の不安要素はないとされています。「必要となる決済資金の準備も完了しております」との発表がある通り、資金面でTOB実行に支障はない見込みです。
- 今後のスケジュール: 現時点でTOBの開始時期は2025年12月上旬頃と案内されています。これは国内外の関係当局で必要な手続きを完了させるための期間を見込んだもので、正式な開始日程は今後確定次第公表される予定です。その後、条件である株式数2/3以上の応募が得られればTOBは成立となり、MBKは速やかに残余株主の排除手続(株式併合など)を進めます。上場廃止については、TOB成立後に所定の手続きを経て2026年初頭(2〜3月頃まで)に実施される可能性があります。なお、監理銘柄の指定など上場廃止に向けた準備措置については東京証券取引所から別途アナウンスが行われるでしょう。
今後の見通し – TOB成立の可能性、株主への影響、株価動向
TOB成立の可能性
今回のMBKパートナーズによるTOBは、経営陣が賛同を表明している友好的買収であり、成立する可能性は極めて高いと考えられます。応募下限が2/3と高めに設定されていますが、既に牧野フライスの取締役会自ら株主に応募を推奨しており、機関投資家や大株主もこれに追随する公算が大きいでしょう。事前にMBK側と大株主との間で応募合意がなされている可能性もあります(一般的に友好的TOBでは主要株主から応募確約を取り付けるケースが多いです)。
ライバルであったニデックは既に撤退しており、対抗の買収提案が再浮上する可能性は低いとみられます。仮に別の第三者が更に高い価格を提示して競りかけるシナリオも考えられなくはありませんが、経営陣の支持を失った敵対的提案は実現可能性が乏しく、MBK提案を覆すほどの動きは出ないでしょう。
株主にとっての影響
牧野フライスの既存株主にとって、本TOBは株式を現金化する好機となります。提示価格11,751円には十分なプレミアムが乗っており、ニデック提案時からの株価上昇分を含めて大きな含み益を得ている投資家も多いはずです。TOBに応募すれば、原則として保有全株をこの価格で売却できます。応募せず残った場合でも、TOB成立後に実施される株式併合等で最終的には同程度の価格で強制的に買取られる見通しです。
したがって、牧野フライス株を持つ一般投資家にとっては最終的に現金で精算されることになり、株主としての権利(配当や議決権等)は上場廃止までの間に消滅していきます。今後も会社の成長に投資を続けたいと考えても、非公開企業になるため株式を保有し続ける選択肢は基本的にありません。その意味で、本TOBは株主に確定利益の実現と引き換えに今後の株主としての参画機会を失う出来事といえます。株主は提示価格が妥当か慎重に判断しつつ、応募期限までに売却するか否かを決める必要があります。
株価動向の見通し
TOB発表以降、牧野フライスの株価はTOB価格にサヤ寄せする形でほぼ横ばいの推移を見せると予想されます。一般的に上場企業が買収される場合、株価は提示買付価格近辺で推移しやすくなります。実際、6月初旬の発表直後、牧野フライス株は一時TOB価格付近まで上昇しました。現時点で大きな株価上昇余地や下落リスクは限定的であり、市場参加者はTOBの成立を織り込んでいる状況です。
今後、仮に買収プロセスに遅延や不透明要因(例:規制当局の審査長期化など)が生じれば、一時的に株価がTOB価格を下回る可能性もあります。しかし基本シナリオでは、TOB完了まで株価は安定したレンジに収まり、成立発表後に上場廃止へ向けて取引停止となるでしょう。
なお、一部のアクティビスト(物言う株主)やヘッジファンドが価格引き上げ交渉を促すため応募を渋る可能性も指摘されていますが、経営陣が合意済みの案件であること、そして買収者側も既に十分高いプレミアムを提示していることから、価格再交渉の余地は小さいと考えられます。
総括
今回のTOBは成立する公算が大きく、牧野フライスは約80年の上場企業としての歴史に一区切りをつけ非公開企業へと移行する見込みです。これは近年の日本企業における大型M&Aの一例であり、特に敵対的買収をきっかけに最終的には経営陣公認のMBO的な展開となった点で注目されています。一般投資家にとっては、自社株が買収提案を受けた際にどう対応すべきかを考える契機ともなるでしょう。
牧野フライスのケースでは、防衛策発動や対抗提案の引き出しを経て、最終的により高い提案が株主にもたらされた形となりました。市場原理が働いた結果とも言え、企業価値の適正な評価が再確認される展開となっています。今回提示された11,751円という価格が「適正価格」であるかどうかは、最終的には株主の判断に委ねられます。しかし経営陣が賛同し、現実に買収が完了すれば、その価格がマーケットの答えとなります。今後、牧野フライスが非公開化のもとで更なる成長を遂げ、数年後に再上場などが検討されることになれば、今回の買収劇は投資ファンドと日本製造業のウィンウィンのケーススタディとして語られるかもしれません。