【TOB事例】アセンテックに対するオリックス子会社のTOB解説と中堅IT企業の支援型TOB候補3選
2025.06.16投稿
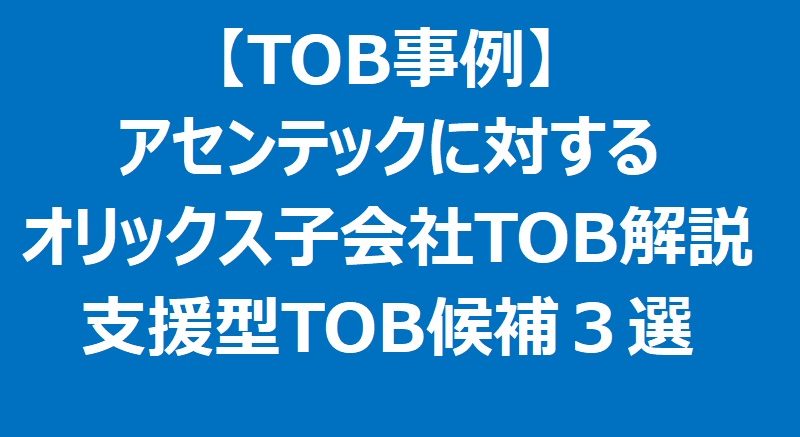
今回は、仮想デスクトップ(VDI)関連事業を手がけるアセンテック株式会社(東証スタンダード・証券コード3565)に対し、オリックスグループの子会社が実施しているTOB(株式公開買付け)について解説します。
オリックスの完全子会社化の狙いから、買付価格の行方、今後の経営方針まで、ポイントを押さえて見ていきましょう。
背景:オリックスがアセンテックを買収する狙いとは?
なぜオリックスグループがアセンテックを完全子会社化しようとしているのか?
その背景には、アセンテックの事業価値とオリックスの戦略的投資方針があります。
アセンテックの事業魅力
アセンテックは仮想デスクトップなど企業のITインフラソリューションを提供する専門企業です。2009年設立で、2017年に東証マザーズ(現スタンダード市場)に上場して以来、仮想デスクトップ環境の構築・機器販売から保守まで一貫サービスを展開してきました。
オリックスは近年、テクノロジー分野への関心を高めており、ITネットワーク関連ビジネスへの投資を積極化しています。アセンテックはその専門性からオリックスにとって将来性のあるデジタル分野の投資先と映ったのでしょう。
オリックスの投資戦略
オリックス本体は金融から実業まで幅広い事業を持つ大手ですが、近年は自社資金で企業に長期投資し、専門性や事業基盤を提供して企業価値向上を支援するビジネスを展開しています。今回も、オリックスは自前の投資子会社OPI・18株式会社を2025年4月に設立し(資本金わずか5万円の買収目的会社です)、この会社を通じてアセンテック株を市場から買い集め完全子会社化する計画です。
目的はアセンテックをグループ内に取り込み、オリックスのリソースで同社の企業価値向上を後押しすることにあります。
友好的なTOB
このTOBは友好的買収として進められています。つまり、アセンテック経営陣も買収に賛同しており、主要株主も協力的です。
具体的には、筆頭株主の永森伸一氏(創業者)が約22.9%、重要取引先である米Cloud Software Group社(Citrix関連会社)が約4.9%の株式を保有していますが、両者合わせて27.8%の株式についてTOBへの応募に合意済みです。
これによりオリックス側は買付け開始前から約3割近い株式取得を確実化しており、買収実現のハードルを下げています。
特徴的なパートナー連携
他のTOBと異なるユニークな点として、Cloud Software Group(CSG)との提携スキームがあります。
CSG社はアセンテックにとって重要な米国企業パートナーですが、今回のTOBでCSGも株式を手放す代わりに、買収後にOPI・18側へ最大5%出資する権利を得ています。つまりCSG社はアセンテックがオリックスの完全子会社になった後も、新会社(OPI・18)の株主として関与を続ける予定です。
このように、主要取引先を巻き込んだ協調的な買収になっている点は特徴的でしょう。
以上のように、オリックスはアセンテックの技術と市場を取り込み、自社グループの力で成長させる狙いでTOBに踏み切ったわけです。次に、その買付け価格の詳細と評価について見てみましょう。
買付け価格の詳細:提示額の交渉と最終プレミアム
TOBの買付価格はいくらで、どのように決まったのでしょうか?
今回の最終的な買付価格は1株あたり1,680円ですf。この価格に至るまでには、オリックス側とアセンテック側との間で綿密な交渉が行われ、当初提案から引き上げられました。以下、その経緯を時系列でまとめます。
初期提案
2025年5月中旬、オリックス(OPI・18)はまず1株1,365円でTOBを提案しました。しかし、この価格は直前の市場株価に対するプレミアム(上乗せ幅)が小さい水準でした。提案当時の終値と比較すると約+4.4%程度で、特別委員会(後述)から「やや低い」との感触だったようです。
価格引き上げの交渉:
アセンテック側は社内に独立役員だけで構成された特別委員会を設置し、買収価格の公正性を慎重に協議しました。この委員会が中心となり、オリックスに対して価格引き上げの要請と交渉を重ねます。
その結果、オリックスは5月末までに段階的な増額提案を行いました。5月27日には1株1,440円(初回提案から+75円)、5月30日には1,540円、6月5日には1,590円という具合に、数日に一度ずつ段階的に提示額を引き上げていきました。
それでも特別委員会は「依然として市場価格や企業価値を十分反映していない」と判断し、更なる上積みを要求しています。
最終合意価格
粘り強い交渉の末、6月10日には1,660円まで提示額が上がり、最終的に6月12日頃にオリックスが提示した1株1,680円で双方合意に至りました。
初回提案の1,365円と比べると約23%の大幅増額となり、特別委員会もこの価格なら株主にとって妥当と判断したわけです。
提示価格に含まれるプレミアム
最終価格1,680円は、TOB公表直前のアセンテック株価に対し約15.7%のプレミアム(上乗せ幅)になります。
さらに、直近1か月間の平均株価(約1,372円)と比べると+22.4%、直近3か月平均(約1,237円)と比べると+35.8%、直近6か月平均(約1,110円)に対しては実に+51.5%高い水準です。
半年スパンで見て株価を半値近く上回る価格が提示されたことになり、アセンテックの少数株主にとっては十分に魅力的な売却プレミアムと言えるでしょう。
以上のように、オリックスは当初提案額から数回の価格引き上げ交渉を経て最終的に1,680円に落ち着きました。この価格についてアセンテック取締役会は「本取引条件は株主にとって妥当であり、十分に合理的な売却機会を提供するもの」と評価しています。特別委員会の助言のもと、少数株主の利益が適切に保護される水準までプレミアムが積み上げられた形です。
TOBの条件:買付期間・応募条件・主要株主の動向
TOBの具体的な条件も押さえておきましょう。買付け期間や成立条件、主要株主の対応などは以下の通りです。
買付け期間は長めに設定
OPI・18による公開買付けの買付期間は34営業日間と発表されています。法律上の最短必要期間(20営業日)よりかなり長めで、約7週間程度の期間です。これは、株主が十分に検討し判断する時間を確保するためとともに、他の第三者が対抗的な買収提案(ホワイトナイトなど)を行う機会も確保するためです。
買付予定株数と条件
オリックス側はアセンテックの発行済株式全て(自己株を除く約1,431.9万株)を取得目標としています。ただし最低成立条件として3分の2以上(66.67%)の株式取得を下限に設定しました。
具体的には954.6万株以上の応募がなければ一切買付けを行わず不成立とし、それ以上集まれば上限なく全株買い取るとしています。66.67%というラインは特別決議要件(株主総会で株式併合などを行うのに必要な割合)に相当し、これを超えればオリックスは残り株主をスクイーズアウト(強制買取)できるため、完全子会社化が確実になります。
主要株主の応募状況
前述の通り、筆頭株主の永森氏(約22.9%)と5位株主のCSG社(約4.9%)はTOBに応募する契約を結んでいます。この合計27.8%分は確実に応募されるため、成立には残り約39%程度の株主の応募が必要です。
アセンテック取締役会はTOBへの賛同と応募推奨を決議していますので、機関投資家や一般株主もそれに従う可能性が高く、成立条件の2/3超えは比較的ハードルが低いとみられます。
今後の見通し:上場廃止とアセンテックの経営方針
TOB成立後、アセンテックのオリックスとのシナジー創出について考えてみたいと思います。
オリックスとのシナジー効果
オリックスはアセンテックを取り込むことで**グループ内での事業シナジー(相乗効果)**を追求すると述べています。具体的には、以下のような協業プランが挙げられています。
ネットワーク構築分野での協業強化
オリックス子会社のHCNET(エイチシーネット)とシステムインテグレーション(SI)業務で協力し、アセンテックの仮想デスクトップ提案にネットワーク構築力をプラス。グループ内連携でより包括的なソリューション提供が可能になります。
技術・設備の共有による効率化
アセンテックが持つ最新機器を揃えた検証ラボやVDI製品開発の知見をHCNETと共有し、両社の開発・検証プロセスを効率化します。お互いの強みを出し合うことで、新サービス開発のスピードアップが期待されます。
販売チャネルの拡大
アセンテック自社開発の「リモートPCアレイ」などVDI関連製品を、全国に拠点と顧客基盤を持つHCNET経由で官公庁・教育・医療・民間企業など幅広い顧客層に販売できるようになります。オリックスグループ内のネットワークを活用することで、今までリーチできなかった市場にもアプローチできるでしょう。
レンタルサービスの充実
オリックスには計測器レンタル大手のオリックス・レンテックという子会社があります。アセンテックはオリックス・レンテックが扱うハイテク機器のレンタルサービスを自社顧客に提案したり、逆に自社製品をレンテックを通じてレンタル提供するといった形でサービスラインナップを拡充できます。これにより、初期導入コストのハードルを下げて仮想デスクトップを提案できるなど、新たなビジネスモデル展開も可能になります。
本TOBから推測される「大手が狙うかもしれない支援型TOB」中堅IT企業3選
オリックス傘下に入った後のアセンテックは、非公開化のメリットを活かして中長期的な事業強化に専念できるはずです。オリックスの豊富な経営資源やネットワークとのシナジー効果により、仮想デスクトップ事業のさらなる拡大や新サービス創出が期待されます。
本件は大企業グループによる中堅IT企業の支援型TOBの好例として、市場動向を知る上で参考になると考えていますが、今後予想される同様な事例として今後支援型TOBが期待される可能性のある中堅IT企業3社をピックアップしました。
業績の安定性や成長性、親和性のある事業領域、そして大企業との既存の取引・資本関係などを総合的に考慮しています。
Appier Group(4180) – AIマーケティングの成長株
Appier Groupは、台湾発の「AIネイティブSaaS企業」であり、AIを活用した広告配信や顧客行動予測プラットフォームを提供しています。マーケティング支援のクラウドサービス(いわゆるAdTech/MarTech領域)で国内外の顧客企業のROI改善を後押ししており、売上は順調に拡大中です。
上場以来まだ赤字決算が続いているもののARR(年次経常収益)は伸びており、AIブームの追い風もあって高い成長性が期待されています。
同社の株主構成を見ると、創業者の持株比率が低く、代わりに海外VCやPEファンドなど外部資本が多くを占めている点が特徴的です。筆頭株主は英領バージン諸島籍の投資会社Plaxie(出資比率約16.8%)、次いで米VCのSequoia Capital India(約9.8%)など、ベンチャーキャピタル勢が名を連ねています。このため将来的な出口戦略として、これらVCが主導する形でTOBによる非公開化(MBO)が検討される可能性があります。
また、株価は上場時の公募価格前後で停滞気味で割安感も指摘されていることから、同社のAI技術や顧客基盤に魅力を感じる他のDX企業や大手IT企業が買収に乗り出す余地も十分にあると見られます。例えばNTTやKDDIなど通信・IT大手にとっては、自社のデジタルマーケティング領域を強化する絶好の機会になるかもしれません。成長力と戦略的価値を併せ持つAppierは、まさに支援型TOBの候補として投資家注目の一社です。
サーバーワークス(4434) – クラウドインテグレーターの有力株
サーバーワークスは、AWS(アマゾンウェブサービス)に特化したクラウドインテグレーション事業の草分け的存在です。
2009年にいち早くAWS専門サービスを開始し、日本企業で初めてAWS公式のマネージドサービスプロバイダー認定を取得するなど、高度なクラウド導入支援ノウハウを築いてきました。現在もAWS導入支援から運用監視まで一貫サービスを提供し、クラウド市場の拡大を追い風に業績は堅調です。
実際、同社の主力であるAWS課金代行売上はクラウド需要の拡大に伴い伸び続けており、導入支援や運用代行サービスも顧客数増加で着実に拡大しています。人件費増など先行投資はあるものの、安定した収益基盤と成長性を両立した企業と言えるでしょう。
戦略的な親和性という点でもサーバーワークスはTOB候補として有望です。同社は2018年にNTTデータおよびNTTコミュニケーションズと資本業務提携を結び、第三者割当増資を引き受けてもらう形で両社が株主に加わっています。NTTグループの狙いは、この提携によって自社のクラウドSI(システム構築)サービス強化とノウハウ共有にありました。
現在NTTデータとNTTコミュはそれぞれ数%程度の株式を保有しており、サーバーワークスはNTTグループの持分法適用関連会社でもあります。こうした深い取引・資本関係を背景に、NTT側がさらなるシナジー獲得を目指して将来的に追加TOBで子会社化する可能性は十分考えられます。
実際、NTTは近年グループ内再編を積極化しており(NTTデータの完全子会社化など)、クラウド分野でも優れた社外パートナーを取り込むことで競争力強化を図る戦略です。仮にNTTが支援型TOBに踏み切れば、サーバーワークスは広範な法人顧客基盤と資金力を持つ親会社の下で更なる成長が期待できるでしょう。
クラウド黎明期から実績を積む業界トップクラスのAWSインテグレーターだけに、今後の動向に要注目です。
あいホールディングス(3076) – 安定収益のセキュリティ機器ベンダー
あいホールディングスは、監視カメラや録画装置などのセキュリティ機器や事務機器の開発・販売を手がける老舗企業です。その製品ラインナップは防犯カメラシステムからカード発行システムまで幅広く、自社グループ内に警備会社や施設管理会社を抱え、セキュリティ関連のサービス事業にも展開しています。
堅実な経営で知られ、売上・利益は大きなブレはないものの安定的に推移しており、高配当傾向もあって財務の安定性は抜群です。近年は成長分野である電子決済やDX関連にも商機を広げつつあり、成熟企業ながらも堅調な事業基盤を維持しています。
同社がTOB候補として注目される理由は、資本構成と外部との関係にあります。
創業家出身の筆頭株主・佐々木氏でも持株比率は20%弱に留まり、経営陣の支配力は相対的に小さい状況です。一方で2023年には米国の投資ファンドであるDalton Investmentsが株式の約5%を取得し大量保有報告を提出するなど、外部資本が入りつつあります。
米PEファンドの新規参入は経営権獲得を睨んだ動きとも見られ、実際Daltonが追加でTOBを仕掛けて非公開化に踏み切る可能性も指摘されています。創業家の持分が少数に留まるため外部勢力による買収余地は大きく、加えて同社の属するセキュリティ・人材系事業分野は業界再編やM&Aでスケールアップを図れる余地があります。
例えば、大手通信や商社があいHDを傘下に収めれば、自社のスマートシティ事業や防犯ソリューションとのシナジーが期待できるでしょう。また同社自身もM&Aによる事業拡大戦略を掲げており、グループ再編の核として大企業が支援に乗り出すシナリオは現実味を帯びています。
安定した収益力と隠れた成長余地を併せ持つあいHDは、今後も投資家が目を離せない一社です。
まとめ
以上、オリックスによるアセンテックへの支援型TOBとあわせて、今後において支援型TOB期待される中堅IT企業3社をご紹介しました。
いずれも業績の安定感と将来の成長ポテンシャルを備え、大企業との親和性や関係性が見込まれる注目株です。昨今の親子上場解消ブームやDX加速の流れも相まって、こうした企業が大手グループの支援を受け入れて飛躍を遂げるケースは増えていくかもしれません。
もっとも、TOBの実施タイミングや実現可否は不確実であり、あくまで可能性に過ぎません。しかし投資家にとって、こうした候補銘柄を押さえておくことは将来のサプライズに備える上で有益でしょう。大手による“次の支援型TOB”の行方にぜひ注目していきたいですね。