【TOB事例】協栄産業TOBの概要・特徴と今後のTOB候補銘柄3選
2025.05.31投稿

半導体商社の再編が加速しています。加賀電子は協栄産業を1株3,950円で公開買付けし、完全子会社化を狙います。この波は割安な同業他社にも及ぶかもしれません。
本記事では今回のTOBの仕組みと狙い、今後可能性のある3社の買収可能性を整理し、個人投資家がプレミアム獲得のチャンスとリスクを見極めるポイントをご紹介します。
協栄産業へのTOB概要
買付価格と目的
2025年5月30日、加賀電子は協栄産業の普通株式を1株あたり3,950円で公開買付け(TOB)すると発表しました。買付予定総額は約87億円規模で、協栄産業を完全子会社化(全株取得)して上場廃止にすることが目的です。協栄産業は三菱電機系のエレクトロニクス商社で、三菱電機が約18%を出資する筆頭株主でした。
今回のTOBで加賀電子は協栄産業株の残りすべてを取得し、三菱電機との資本関係を解消したうえで、自社グループに取り込む狙いです。
背景:
加賀電子は以前から協栄産業株を市場で買い増しており、2024年5月時点で8.09%を保有していました。一方、協栄産業は独立系ながら三菱電機の販売代理店として長年取引関係にあり、三菱電機以外に大株主の核がいない状態でした。業界ではエレクトロニクス商社の再編機運が高まっており、加賀電子は規模拡大と事業領域強化のため協栄産業の買収に踏み切ったものとみられます。
協栄産業取締役会はTOBに賛同を表明し、株主に応募を推奨することを決議しています。
スキームの特徴
今回のTOBは二段階買収で進められます。まず加賀電子がTOBで協栄産業株の過半数超を取得した後、TOB未応募株主を排除する手続として株式併合(1株未満の端数を発生させる割合での株式併合)を実施し、残る少数株主を強制的にキャッシュアウトします。この手続により協栄産業は上場廃止となり、加賀電子の完全子会社化が完了する計画です。
このため東京証券取引所は5月30日付で協栄産業株を監理銘柄(確認中)に指定し、上場廃止の可能性があることを投資家に周知しました。協栄産業側もTOB成立を前提に期末配当110円の支払いを見送り、株主優待制度も廃止すると発表しており、買収後を見据えた資本政策がとられています。
三菱電機との合意
三菱電機は協栄産業の大株主でしたが、今回の取締役会決議に賛同しており、TOBに応募する見込みと考えられます。明示的な公表はありませんが、筆頭株主の協力なしに完全子会社化は困難なため、加賀電子と三菱電機の間で事前に応募合意が成立した可能性が高いでしょう。これにより買付予定数を確実に確保し、スムーズに全株取得への道筋を立てています。
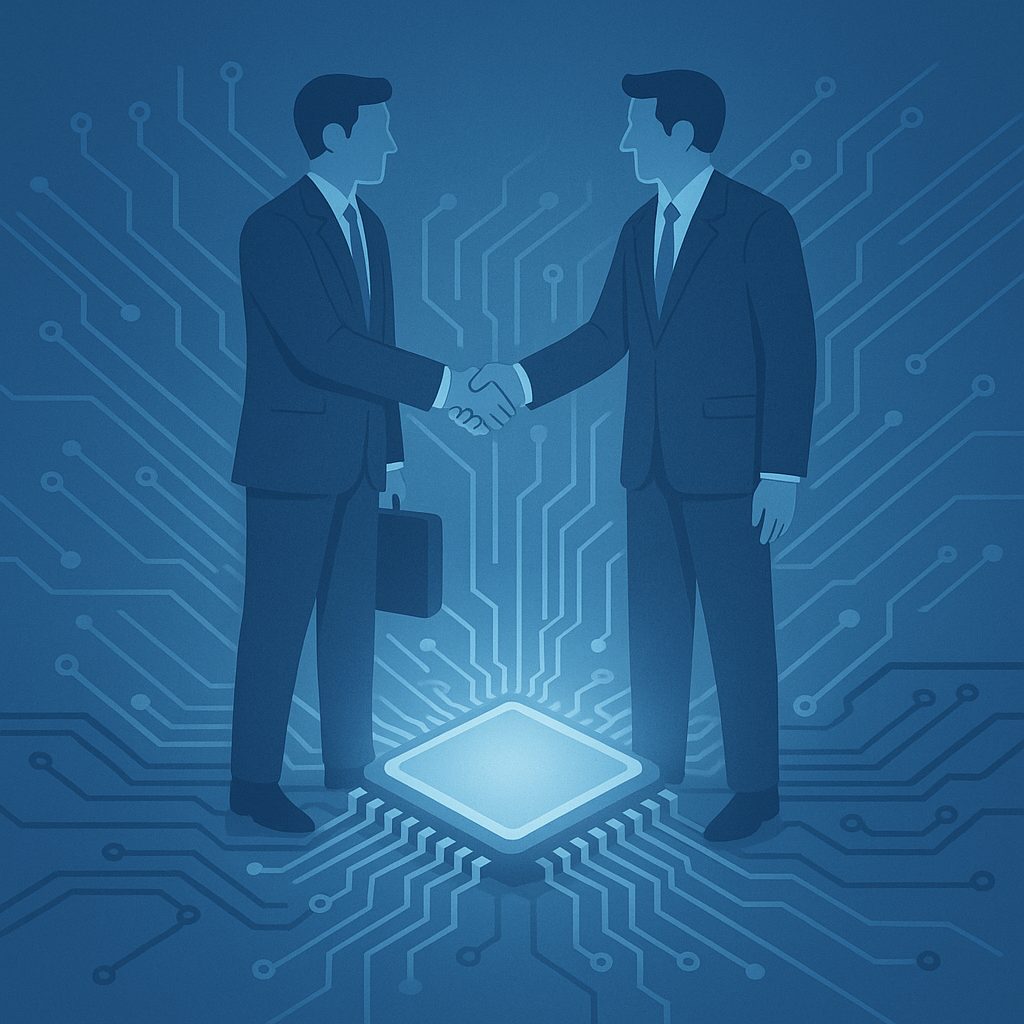
今回のTOBの特徴と狙い
① 完全子会社化を目指す二段階買収
加賀電子による協栄産業買収は、上場子会社を非上場化する典型的な手法です。まず公開買付けでできる限り株式を集め、続いて株式併合で残余株主を排除する二段階プロセスを採っています。このような手法により100%子会社化を確実に実現し、少数株主との利害調整を完了させる狙いがあります。
公開買付け段階で応募下限や条件を設定することで、一定割合以上の株式取得をTOB成立条件としており、成立後は速やかに併合手続きに移行できる契約となっています(協栄産業もこれを前提に決議。結果として協栄産業は株式市場から退出し、加賀電子グループ内で自由度高く事業再編・戦略展開が可能になります。
② 買付価格と交渉経緯
買付価格3,950円は、協栄産業株の直近株価に大幅なプレミアムを乗せた水準です。発表直前の株価(5月下旬は2,200円台)に対し約70%近い上乗せとなり、市場価格を大きく上回ります(発表前週の終値2,273円に対し+73.7%のプレミアム)。
これは筆頭株主である三菱電機や少数株主に十分な売却インセンティブを与えるためであり、協栄産業側の独立委員会や取締役会も価格の公正性を検証した上で賛同しています。実際、協栄産業取締役会は外部財務アドバイザーからフェアネス・オピニオン(妥当価格の意見書)取得等のプロセスを経て価格交渉を行い、3,950円で合意に至ったと推察されます。比較的小規模な企業の買収にしては高い買収プレミアムですが、それだけ協栄産業の企業価値やシナジーを評価した結果と言えるでしょう。
③ 業界再編の文脈
協栄産業の属するエレクトロニクス商社業界では、ここ数年で再編が加速しています。例えば2024年4月にはライバル同業の菱洋エレクトロ(8068)とリョーサン(8140)が共同持株会社方式で経営統合し、新会社「リョーサン菱洋ホールディングス」が発足しました。この統合では両社が上場廃止となり持株会社に移行しており、市場では「業界再編の波が中堅商社にも及んでいる」との見方が広がっています。
加賀電子自身も2018~2020年頃にかけて佐鳥電機(7420)の株式を一時10%以上保有し業界再編を模索しましたが、2023年に佐鳥電機が自己株TOBで対応し結果的に保有株を売却するなど、一部では統合が実現しなかったケースもあります。
そうした中、今回改めて協栄産業の買収に踏み切ったのは、業界再編の潮流に乗り競合他社に先駆けて規模拡大を図る狙いといえます。半導体商社業界は海外勢との競争も激しく、国内同業の統合で仕入先・販売先の拡充や在庫リスクの低減などスケールメリットを追求する必要性が高まっています。加賀電子は協栄産業を取り込むことで、国内外約2,000社からの仕入れと4,000社への販売ネットワークをさらに拡大し、市場地位を強化できると判断したのでしょう。
④ 想定されるシナジー効果
本件買収により、事業面・財務面で様々な相乗効果が期待されます。協栄産業は三菱電機系商社として産業機器システムやプリント配線板事業などを手掛けており、加賀電子の既存事業(電子部品・半導体の調達販売やEMS=受託製造など)との親和性が高いと見られます。加賀電子にとっては協栄産業が得意とする三菱電機製品の販路や顧客基盤を取り込めるメリットがあり、販売商品ラインアップの拡充や新規顧客獲得につながるでしょう。
また両社の在庫や物流網を統合することで業務効率向上やコスト削減が期待できます。財務面でも、上場子会社だった協栄産業を完全子会社化することで、グループ内の資本調達や資金配分を最適化でき、重複業務の統廃合による利益率改善も図れる可能性があります。
さらに、人材面でも相互補完効果があり、協栄産業の技術者や営業ネットワークを加賀電子グループ全体で活用することで総合力の向上が見込まれます。
要するに、今回のTOBは単なる規模拡大だけでなく製販体制の強化と収益力向上を目的とした戦略的買収と言えるでしょう。

将来的にTOBされる可能性のある中堅技術系企業
業界再編の流れを踏まえると、協栄産業と類似の特徴を持つ中堅技術系企業にも将来的にTOB(買収)の可能性が取り沙汰されています。
共通するポイントは「業界内で独立系または親会社による支配が弱い中堅企業」「財務的に安定しているが株価指標面で割安」「業界環境の変化により統合メリットが見込める」などです。
以下では、そのような企業として3社を取り上げ、それぞれ財務指標・業界動向・株主構成・株価水準の視点から分析します。最後に3社の買収される可能性の強弱も比較表で示します。
佐鳥電機
会社概要・業界ポジション
佐鳥電機は半導体・電子部品を扱う老舗エレクトロニクス商社です。電子部品の販売だけでなく製造支援や設計・開発機能も持ち、海外では台湾市場に強みがあります。国内半導体商社としては中堅規模で、マクニカ富士や加賀電子に次ぐグループに位置します。
財務指標
直近期の売上高は数百億円規模、自己資本比率も高く財務健全性は良好です。ROE(自己資本利益率)はおおむね8%前後で、安定した収益を上げています。株価指標を見るとPER約9倍、PBR約0.7倍、配当利回り5%超と典型的なバリュー株水準にあり、市場評価は純資産額に対して割安です。
これは業績好調にもかかわらず株価が伸び悩んでいる状態で、企業価値に比して株式の評価が低いことを示唆しています。
業界動向・再編の可能性
半導体商社業界では前述のとおり再編が活発化しています。佐鳥電機自身も過去に加賀電子から株式買い増しを受けた経緯がありましたが、2023年に自社株TOBを実施して加賀電子の持株を買い取る形で独立を維持しました。
この出来事は、同社経営陣(創業家)の独立志向を示すものと言えます。一方で半導体流通事業はグローバル化が進み、単独では規模不足との指摘もあります。生成AIブームやIoT拡大で半導体需要は中長期的に増加が見込まれ、対応力強化のために海外大手との資本提携や業界再編に参加する可能性はゼロではありません。
株主構成
大株主上位は信託銀行(マスタートラスト等)や日本カストディ銀行名義が占め、固定的な親会社は不在です。創業家の佐鳥浩之氏(社長執行役員)個人の持株比率は大量保有報告ベースでも5%未満とみられ、公表された主要株主には入っていません。
つまり支配株主不在の分散株主構成であり、敵対的買収に対する防衛策が課題となりえます。前回は自社株買いで撃退しましたが、財務負担を伴うため今後も同様に対応できるかは不透明です。創業家の年齢や後継問題もいずれ浮上する可能性があり、そのタイミングで第三者に経営を委ねる(M&Aに応じる)展開も考えられます。
株価水準
2025年5月現在の株価は1,000円前後で推移し、時価総額は約293億円です。PBR0.7倍台ということは解散価値(純資産)より30%近く安い評価であり、PERも一桁台と低水準です。市場では高配当(利回り5%超)であることからインカムゲイン狙いの投資家に人気がありますが、大きな成長シナリオが描きづらいためか株価は割安状態が続いています。
このような状況は、買い手にとっては割安に良質な事業を取得できるチャンスでもあります。事実、加賀電子は割安放置された佐鳥電機株に目を付けて買収を試みた経緯がありますし、今後も株価水準次第では他の資本が介入してくるリスク/チャンスがあります。
TOBされる可能性
総合すると、佐鳥電機は「TOB予備軍」の有力候補の一つです。他社から見て収益力のある事業を安価に買収できる余地があり、かつ特定の親会社もいないため交渉のハードルも比較的低いと言えます。ただし前回のように経営陣が強く独立を望む限りは自主独立路線が続くでしょう。
買収される可能性は中程度で、今後の業界再編の状況や株主(機関投資家)の意向次第では一気に現実味を帯びる展開も考えられます。
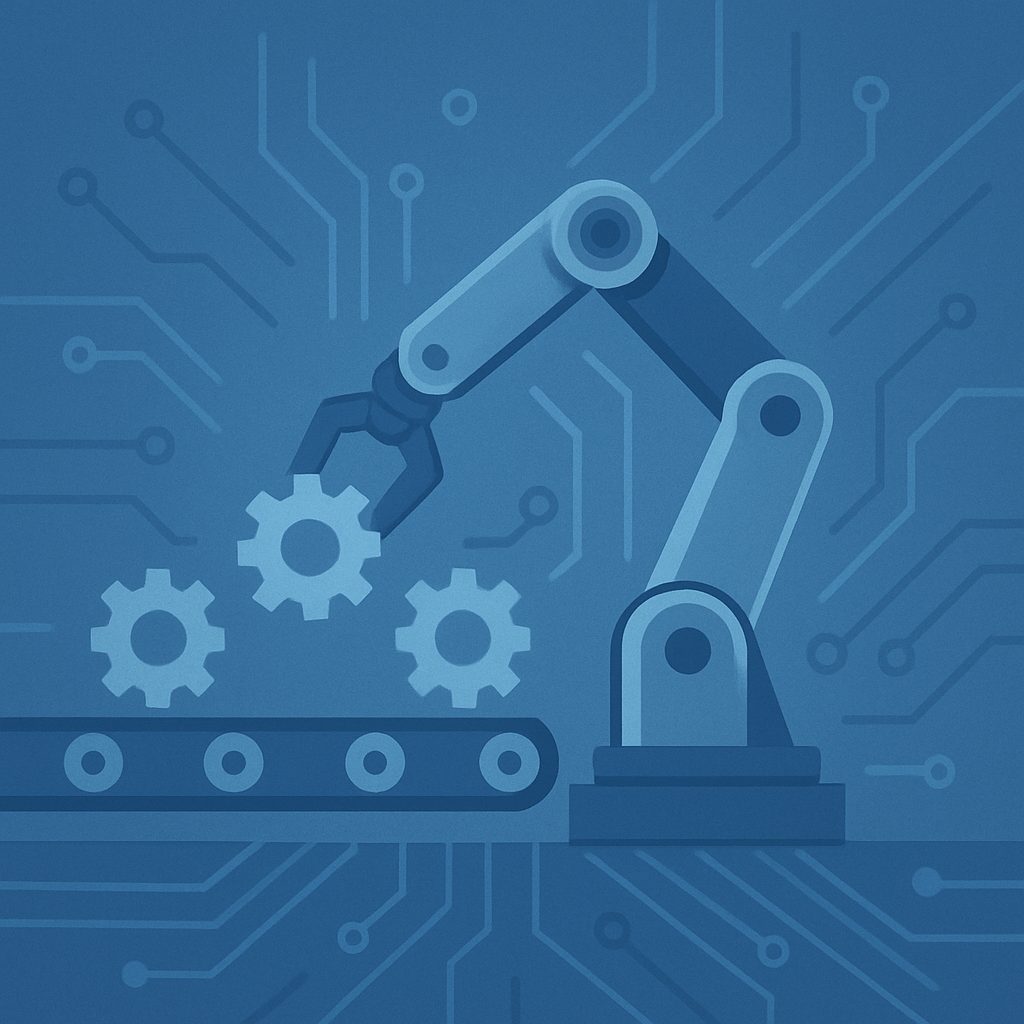
萩原電気ホールディングス
会社概要・業界ポジション
萩原電気ホールディングスは半導体・電子部品を扱う技術商社で、特に車載向けデバイスに強みを持っています。トヨタ系列をはじめとする自動車産業向けの半導体部品供給で存在感があり、近年の電気自動車(EV)化や先進運転支援システム(ADAS)普及の波に乗り恩恵を受けている企業です。売上高は連結で約500億円規模と中堅上位に位置し、営業利益率も安定しています。
財務指標
財務的には自己資本比率が50%以上と堅実で、過去の業績も黒字基調が続いています。ROEは7~8%程度と健全ですが突出した高さではありません。しかし株式市場での評価を見るとPERはわずか8倍強、PBRは0.6倍台しかありません。配当利回りは約5.5%にも達しており高配当銘柄として分類できます。これは萩原電気HDが解散価値の6割程度の評価しか受けていないことを意味し、同社もまた割安に放置されているバリュー株と言えます。
現金創出力に比して株価が低迷しているため、資本市場から見ると企業価値向上策(統合や非公開化)の余地がある状態です。
業界動向・再編の可能性
車載半導体分野は需要拡大が続く一方、サプライチェーン強化のための提携・統合も活発化しています。萩原電気HDの場合、主要顧客である自動車メーカーやティア1部品メーカーとの関係強化が重要で、場合によっては自動車メーカー系列による取り込み(資本参加)や、同業他社との合併で規模拡大するシナリオも考えられます。
実際、電子部品商社では規模のメリットが調達力・在庫対応力に直結するため、中堅同士の合併例(例えば菱洋エレクトロとリョーサンの統合)も出ています。萩原電気HDも独立系であるため、業界再編のピースとして他社からアプローチを受ける可能性は十分あります。特に車載分野に強い同社は、自動車業界の変革期において魅力的な買収ターゲットとなりえます。
株主構成
大株主上位を見ると、信託銀行(マスタートラスト信託口)が約11%、次いで日本カストディ銀行信託口が8%と機関投資家が並びます。一方、創業家・経営陣に関連する株主として有限会社スタニイが5.49%、萩原智昭氏(代表取締役会長と思われる)が3.77%保有しています。創業家一族の保有は合計で9%程度と見られ、経営の安定株主ではあるものの過半数には遠い水準です。
このため、もしTOBの提案があれば創業家だけで拒否するのは難しく、機関投資家の動向がカギになります。創業家が事業承継に悩む局面では、友好的買収提案に応じる可能性も否定できません。ただし現経営陣が強く独立維持を志向する場合は、防衛策として他社との資本業務提携やホワイトナイトを模索するかもしれません。
株価水準
2025年5月時点の株価は1株3,100円台で、時価総額は約317億円となっています。指標面ではPER8倍・PBR0.66倍・配当利回り5.5%という極めて割安な水準です。市場から見ると「収益力はあるが成長期待が低い」ものとして評価されており、新規事業などの材料が出ない限り株価の大幅な re-rating(評価替え)は起こりにくい状況です。
しかし、逆に言えば割安なまま放置されていると見做されれば外部からの働きかけが起こりやすいとも言えます。実際、萩原電気HDは近年アクティビスト(物言う株主)が保有報告を出したとの観測もあり、市場価値向上のプレッシャーが高まっている可能性があります。
TOBされる可能性
萩原電気HDは買収の可能性が充分に考えられる企業です。特に、自動車産業のサプライチェーン強化の文脈で親和性の高い企業からのアプローチがあり得ます。例えば、大手商社や他のエレクトロニクス商社、あるいは顧客である自動車メーカー系列の企業が資本参加・買収を提案するシナリオです。
創業家の意思と機関投資家の判断次第ではありますが、現状の株価割安度や業界での位置付けを踏まえるとTOBの可能性は中程度と評価できます。外部環境(半導体不足の解消や業績動向)によっては買収提案が顕在化する可能性もあり、引き続き動向に注目が集まるでしょう。
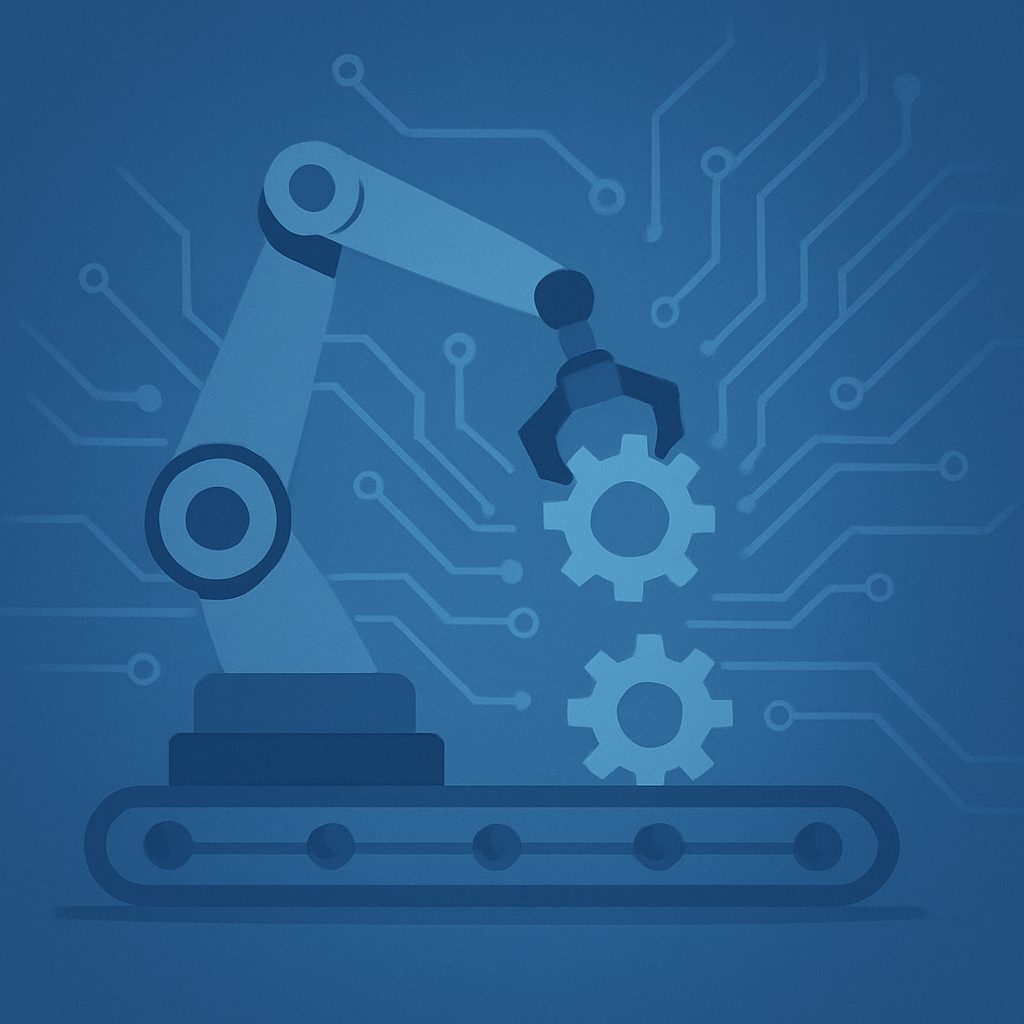
丸文
会社概要・業界ポジション
丸文は100年以上の歴史を持つ独立系エレクトロニクス商社で、半導体から電子部品、電子機器まで幅広く扱う老舗です。アナログIC、メモリ、マイクロプロセッサ、カスタムICなど多様な製品ラインアップを持ち、国内外の電子部品メーカー約200社の代理店として機能しています。
業界内では中堅どころですが、その伝統とネットワークから国外企業との提携も進んでおり、アメリカ大手半導体商社のアロー・エレクトロニクス(Arrow Electronics)が資本参加している点が特徴的です。
財務指標
丸文の業績は安定しているものの大幅成長には至っておらず、財務健全性も適度(自己資本比率40%台)です。収益性指標はROEで5~6%程度と控えめですが黒字は維持しています。株式市場での評価はPER約10倍、PBR約0.45倍とこちらも大きく割安となっており、配当利回りは5%強あります。時価総額は約263億円(株価937円)と他の中堅商社と同レンジです。PBRが0.5倍を下回っているのは、純資産の半分以下の評価しか受けていないことを意味し、かなり市場期待が低い状態です。背景には業績横ばいで成長性に乏しい点や、株主還元以外の話題が少ない点が挙げられます。
業界動向・再編の可能性
丸文は独立系商社ゆえに業界再編の波では重要な駒となり得ます。既にアメリカのアロー社が約8%の株式を保有しており、業務提携関係にあります。このことは、将来的にアロー社による完全買収(丸文の子会社化)や、更なる資本提携強化の可能性を示唆します。アロー社にとって日本市場の拡大は戦略的価値があるため、丸文を通じてプレゼンスを高めたい思惑があるかもしれません。
また国内に目を転じても、例えば加賀電子や他の独立系商社との合併で規模拡大を図るシナリオも考えられます。実際、業界内では「丸文は次の再編ターゲット」と見る向きもあります。マクニカ富士電子や菱洋・リョーサン連合に次ぐ存在として、丸文がどこと組むかで業界勢力図が変わりうるからです。
株主構成
上位株主を見ると、日本マスタートラスト信託銀行が約9.1%、前述のArrow Electronics社が約8.4%を保有しています。その他は信託銀行系が並び、事業会社では兼松エレクトロニクス(兼松系)などが一部保有する程度です。特定の支配株主はおらず、経営陣持株も大きくありません。
したがって、仮にArrow社がTOBを仕掛ける、あるいは第三の企業が買収提案する余地は十分にあります。鍵を握るのはArrow社の動向で、同社がさらに出資比率を高めるか、あるいは逆に株式を手放すかによって将来シナリオは変わります。少なくとも現状では丸文経営陣は独立路線を維持していますが、外部株主の意向には注意が必要です。
株価水準
株価は2025年5月時点で1株1,000円前後、時価総額は約263億円です。PBR0.45倍と極端に低く、配当利回りが5%を超えるなど放置状態に見えます。市場からの評価が低い一方で、潜在力のある事業基盤を持つため企業価値向上の余地があります。
このギャップに目を付ければ、既存株主による経営改革要求や他社からの買収提案が起きても不思議ではありません。現に、丸文は2023年に株主優待の新設や増配を発表し、総株主利益の向上に努めていますが、株価は依然低水準です。こうした施策にも限界がある場合、思い切った構造改革(他社との統合)が選択肢となるかもしれません。
TOBされる可能性
丸文は将来的なTOB可能性が高い部類と考えられます。その最大の理由は、既に戦略的株主であるArrow社の存在です。グローバル企業であるArrow社が本格的に買収に動けば実現可能性は高く、仮にArrow社が動かなくとも他の国内企業が割安さに注目して提案する可能性もあります。
もちろん経営側がどう判断するか次第ですが、独立を守るためには株価を上げ続けるしかなく、それが叶わないなら資本提携やTOBを受け入れる現実路線も視野に入るでしょう。従って、丸文のTOBされる確率は3社の中でも相対的に高いと評価できます。

3社の比較とTOB可能性の強弱
最後に、上記3社の主要指標と買収される可能性について比較表にまとめます。それぞれ財務の健全性、株価の割安度、支配株主の有無、業界内ポジションなどから総合的に判断したものです。
| 企業名(証券コード) | PBR(株価純資産倍率) | PER(株価収益率) | 配当利回り | 主な大株主 | TOBされる可能性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佐鳥電機 | 0.7倍程度 | 9倍程度 | 5.5%程度 | 特定支配株主なし(機関投資家が上位) | 中程度(独立志向強いが割安) |
| 萩原電気HD | 0.6倍程度 | 8倍程度 | 5.5%程度 | 創業家系約9%、他は機関投資家中心 | 中程度(業界注目も創業家次第) |
| 丸文 | 0.5倍程度 | 10倍程度 | 5%程度 | Arrow社8.4%、信託銀行9% | 高め(戦略株主あり再編余地大) |
※売上高は直近期の概算規模、その他指標は2025年5月時点。TOB可能性は筆者判断。
上の表を見ると、3社とも財務・収益面は安定している一方で株価バリュエーションが低く(PBRはいずれも1倍未満、PERも10倍前後)、共通して「割安な中堅テクノロジー企業」であることが分かります。佐鳥電機と萩原電気HDは配当利回りが高く(株主にとっては魅力ですが、それだけ株価が低迷)、丸文も含め純資産に対する株価が半分程度と、大企業と比べて市場評価が伸び悩んでいます。この状況は、裏を返せば第三者から見て非常に魅力的な買収候補であることを示唆します。
一方、株主構成を見ると各社で事情が異なります。佐鳥電機は明確な親会社がおらず機関投資家が中心のため、買収提案があれば株主次第で成立しやすい状況です。しかし経営陣が独立志向を持ち、自社株買いなどで対抗してきた実績があります。萩原電気HDは創業家が一定株を持つものの決定力は弱く、機関投資家の賛同があれば友好的TOBがまとまりやすい土壌があります。ただし創業家の意向が大きく影響するでしょう。丸文は外国戦略株主(Arrow社)がいる特殊ケースで、この株主が動けば一気に話が進む可能性があります。逆に言えば既に準備段階にあるとも言え、買収される蓋然性は比較的高そうです。
以上より、将来的にTOBされる可能性は丸文がやや高く、佐鳥電機と萩原電気HDがそれに次ぐと考えられます。ただ、中堅技術系企業の買収は最終的に経営陣や大株主の意思に左右されるため、必ずしも数字の論理だけでは決まりません。
実際に協栄産業のケースでも、三菱電機や協栄産業経営陣の合意があって初めてTOB成立に至りました。従って、これら3社もそれぞれの経営トップや主要株主が「このままでは企業価値向上が難しい」と判断した時に初めて、公開買付けによる再編が現実のものとなるでしょう。
まとめ
以上の解説から、業界再編期において割安な中堅企業は大手や競合からTOBの標的になり得ることが分かります。個人投資家としては、そうした潜在的TOB候補の企業に投資することで思わぬキャピタルゲイン(TOBプレミアム)を得られるチャンスもあります。
一方で上場廃止となれば継続保有はできなくなるため、TOB提案があった際は応募するか否かの判断が必要です。株主優待や配当狙いで長期保有していた場合でも、一度冷静に提示価格が妥当か検討し、自身の利益に沿った行動を取りましょう。業界再編の動きは今後も続く可能性が高く、関連ニュースやIR発表をチェックしつつ、適切な投資判断につなげてください。