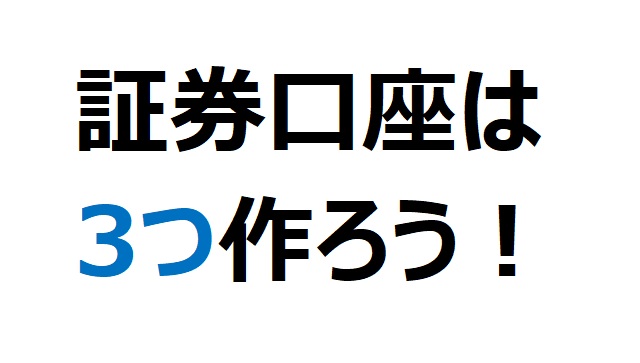
株式取引を始める際、多くの人は1つの証券会社の口座で取引を行います。しかし、経験を積んでいくうちに、複数の証券口座を持つことで取引の幅が広がり、リスク管理がしやすくなることに気づくはずです。本記事では、株式取引において複数口座を持つメリットや、具体的な活用方法について詳しく解説します。
証券口座を複数持つメリット・デメリットを比較!
| 項目 | 複数口座のメリット | 複数口座のデメリット |
|---|---|---|
| 取引コスト | 取引コストを最適化できる(証券会社ごとの異なる手数料体系を活用) | 管理が煩雑になる(複数口座の整理が必要) |
| 取引ツール | 取引ツールの多様化(高機能チャート、ニュース配信、スマホアプリなど) | 各証券会社のシステムの違いに慣れる必要がある |
| IPO投資 | IPOの当選確率向上(証券会社ごとの抽選枠を活用) | 証券会社ごとのルールや制限を理解する必要がある |
| 資産管理 | 資産分散によるリスク管理(システム障害の影響を低減) | 資産の一元管理が難しくなる(どの口座にいくらあるか把握しづらい) |
| 取引履歴管理 | ー | 取引履歴の整理が面倒(確定申告時に損益計算が複雑化) |
| 確定申告 | ー | 確定申告が煩雑になる(異なる証券会社間で損益通算が必要) |
| 投資スタイル | 取引スタイルの使い分け(短期・長期投資を明確に分けられる) | ー |
| その他 | ー | 相続や家族管理時の手続きが煩雑になる |
複数の証券会社をどう使い分ける?目的別活用パターン
証券会社の選び方
複数口座を持つ際には、それぞれの証券会社の特徴を理解し、目的に応じた口座開設を行いましょう。
| 証券会社 | メリット |
| SBI証券 | 手数料が安く、IPOの取り扱いが多い |
| 楽天証券 | 楽天ポイントが貯まり、ツールが充実 |
| 松井証券 | 1日50万円以下の取引手数料が無料 |
| マネックス証券 | IPOの当選確率が比較的高い、米国株に強い |
| auカブコム証券 | au経済圏の特典あり |
| GMOクリック証券 | 手数料が業界最安水準で、取引コストを抑えやすい |
取引戦略に応じた活用法
- デイトレード口座(スキャルピング向け): 高速約定が可能な証券会社を選ぶ
- 長期投資口座: NISA口座や手数料が無料の証券会社を活用
- IPO投資口座: 複数口座で抽選の確率をアップ
- 配当・優待投資口座: 株主優待や配当金狙いの長期投資向けに、優待情報が充実した証券会社を選ぶ
- 信用取引専用口座: 信用取引の手数料や金利が安い証券会社を利用し、レバレッジ取引に特化
- 海外株投資口座: 米国株や新興国株を取り扱う証券会社を活用し、グローバル投資を行う
- 積立投資専用口座: つみたてNISAや投資信託の積立を行うための口座を分けることで管理を容易にする
- 先物・オプション取引口座: 先物・オプション取引が可能な証券会社を利用し、リスクヘッジや投機を行う
- PTS取引用口座: 夜間取引や私設取引システム(PTS)を利用するために、対応している証券会社を選ぶ
資産管理の工夫
複数口座を持つと管理が煩雑になります。エクセルやGoogleスプレッドシートで資産管理することも最初のうちは考えられますが、必要に応じて資産管理アプリ(マネーフォワード、Zaimなど)を活用することで株式以外の資産の管理も含め適切に行えると思いますので、あわせて検討をしてもよいかと思います。
証券口座を使い分けると何が変わる?期待できる3つの効果
株式投資にはいろいろな知識・スキル・経験が必要だと思いますが、それらがどれだけ備わっていても最終的には「メンタル」をどうコントロールできるかが最重要になると考えています。
- 将来値上がりすると確信して買ったのに、ずるずる下がる状況に耐えらず売却してしまう
- 相場の急変動にあせって感情的に取引をしてしまう
- ついつい必要以上に信用取引を膨らませてしまう
いろいろな経験・知識・哲学があっても、この「メンタル」がすべてをぶち壊してしまうため、株式投資に関しての「メンタルコントロール」ができないと、なかなかトレードで勝っていくことは容易ではありません。
では、どのようにメンタルコントロールをすればよいかですが、株式投資において一番効果的なメンタルコントールは、なんといっても
「証券口座を複数もって使い分けること」
に尽きると思います。
証券口座を分けて、強制的にメンタルをコントロールできれば、不本意なトレードを減らしたうえでリスク管理もでき、結果的に資産も安定的に増やしやすくなるということです。
私が実際に使い分けている3つの証券会社と理由【体験談】
具体例として3つの証券口座を作って、短期保有・中期保有・長期保有という3つに分けて利用するようなイメージにするとメンタルコントールにも最適です。
人間の特性として、損益金額をリアルに見てしまうと、当初の意図とは別の力が働いてしまいます。たとえば、長期投資のつもりだったのに、含む損が膨らむと手放したり、長期でもっていると含み益が増えていくところをすぐに利確してしまったり、といったことが起きます。
このような不本意なトレードを避けるためには、
「証券口座を見ない」
というのが一番の解決策です。
そのためには、長期投資用の証券口座と短期投資用の証券口座を物理的に分ける必要があります。1つの証券口座に長期投資も短期投資もごちゃ混ぜにして運用してしまうと、意図しないトレードをしてしまいますので、とくに長期投資も併用したい場合には、必ず証券口座を別に保有しておく必要があります。
短期保有口座(例:SBI証券、楽天証券)
- 手数料の安い証券口座
- 操作性のよい証券口座
中期保有口座(例:松井証券、マネックス証券
- 手数料の安い証券口座
- 銘柄分析等の機能が充実している証券口座
長期保有口座(例:立花証券)
- 手数料の高い証券口座(⇒手数料が高い方が安易に売買しない)
- 操作性の悪い証券口座(⇒操作性悪い方が安易に売買しない)
まとめ
証券口座を複数作ると、管理が面倒になったりするといったでメリットも当然ありますが、それを上回るメリットがあるので、株式投資に慣れてきたら、ぜひ複数の証券口座を運用するスタイルに徐々に移行してみましょう。
口座数としては3つくらいがベストかと思います。
そのうち1つの証券口座は、一番多くトレードをするメインの証券口座になると思いますが、おそらくその口座は最初に作っている証券口座がその役割を担うことが多きがします。手数料等の問題もあると思いますが、やはり使い慣れた証券口座が一番取引がしやすいと思いますので。
そのうえで、2つ目、3つ目の口座は、中長期投資用としてあまりトレードをしない前提でよいので、保有することをお勧めします。トレードを頻繁にしないので、手数料とかはあまり重視しなくてよいと思っています。逆に手数料が無料だと不要な取引をしてしまうので、SBIや楽天のような完全無料な証券口座は不向きかもしれません。
2つ目、3つ目の口座としてお勧めなのは、以下のような証券口座だと考えております。
- マネックス証券
- 松井証券
- auカブコム証券
- GMOクリック証券
- 立花証券