富士通ゼネラルがTOBに!その背景と「買われやすい企業」の特徴とTOB予想銘柄3選
2025.05.07投稿
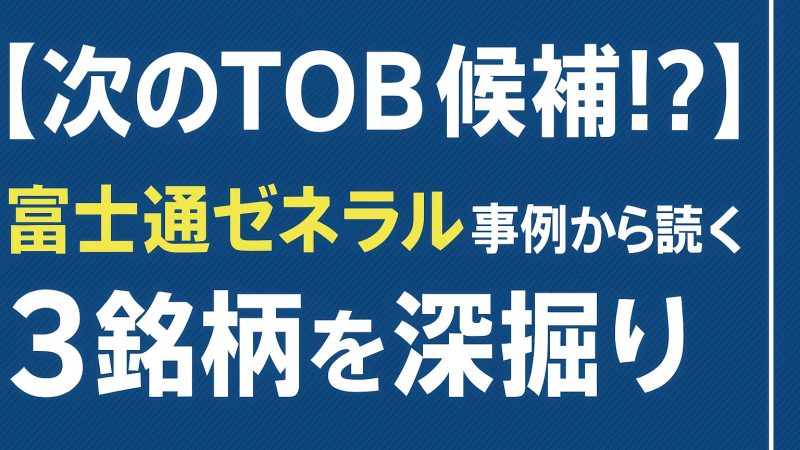
空調機器メーカー大手の富士通ゼネラル(東証プライム:6755)が、パロマ・リームホールディングス(以下、パロマ・リームHD)によるTOB(株式公開買付け)の対象となることが発表されました。個人投資家にとっては「なぜこの会社が買収されるの?」「どんな企業がTOBのターゲットになりやすいの?」と気になるニュースでしょう。本記事では、このTOBの概要や背景をわかりやすく解説し、過去の事例との比較を交えながら「買われやすい企業の特徴」や「買収を仕掛ける企業の狙い」について考察します。
TOB概要:価格・期間・プレミアム・スクイーズアウト
まず今回のTOBの基本情報を押さえましょう。パロマ・リームHDは2025年4月28日から5月28日までの期間で、富士通ゼネラル株を1株あたり2,808円で買付けすると発表しました。この買付価格2,808円には、直前の株価に対して約20%強のプレミアム(上乗せ幅)が含まれています。プレミアムとは、株主に売却してもらうために通常の株価より高く提示する上乗せ価格のことです。
今回の場合、例えば2024年12月30日時点の終値2,327円に対して約20.7%上乗せされた水準であることが報告されています。また、過去1ヶ月間の平均株価2,206円と比べると約27.3%、過去3ヶ月平均2,075円に対して約35.3%、過去6ヶ月平均2,018円に対して約39.2%プレミアムがついており、ここ数年のTOB事例と比べてもまずまず高めのプレミアムと言えそうです。
公開買付け(TOB)とは、買い手(企業や投資ファンドなど)が対象企業の株式を市場外で不特定多数の株主から直接買い集める手法です。通常の株式市場で買うのではなく、「●●円で●●期間中に買います」と公表して株主から応募(売却)を募る仕組みです。今回、パロマ・リームHDは富士通ゼネラルの発行済株式の全て(ただし同社の自己株式と親会社・富士通株式会社が保有する株式を除く)を買い付ける計画です。買付予定総額は約1,647億円に達し、TOB成立後は富士通ゼネラルを上場廃止として完全子会社化(100%親会社の傘下にする)する方針です。
ただし今回特徴的なのは、富士通ゼネラルの親会社で約44%の株式を持つ富士通株式会社はTOBに応募しないという点です。その代わり、TOB完了後に富士通ゼネラルが富士通からその株式を買い取る(自己株式取得)手続きを取ることで、最終的に全株をパロマ・リームHD側が取得する段取りとなっています。このようにTOB後に残った株式を強制的に取得して完全子会社化するプロセスは、スクイーズアウト(Squeeze-out)や二段階買収と呼ばれます。具体的には、TOBで一般株主からできる限り株を取得した後、残りの富士通保有分を株式併合や自己株買い等で取得し、完全支配を達成します。スクイーズアウトでは少数株主(今回は富士通)は強制的に現金化される形になりますが、今回の枠組みでは富士通も一般株主と経済的に同等の条件になるよう調整されています。つまり、富士通だけが特別に有利・不利にならないように配慮しつつ進められる点が注目ポイントです。
また、今回のTOBは友好的TOBです。富士通ゼネラルの取締役会はこの提案に賛同の意見を表明しており、株主に対してTOBへの応募を推奨する姿勢を示しています。友好的TOBとは、対象会社の経営陣や主要株主の同意を得た上で行われるTOBで、対立のない円満な買収プロセスを指します。逆に、経営陣の意向に反して強行される買収は敵対的TOBと呼ばれます。今回の場合、富士通ゼネラル経営陣は「本TOBは当社の企業価値向上に資するもので、価格も公平妥当であり、株主の皆様にとって合理的な売却機会を提供する」と評価し賛成している旨が開示されています。このように協調路線で進むTOBは成立の可能性が高く、実際に富士通ゼネラル株はTOB発表直後に買付価格にサヤ寄せして株価が上昇しました(TOB価格2,808円に向けて上昇)。
以上がTOBの基本的な概要です。では、なぜ富士通ゼネラルは買収されることになったのでしょうか?背景を見ていきましょう。
富士通ゼネラルがTOB対象になった理由(背景と富士通の意図)
富士通ゼネラルが今回TOBの対象となった背景には、大株主・富士通本体の事業戦略の変化があります。富士通ゼネラルは1984年以来、親会社である富士通株式会社と資本提携関係にあり、富士通が約44.02%の株式を長らく保有してきました。つまり富士通ゼネラルは富士通グループの一員だったわけです。しかし近年、親会社の富士通は事業ポートフォリオの見直しを進めており、グループ再編の一環としてノンコア(中核ではない)事業の整理・売却を積極化させています。
富士通にとって、空調専業の富士通ゼネラルはかつては関連シナジーも見込まれたパートナーでしたが、デジタルサービス企業へと変革を進める富士通本体との親和性が薄れてきたと指摘されています。実際、2020年頃から両社は資本関係の今後について協議を続けてきたとのことです。富士通としては、自社の集中分野ではない空調機器事業を手放して資源を本業に集中したい一方、富士通ゼネラルにとっても親会社の方針転換により将来の支援が期待しにくくなった状況でした。
こうした中で外部からの買収提案が浮上します。実は2024年9月、パロマ・リームHD側から富士通ゼネラルに買収の提案があったことが報じられています。富士通ゼネラルと富士通はその提案を受け、交渉を重ねた結果、2025年1月に今回のTOBに関する基本合意が発表されました。この時点で富士通ゼネラルは「賛同の意向」を示し、富士通も自社保有株をTOBでは売却せず別途処理(前述の自己株取得)する形で買収に協力することになります。
富士通本体の狙いとしては、保有株式の売却益を得ることや、グループ外企業に委ねた方が富士通ゼネラルの事業拡大につながるとの判断があったと考えられます。実際、富士通は富士通ゼネラル株の売却によって約800億円規模の利益計上を見込む旨を公表しています(2025年1月時点報告より)。富士通ゼネラルの成長よりも、自社の財務強化や構造改革を優先した経営判断と言えるでしょう。
まとめると、富士通ゼネラルがTOB対象になったのは:
- 親会社・富士通の事業再編方針(ノンコア事業の切り離し)
- 両社のシナジー低下に伴う資本提携解消の流れ
- 外部から魅力的な買収提案(パロマ・リームHD)があったこと
といった背景が重なった結果でした。では一方の買い手であるパロマ・リームHDは、なぜ富士通ゼネラルを買収したいのでしょうか?
パロマ・リームHDが富士通ゼネラルを買収したい理由(戦略とシナジー)
パロマ・リームホールディングスは、世界的な空調・給湯機器メーカーグループです。日本のガス機器大手「パロマ」と、米国の空調・温水機器メーカー「リーム(Rheem)」が1988年に資本統合して生まれた企業グループで、空調(エアコン)と給湯機器の両分野でグローバル展開しています。グループ売上高は1兆円規模、従業員約19,000人を擁する巨大プレイヤーです。
パロマ・リームHDが富士通ゼネラルを買収する狙いを一言で言えば、グローバル展開力と技術力の強化です。
北米市場へのさらなる進出:
富士通ゼネラルはエアコン分野で北米市場に強みを持っています。特に家庭用エアコン「ノクリア」ブランドなどで日本品質の省エネエアコンを北米に展開しており、現地での販路やブランド力があります。パロマ・リームHDはリームを通じて北米市場に基盤がありますが、富士通ゼネラルを取り込むことで北米の販路拡大や製品ラインアップ強化が望めます。
アジア・欧州への事業展開:
富士通ゼネラルはインドや欧州、中東などでも空調事業を展開しています。パロマ・リームHDは給湯器分野が主力ですが、富士通ゼネラルを傘下に入れることで空調事業でアジア・欧州にもネットワークを広げられるメリットがあります。
技術開発のシナジー:
富士通ゼネラルは空調制御や関連ITシステムに強みを持ち、IoTやAIを活用したスマート家電化にも取り組んでいます。一方パロマ・リームHDも環境対応技術や省エネ技術に注力しています。両社が組めば技術開発リソースを共有し、新製品開発や既存製品の高性能化でシナジーが期待できます。
要するに、パロマ・リームHDは富士通ゼネラルを取り込むことで「Air(空調) & Water(給湯)」分野で世界トップクラスの総合力を目指していると言えます。双方の事業領域が補完関係にあり、統合によりスケールメリットや研究開発の相乗効果が見込めるからです。さらに富士通ゼネラルは上場企業として独立経営していましたが、今後は非上場の完全子会社となることで短期的な株主プレッシャーから解放し、中長期的視点の大胆な投資・戦略展開が可能になる利点もあります。パロマ・リームHDとしては、グループ内に取り込んでじっくり育成・拡大したい考えでしょう。
一方、富士通ゼネラル側にとっても、親会社が富士通からパロマ・リームHDに変わることで事業シナジーが高まると期待されます。同じ空調・給湯にフォーカスした親会社の元で、研究開発投資や海外展開の加速など、新たな成長機会が開けるかもしれません。現経営陣がTOBに賛同したのも、パロマ・リームHD傘下での企業価値向上に手応えを感じたからと推測できます。
過去のTOB事例との比較:共通点と相違点
今回の富士通ゼネラルのTOBは、近年日本で相次いでいる上場子会社の完全子会社化の流れの一つとも言えます。過去の事例と比較し、共通点や違いを整理してみましょう。
| 事例(年) | 買収者(主体) | 対象企業(子会社) | TOB価格とプレミアム | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 富士通ゼネラル (2025年) | パロマ・リームHD(第三者) | 富士通ゼネラル | 2,808円(直近期末終値に約20%上乗せ) | 親会社富士通が売却、第三者が取得。友好的TOB。 |
| NTTドコモ (2020年) | NTT(親会社) | NTTドコモ | 3,900円(終値2,775円に約40.5%上乗せ) | 親会社による完全子会社化。巨額TOB(約4.3兆円】。 |
| 日立ハイテク (2020年) | 日立製作所(親会社) | 日立ハイテク | 8,000円(終値4,080円に約96%上乗せ)※参考値 | 親会社による完全子会社化。高プレミアムで話題に。 |
| 東芝 (2023年) | JIPコンソーシアム(第三者ファンド) | 東芝 | 4,620円(終値4,213円に約9.7%上乗せ) | 経営再建で非上場化。プレミアムは低め。 |
| デサント (2019年) | 伊藤忠商事(筆頭株主) | デサント | 2,800円(終値1,871円に約49.7%上乗せ) | 敵対的TOB(当初は反対)。のち和解し経営権取得。 |
| 日立化成 (2019年) | 昭和電工(第三者) | 日立化成 | 4,630円(終値4,080円に約13.5%上乗せ) | 子会社売却。買収額約9600億円。 |
※日立ハイテクのプレミアム(約96%)は他に類を見ない高水準で、当時の市場株価が割安すぎたことも要因です。通常は20〜40%程度が一般的です。
こうした事例を見ると、上場企業がTOBで買われるパターンはいくつかあります:
- 親会社が残り株を買い取って完全子会社化(例:NTTドコモ、日立ハイテクなど)。親会社にとっては少数株主への配慮や機動的経営のため、子会社を非上場化する動機があります。プレミアムは親子上場解消の場合比較的高くなる傾向(株主説得のため高値を提示)にあります。
- 第三者(他社やファンド)が買収(例:富士通ゼネラル、東芝、日立化成など)。親会社や筆頭株主が株式売却に応じ、外部の企業グループが取得するケースです。事業シナジーや再建目的など背景はいろいろですが、対象企業側が買収提案に賛同していると友好的TOB、反対だと敵対的TOBになります。プレミアムはケースバイケースですが、友好的であれば市場価格+20〜30%、敵対的なら場合によっては+50%以上提示する例もあります(デサントの初回提案は約49%上乗せ)。
- 経営陣が主体のMBO(経営陣買収でTOBする例)もありますが、今回は割愛します。
富士通ゼネラルの場合は「親会社が売却し第三者が取得」のパターンで、友好的TOBです。同じ型の例として日立製作所が日立化成を昭和電工に売却(2019年)や、富士フイルムが富山化学を投資ファンドに売却(2021年)などがあります。この場合、親会社・対象会社・買収者の三者合意で進むため成功率が高いのが特徴です。
一方でTOBが不成立に終わるケースや、敵対的買収の失敗もあります。有名なものでは王子HDによる北越製紙へのTOB(2006年、失敗)や、村上ファンド系による新生銀行へのTOB提案(2021年、失敗)など。これらは経営陣の強い反対や対抗策で阻止されました。敵対的買収は日本ではまだ成功例が少なく、買収側はかなりの高値を提示しないと株主の支持を得にくい傾向があります。
「買われやすい企業」の特徴:次のTOB候補を考えるヒント
TOBの事例を見てきましたが、個人投資家としては「次にTOBされるのはどんな会社か?」と予想したくなるものですよね。買われやすい企業の特徴をいくつか挙げてみます。ただし、これはあくまで一般論であり、必ずしも当てはまるわけではありませんので参考程度にお読みください。
1. 大株主が明確な売却意向を持っている会社
親会社や筆頭株主が「株式を手放したがっている」ケースはTOBの種になりやすいです。富士通ゼネラルは富士通がノンコア整理を進めていましたし、日立化成も親の日立製作所が売却方針を示していました。大株主が明確なエグジット(売却)戦略を持つ企業は、その株を誰が買うかという話になりやすく、結果TOBの対象になります。最近では商社系が持つ非上場会社や金融機関の持ち株なども整理が進んでおり、関連する上場子会社が浮上することがあります。
2. 業績は堅調だが株価が割安な会社
敵対的買収の文脈でも言われますが、株価が安い(PBRが低い、含み資産が多い等)企業は狙われやすいです。上場していても市場から正当な評価を得られていない企業は、外部から「安いうちに買って立て直せばリターンが取れる」と見做されることがあります。さらに業績が安定していてキャッシュフロー豊富な企業は、買収後の財務負担リスクも低いため買い手に好まれます。例えばNTTドコモは安定高収益で配当利回りも高かったため、NTT本体が割安と判断して買い増しに踏み切りました。
3. 成長分野の独自技術やブランドを持つ会社
特許やブランド力など、他社が欲しがる独自資産を持つ企業も買収されやすいです。特に買い手企業が参入したい新市場にフィットする技術・製品を持っている場合、シナジー獲得目的でTOBが仕掛けられます。富士通ゼネラルの空調技術はパロマ・リームHDにとって魅力的な資産でした。同様に、例えばDX関連技術を持つ企業が旧来産業の大企業に買われるケースや、海外進出の足がかりとなるブランド企業が狙われるケースがあります。
4. 株主構成が分散していて買収防衛策がない会社
大株主が不在で株主が分散していると、敵対的TOBも成立しやすくなります。逆に安定株主が固めていて買収防衛策(ポイズンピルなど)を導入している企業はハードルが高いです。上場企業でもオーナー家や友好的株主が固めていない、浮動株が多い会社は、外部から仕掛けられやすい土壌があります。
5. 事業が成熟期にあり、更なる成長には再編が必要な会社
自社だけでは頭打ちだが、他社と組めば活路がある——そんな企業もM&Aの対象になります。市場縮小や競争激化で単独では厳しい場合、業界再編の流れでTOBの対象となるケースがあります。例えば家電業界や素材業界などで、業界再編が続く分野は今後もあり得ます。
こうした特徴を複数持ち合わせる企業は、「次はここがTOBされるかも?」とマーケットで噂になることもあります。ただし、実際のTOBは水面下で交渉が進み突然発表されるのが常です。事前予想は専門家でも難しいものなので、投資家としては参考程度に考え、実際にニュースが出てから適切に対応できるよう知識を蓄えておくことが大切です。
まとめ:TOBは投資家にとってチャンスか?注意点は?
最後に今回の件と一般論を踏まえてまとめます。
富士通ゼネラルのTOBは、親会社の方針転換と第三者企業の戦略的狙いが合致した、友好的な買収劇でした。価格2,808円・期間4/28〜5/28・プレミアム約20〜30%という条件で進み、TOB成立後は株式が上場廃止となる見込みです。個人株主にとっては、TOB価格での売却益が得られる一方、愛着ある会社の上場廃止という寂しさもあるでしょう。TOBに応じるか否かは基本的に自由ですが、今回は経営側が賛同しており上場廃止が避けられないため、ほとんどの株主は応募または市場売却する流れになると思われます。
投資家向けの視点として、TOBは時にサプライズで株価が急騰するチャンスとなります。事前に仕込んでおけば大きな利益が出ることも。ただし、やみくもに「割安だから買われるはず」と投資するのは危険です。買収されなければただの割安株止まりで、いつまでも放置されるリスクもあります。また、敵対的TOBの場合は紛糾して不成立となり株価が元の水準に戻るケースもあります。
大事なのは、企業の本質価値を見極めた上で投資判断することです。仮にTOBされなくても割安ならいずれ市場で評価される、自力で成長できると信じられる企業に投資しておけば、TOBがあればラッキーくらいのスタンスが健全でしょう。逆に、「買われやすい特徴」に当てはまっていても業績不振や将来性疑問の企業は、買収提案が出ても安値買い叩きになりかねません。
今回の富士通ゼネラルの例は、株主・企業双方にメリットのあるウィンウィンな買収と言えます。個人投資家としても、TOBの仕組みや最近の動向を知っておくことで、いざ自分の持ち株にTOB提案が来た時にも慌てず対応できるでしょう。
次のTOB候補!?高配当・低PBRで“買われやすい”3銘柄を深掘り!
最後に、今回の事例をもとに次のTOB候補を予想してみたいと思います(※あくまで個人的な予想となります)。
上記でまとめた 「買われやすい企業の5条件」──
- 大株主の売却意向/非コア化
- 技術・ブランドなど独自資産
- 高いキャッシュ創出力と割安バリュエーション
- 株主構成がシンプルで防衛策が弱い
- 成熟市場で再編メリットが大きい
ここに追加で 「配当利回り3.5%以上&PBR1倍以下」 のフィルターを当てはめ、TOB(公開買付け)の次なるターゲットになってもおかしくない 3 社を選んでみました。
| 銘柄 | 配当利回り※ | PBR※ | 時価総額(概算) | キーワード |
|---|---|---|---|---|
| マツダ(7261) | 6.39% | 0.30倍 | 約8,000億円 | トヨタ5%保有/EV提携 |
| AOKI HD(8214) | 5.93% | 0.78倍 | 約1,650億円 | 創業家系ファンド38%/不動産含み益 |
| 東京汽船(9193) | 6.26% | 0.33倍 | 約350億円 | MOL11%+創業家17%/港湾再編 |
※2025年5月1日終値ベース
マツダ──トヨタが本気を出せば“一気買い”も?
- 低PBR0.30倍・配当6%超は大手完成車メーカーで突出。
- 筆頭は信託銀行だが、トヨタ自動車が5.1%を保有し資本業務提携済み 。
- EV開発では規模の論理が効くため、トヨタが追加出資で主導権を握るシナリオは市場の常連ネタ。
- 買収メリット
- ラインアップ拡大:マツダの内燃機×電動ハイブリッド技術はHV下位ブランドとして親和。
- 北米販路の共有:トヨタ系ディーラー網にマツダ車を相乗り → 広告・物流を一本化。
- カーボンニュートラル投資の平準化。
ポイント:自動車産業は巨額投資を抱えるため単独上場のデメリット(資本コスト上昇)が顕在化。EVの重い先行投資を考えると、トヨタがTOBで完全子会社化し、研究・生産を一体運営する選択肢も非現実的なものではないと考えられます。
AOKIホールディングス──“創業家38%”はMBOの呼び水
- ブライダル施設「アニヴェルセルHD」が 38.5% を握り、創業家親族がさらに約10%強を保有 。
- コロナ禍で苦戦したスーツ事業だが、店舗統廃合が一巡しフリーCFは黒字基調。
- 商業地立地の大型路面店など不動産含み益が豊富。
- 想定される買い手
- 創業家主体のMBO+PEファンド(ベイン・CVC等):上場維持コストと四半期開示を嫌い非公開化。
- 総合リユース大手(メルカリ・ラクサス)などOMO型アパレル連合:リアル店舗網を一気に獲得。
ポイント:経営陣と創業家が大株主のため、株式をまとめて買い取る“話の早さ”が魅力。配当利回りの高さは「買収後に配当を絞って投資に振り向ける余地がある」サインでもあります。
東京汽船──港湾サービス再編の“ラストピース”
- タグボート(曳船)専業で都心港湾に強み。設備投資済みで現在は高CF体質。
- 創業家17.4%+商船三井(MOL)11.2%が大株主 。
- 配当利回り 6%、PBR 0.33 と“解散価値割れ”水準。
- 買収ストーリー
- ① MOLが追加取得し完全子会社化 → コンテナ・不定期船との安全運航シナジー。
- ② 国際港湾運営ファンド(オリックス系・豪IFM等)がインフラ資産として買収。
- ③ 国内港湾グループ再編(横浜・川崎汽船グループとの合従連衡)。
ポイント:港湾は国家安全保障インフラで“敵対的”は起こりにくい一方、指名買いの友好的TOBが動きやすい分野。浮動株が多く、スクイーズアウトまでのコストも低いのが魅力です。
3 社はいずれも「買われやすい5条件」に合致
| 条件 | マツダ | AOKI HD | 東京汽船 |
|---|---|---|---|
| ① 非コア化 or 売却意向 | トヨタ以外の金融信託が17%、親がいない“孤児” | 創業家が議決権確保→タイミング次第 | 創業家高齢化+MOL再編 |
| ② 独自資産 | ロータリー&スモールEV技術 | 婚礼&カラオケ施設+不動産 | 首都圏港のタグボートシェア |
| ③ 高CF & 割安 | 営業CF 3,000億円/年、PBR0.3 | 不動産売却益で潤沢、PBR0.78 | 設備重いが減価後CF厚い、PBR0.33 |
| ④ 株主構成 | トヨタ以外は分散 | 創業家ブロック+浮動株 | 創業家+MOLで過半見通し |
| ⑤ 再編メリット | EV投資共同化 | 上場コスト削減 & 不採算店整理 | 港湾サービス統合 |
どう“張る”か?
- シナリオと時間軸を決めよう
- マツダ: 2~3年以内のEV投資ピークが山。
- AOKI: 創業家の相続対策が顕在化する前後がXデー。
- 東京汽船: 国内港湾再編が動き出すと一気に。
- 高配当をもらいながら待つ戦術
配当利回り 6%前後が“時間を買う”コストを実質ゼロ近くにしてくれます。 - リスクも忘れずに
TOBは“いつ来るか”が最大の読みづらさ。来なければ 低PBR=低ROE の罠に陥る銘柄も多いので、業績トレンドは要チェックです。
| まとめ ・高配当×低PBRで市場から放置されがちな企業は、資本再編の“餌食”になりやすい ・大株主の動き(売却・相続・業界再編)が「火種」になる ・配当を受け取りつつ“待ち伏せ”するのが個人投資家の王道戦術 |