【TOB事例】予想的中!鳥居薬品TOBの分析と業界への影響と類似銘柄のTOB可能性の考察
2025.05.19更新
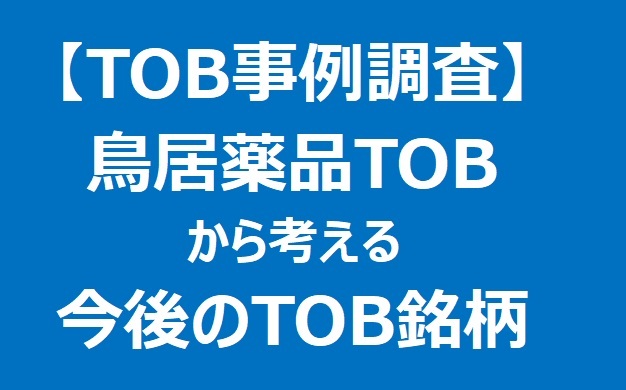
以前に「【TOB候補】鳥居薬品(親子上場)」の記事でTOB候補銘柄として鳥居薬品の紹介をしていましたが、実際にTOBが実施されました。そこで、本記事は鳥居薬品株式会社(証券コード: 4551)に対するTOBに関して、TDnet開示資料(2025年5月7日付)をもとに状況整理をしてみたいと思います。
塩野義製薬(公開買付者)が取締役会決議により、鳥居薬品を完全子会社化することを目的としてTOBを実施しましたが、公式開示情報の内容を5つの観点から整理し、その後に鳥居薬品と類似する特徴を持つ企業について、将来的にTOB候補銘柄として考察してみたいと思います。
TOBの目的(背景と戦略的意義)
鳥居薬品に対するTOBの背景には、親会社である日本たばこ産業(JT)の医薬事業再編と塩野義製薬の成長戦略がありました。塩野義製薬は自社の中期経営計画「STS2030」のもと、医療用医薬品に留まらない総合ヘルスケア企業(HaaS)への変革と成長ドライバーの育成を推進しており、外部資源の取り込みも模索していました。そうした中、JTが医薬事業の整理を検討していたことから、塩野義はJTの医薬事業およびその販売子会社である鳥居薬品の一体取得を2024年初頭より検討し、当該ビジョン実現に大きな意義があると判断しました。実際、塩野義は2024年8月にJTおよび鳥居薬品に対し、JT医薬事業の譲受と鳥居薬品の完全子会社化を提案しています。
このTOBの戦略的意義は、鳥居薬品を非上場化して完全子会社化することで、グループ内での迅速かつ柔軟な意思決定と経営資源配分を可能にし、シナジー効果を最大化する点にあります。塩野義は鳥居薬品を上場のまま業務提携する選択肢ではなく、完全子会社化による一体運営が必要との考えに至りました。上場維持の状態では、短期的な株価変動による一般株主との利害相反や、独立性確保の制約により十分な情報共有・戦略策定が難しく、グループ最適な施策の実行に支障を来す恐れがあるためです。したがって、本TOBは親会社JTから医薬事業を譲り受けつつ鳥居薬品を完全子会社化することで、塩野義グループ全体の企業価値向上を図るという明確な目的のもと実施されています。
買付者の意図と今後の事業戦略
買付者である塩野義製薬は、本TOBにより鳥居薬品を取り込むことで得られる具体的な事業上のシナジー効果を重視しています。公式開示資料によれば、塩野義が期待する主なシナジーは以下のとおりです。
国内事業の強化
塩野義と鳥居薬品は得意とする診療科や領域が異なり、統合後はそれぞれの営業力を補完し合うことで情報提供の範囲と質が向上します。例えば、塩野義が扱う新型コロナウイルス感染症やインフルエンザの治療薬について、鳥居薬品の強みである皮膚科・小児科・耳鼻科領域での販促ネットワークを活用することで、より多くの医師・患者に適切な情報を届けられるようになります。
他方で、鳥居薬品の皮膚科領域製品(例:コレクチム®等)については、塩野義の営業資源を活かして内科や整形外科など皮膚科以外の診療科にも展開でき、結果として顧客満足の向上や営業効率化が図れるとされています。将来的には、両社の開発パイプラインにおいて、塩野義の高い研究開発力と鳥居薬品の強い営業力を組み合わせた開発・販売戦略を構築できる可能性も言及されています。
グローバル展開の加速
塩野義は米欧に開発・販売拠点を有しており、グローバルに事業を展開しています。本取引を通じて、鳥居薬品(現在はJT医薬事業と共同で国内開発を遂行)の将来の開発品をグローバル展開できる可能性が高まるとしています。塩野義の海外での薬事・販売ノウハウを鳥居薬品のパイプラインに適用し、国内外でのデータ収集・評価を重ねることで販売力強化につなげる狙いです。
また、鳥居薬品が積極的に行ってきた医薬品候補の導入探索や事業投資の活動にも、塩野義グループのネットワークや専門人材を活用することで、より効率的かつ有効な取り組みが可能になるとされています。これは塩野義のグローバル戦略と鳥居薬品の開発力を融合させ、国際市場での競争力を高める意図と言えます。
製造・供給体制の柔軟化
塩野義はグループ内にシオノギファーマ株式会社という製造部門を持ち、原則として自社工場で医薬品を製造してきました。本取引後、鳥居薬品やJT由来の医薬品についても塩野義の製造拠点・グローバルサプライチェーンを活用することで、生産能力の増強やバックアップ体制の確保が可能となり、供給リスクの低減や製造コストの削減に資するとしています。地政学リスクや原材料高騰に伴う供給不安が高まる中、グループ内で柔軟に製造拠点を融通しあえることは競争力強化につながります。
以上のように、塩野義製薬は鳥居薬品の完全子会社化によって販売網・開発力・製造基盤の統合効果を得て、自社の中長期ビジョン実現を加速させる狙いです。特に、機動的な経営判断を行うためには上場廃止によるグループ一体運営が不可欠であるとの認識が示されており、本TOBは塩野義の事業戦略と強く合致しています。
経営陣の対応(取締役会の意見・推奨と経営方針への影響)
鳥居薬品の取締役会は、本TOBに対して賛同の意見を表明し、株主に応募(株式売却)を推奨することを全会一致で決議しました。この結論に至るまで、鳥居薬品側では少数株主の利益を守るための厳正な手続が踏まれています。
まず、鳥居薬品は本取引に利害関係のあるJTが親会社である点を考慮し、2024年8月に独立社外取締役のみで構成される特別委員会を設置しました。特別委員会は法律顧問(長島・大野・常松法律事務所)の助言を受けつつ、本TOB提案の妥当性や価格の公正性、少数株主に不利益とならないか等を慎重に審議しています。取締役会は、提案内容についてこの特別委員会から諮問を行い、その答申を尊重する形で意思決定を行いました。
特別委員会の答申では、本取引(TOBおよびその後の手続)が鳥居薬品の企業価値向上に資するものであり、一般株主(少数株主)にとって不利益なものではないことが確認されました。さらに、「取締役会は本TOBに賛同し株主に応募を推奨すべきである」との勧告がなされています。この答申を受け、2025年5月7日開催の鳥居薬品取締役会において正式にTOB賛同と応募推奨の決議が行われた旨が開示されています。本決議には、過去にJTに在籍していた経歴を持つ近藤紳雅社長も含め、鳥居薬品の全取締役が参加し賛成票を投じています(利害関係や職務執行の特別利害により除外すべき取締役が存在しないことが確認されたうえでの決議)。
このように鳥居薬品経営陣は、本TOBが同社の将来にとって有益であり少数株主にも配慮されたものであるとの判断を示しました。経営方針への影響としては、TOB成立後に鳥居薬品が塩野義製薬の完全子会社となることで、塩野義グループの一員として事業運営方針が統合される点が挙げられます。上場廃止によるデメリット(社会的信用や人材採用への影響など)について取締役会でも検討されていますが、「長年培った信用は上場廃止によって失われるものではなく、むしろ塩野義グループとして一体となった採用活動や共同マーケティングにより十分カバー可能である」と判断されています。また塩野義側からも、従業員の処遇について慎重に検討し、離職による悪影響が生じないよう最適配置に努める方針が示されており、買収後の経営体制移行が円滑になされる見通しです。総じて、鳥居薬品の経営陣は本TOBを企業価値向上の好機と捉え、賛同・協力する姿勢を明確にしています。
株主への影響(TOB価格の妥当性、プレミアム、少数株主への配慮)
本TOBにおける買付価格は1株当たり6,350円に設定されており、この水準は市場株価に対して大幅なプレミアムを含んでいます。提案公表前営業日である2025年5月2日の終値5,230円に対して約21%の上乗せとなり、直近1ヶ月平均株価(約4,397円)比で約44%高、3ヶ月平均比で約42%高、6ヶ月平均比でも約39%高と算定されています。
特に、TOB交渉過程で鳥居薬品側の特別委員会が価格引き上げを強く要請し、最終的に提示された6,350円は「これ以上交渉の余地がない最終提案価格」との認識が示されました。この価格水準は、第三者算定機関であるみずほ証券が用いた複数の評価手法(市場株価基準法・類似会社比較法・類似取引比較法・DCF法)の算定レンジ上限をいずれも上回る水準であり、公正な価格であることが確認されています。つまり、客観的な株式価値評価から見ても本TOB価格は妥当であり、少数株主にとって魅力的なプレミアムが提供されているといえます。
また、本取引の構造自体にも少数株主への配慮が表れています。親会社JTは保有する鳥居株(全株式の約54.78%)について本TOBには応募せず、TOB成立後に鳥居薬品による自己株式取得(いわゆる自社株買い)で処分するスキームが採られました。具体的には、JTが売却する株式の価格(1株4,568円)はTOB価格6,350円より低く抑えられており、その分を少数株主への買付価格に上乗せすることで「少数株主への配分をより多くし、TOB価格の最大化と株主間の公正性の両立」を図っています。このように多数株主であるJTが敢えてディスカウントを受け入れる形とすることで、一般株主はより高い対価を得られるように設計されています。税務上もJTにとって有利になるよう調整された結果の価格設定であり(みなし配当課税を考慮した調整)、少数株主に不利益を転嫁しない工夫といえます。
さらに、手続面でも「公正性担保措置」が徹底されています。前述の通り特別委員会の設置や独立専門家による評価が行われ、みずほ証券から株式価値算定書を取得して価格交渉の材料としました。みずほ証券の報酬体系に成功報酬が含まれる点についても特別委員会で検討され、一般的な慣行範囲内で独立性が損なわれるものではないと確認されています。なお、公正意見(フェアネス・オピニオン)は取得していないものの、複数手法による評価結果や交渉過程から少数株主の利益が十分に確保された妥当な取引であるとの結論に至っています。特別委員会も「本取引は公正な手続を経ており、これを通じて少数株主の利益に十分な配慮がなされている」と認定しています。
株主への影響として留意すべきは、TOB成立後に鳥居薬品株式が上場廃止となる可能性が高いことです。塩野義は買付予定数の上限を設けておらず、TOBの結果次第では東京証券取引所の定める基準に従い上場廃止手続きが進められます。実際、本TOBでは応募下限株数が設定され(発行済株式数の3分の2に当たる株数を想定)、それを満たせば少数株主が残存する場合でもその後の株式併合等の手段により最終的に塩野義のみが鳥居株を保有する形を企図しています。
したがって、一般株主にとっては本TOBに応募してプレミアムを享受することが合理的な選択肢となります。仮にTOBに応募せず残った場合でも、最終的には法的なスクイーズアウト手続により現金で売却される見通しであり、その際も経済的待遇はTOB価格と同等になるよう配慮されるものと考えられます(少なくとも本件構造上、JTを除く株主間の公平性が図られる設計となっています)。総合的に見て、本TOBは株主、とりわけ少数株主の利益に十分配慮された内容となっており、提示価格・手続の両面から公正性が担保されています。
業界への影響(製薬業界・同業他社へのインパクト)
今回の鳥居薬品に対するTOBは、日本の製薬業界における企業再編と選択と集中の動向を象徴する事例といえます。まず、JTという非製薬業種(たばこ事業主体)の企業が医薬事業から撤退し、専業の製薬企業である塩野義製薬がその事業を吸収する形となった点は注目されます。実際、JTは今後たばこ事業に専念する方針を明確にしており、本取引により塩野義がJTの医薬関連会社まで含め約1,600億円規模で買収することになりました。このように異業種親会社が医薬品子会社を手放し、本業に経営資源を集中させる動きは、他のコングロマリットや異業種企業にも波及する可能性があります。例えば、飲料・食品・化学メーカーなどが保有する医薬品事業についても、同様に「事業ポートフォリオの最適化」の観点から売却や統合が検討される契機となり得ます。
一方、買収側の塩野義製薬にとっては、感染症領域など自社の強みを補完する製品ポートフォリオや販売チャネルを獲得することで、国内市場での地位強化やグローバル展開加速が期待できます。これは競合他社にとって脅威であると同時に、業界全体で大型買収による成長戦略が一段と活発化する可能性を示唆します。実際、本TOB価格に含まれるプレミアム水準(市場株価に対して約40%超)は、日本企業による同種のTOB事例の中央値と比較しても遜色ない水準であると分析されています。このことは、国内製薬企業が魅力ある事業・技術を持つ企業を取り込むために相応のプレミアムを支払う用意があることを意味しており、今後も業界再編が進む中で株式市場の評価を上回る買収提案が出され得ることを示しています。
さらに、本件のように上場子会社を完全子会社化してグループ最適を図る動きは、他の製薬大手とその子会社の関係にも影響を与えるでしょう。親子上場の解消は近年の潮流でもあり、製薬セクターにおいても研究開発費の集中投下や経営効率化のために同様の決断がなされる可能性があります。例えば、塩野義と同様に新薬創出力を強化したい製薬企業が、提携関係にある専門領域企業を買収するといったケースや、外資系製薬大手が出資先の日本企業を完全統合するといったケースが考えられます。今回のTOB成立により、鳥居薬品は塩野義グループの一員として非公開化される見通しですが、このことは「上場維持の意義」を再考させる契機ともなり、他社も自社グループ内の上場子会社の在り方について検討を深める可能性があります。
総じて、本TOBは製薬業界における資本再編・提携戦略に一石を投じる出来事です。今後、専門領域を持つ中堅製薬企業とそれを取り巻く親会社との関係に変化が生じる契機となり得るでしょう。同業他社は塩野義と鳥居薬品の統合による市場ポジション変化を注視すると共に、自社の競争戦略(提携強化か単独路線維持か)や資本政策について再評価を迫られるかもしれません。
類似企業の例とTOB候補となり得る理由
鳥居薬品と類似した特徴(親会社による高い持株比率、事業領域の補完性、規模や上場維持の是非など)を持つ上場企業について考察してみたいと思います。それぞれ、親会社との資本関係や戦略上の状況から、鳥居薬品同様に「完全子会社化」または「親会社による売却」の候補となり得る理由を述べます。
規模が大きめの会社
以下3社はいずれも親会社が半数超の株式を握り支配権を有している点で鳥居薬品と共通し、現在は上場維持による独立経営を行うものの、親会社の戦略変更や業績動向次第では非公開化によるグループ再編が現実味を帯びる可能性があります。少し規模が大きめなのでTOBの可能性は大きくないかもしれませんが、簡単に3社ほど紹介をさせていただきます。
- 協和キリン(証券コード: 4151) – キリンホールディングスが株式の約54%を保有する医薬品メーカーです。親会社のキリンは飲料事業が主軸ですが、医薬・バイオ事業にも進出しており、協和キリンはその中核子会社となっています。協和キリンはがん・免疫領域のバイオ医薬品に強みを持ちますが、親会社から見れば事業ポートフォリオの一部であり、戦略次第では完全子会社化してグループシナジーを追求することも、あるいは医薬事業の選択と集中の中で外部へ売却する可能性も考えられます。実際、協和キリンは上場子会社であるがゆえに独立性が保たれつつも、キリン本体の経営戦略との調整が必要な場面もあります。将来、キリンがヘルスサイエンス事業への本格注力や再編を図る際には、少数株主を抱えた現状よりも完全支配下に置く方が迅速な意思決定が可能となるため、TOBによる株式取得が選択肢に入るでしょう。
- 中外製薬(証券コード: 4519) – スイスのロシュ社が議決権ベースで約61%(発行済株式の約59.9%)を保有する日本有数の創薬企業です。中外製薬はロシュグループの一員として研究開発面で協働しつつ、日本において独自の上場企業として経営を行ってきました。ロシュは過去に米国のジェネンテック社を段階的買収で完全子会社化した経緯があり、中外製薬に対しても将来的に完全統合を図る可能性があります。現時点でロシュは中外の独立性を尊重しオープンイノベーション戦略を採っていますが、グローバル競争が激化する中で研究開発の効率化や知財の一体管理の必要性が高まれば、残り約40%の株式をTOBで取得して中外製薬を非公開化するシナリオも考えられます。その際には、今回の鳥居薬品のケース同様に高いプレミアムが提示される可能性があります。親会社ロシュから見たシナジー最大化と、日本市場での機動的な事業展開を実現するための手段として、中外製薬はTOB検討候補の一つと言えます。
- 住友ファーマ(証券コード: 4506) – 住友化学が議決権の約51.7%を有する国内製薬大手です。中枢神経領域などでグローバル展開を図っていますが、近年は開発品の遅れや業績面での課題も指摘されています。親会社の住友化学にとって住友ファーマは医薬品事業の中核子会社ですが、化学事業本体とのシナジーが相対的に薄いことや、経営資源集中の観点から完全子会社化による機動的な経営改革を検討する可能性があります。実際、住友化学は他の子会社(例えばかつての三菱ケミカルによる田辺三菱製薬の完全子会社化など同業他社の動き)を踏まえ、自社グループの効率化を模索しています。住友ファーマを非公開化すれば、短期の株式市場の評価に左右されずに大胆な研究開発投資や事業再編を行えるメリットがあります。加えて、株式市場での評価が低迷した場合には親会社としてTOBに踏み切るインセンティブが高まるでしょう。以上より、親会社が過半数を保有する上場企業として、戦略次第でTOBの対象となり得る典型例として住友ファーマが挙げられます。
★参考記事:【TOB候補】協和キリン(親子上場)
中堅・小型で “鳥居薬品型” TOB のシナリオが描きやすい 2社
次に、鳥居薬品のように少し規模の小さめの会社にも目を向けてみたいと思います。こちらの方がTOBとしては実現しやすい金額感かもしれませんので、簡単に銘柄紹介だけしておきたいと思います。
| 銘柄 | 親会社等の持株比率(議決権ベース) | 時価総額* | 着目ポイント | なぜ TOB の思惑が高まりやすいか |
|---|---|---|---|---|
| ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング (J-TEC 7774 東証G) | 帝人 57.7 % | 約250億円 | 再生医療ベンチャー。売上はまだ小さい。 | 過去に富士フイルムが親会社であったところ、帝人がTOBで親会社になった背景がある。 |
| 生化学工業 (4548 東証P) | 大株主分散(筆頭でも14 %)だがPBR 0.5倍 | 約400億円 | ヒアルロン酸関節注射でニッチ首位。ロイヤリティ減少で業績調整局面。 | 支配株主不在+割安バリュエーション(PBR 0.5倍)は“買い手フレンドリー”。科研製薬や参天製薬が国内販路を担うなど依存関係が強く、販売委託元が「安定供給確保」を名目に TOB に踏み切る余地がある。 |
*時価総額は 2025 年5 月2 日時点終値ベースの概算。
まとめ
鳥居薬品のTOB事例は、こうした親子上場企業における少数株主の位置づけや上場継続の意義を改めて問い直す契機となり得ます。将来的に市場環境や親会社の経営判断によっては、これら類似企業にもTOBの波及効果が及ぶことが考えられます。ぜひ、製薬企業業界を注視しておきたいですね。
さいごに
最後にプレミアム狙いの事前投資戦略についても触れておきます。
親子上場関連株は「いずれTOBでプレミアム獲得できるのでは」と期待して先回り買いする投資家が増えてきていると思います。実際、親子上場解消が噂されると株価が思惑で上昇することもあります。ただし、いつTOBになるか確証はなく、長期間放置される可能性や、最悪基準未達で上場廃止(TOBなしで株主が市場で売る機会を失う)リスクもあります。したがってこの手法は中長期のリスク許容度がある中級者以上の投資家向きともいえます。
当サイトでもTOB候補銘柄を紹介していますが、不確実性の高いなかでTOBだけを目的に積極的に買い向かうのは得策ではありません。TOBだけを目的にすると、TOBが実行されるまでは機会損失を被ることも多いので、必ずTOBとあわせてプラスαの材料をもつ銘柄に投資をしておきたいところです。
プラスαの材料としては、たとえば以下のようにTOBがなくても株価が上がったり、リターンが見込めるような銘柄が理想的です。
- TOB+高配当
- TOB+黒字化銘柄
ぜひ、「TOB+α」の銘柄を探してみましょう!